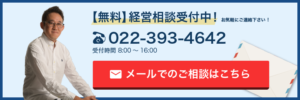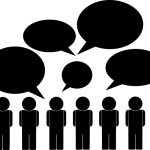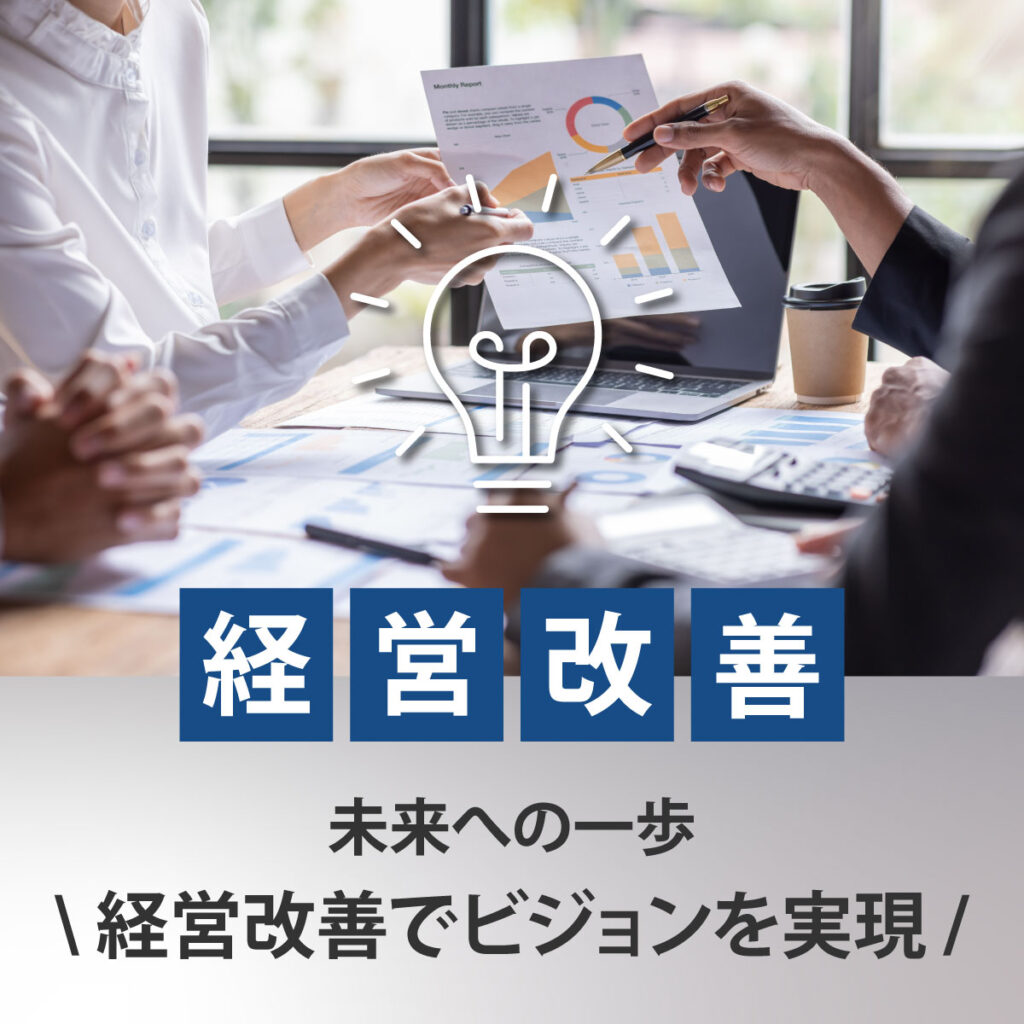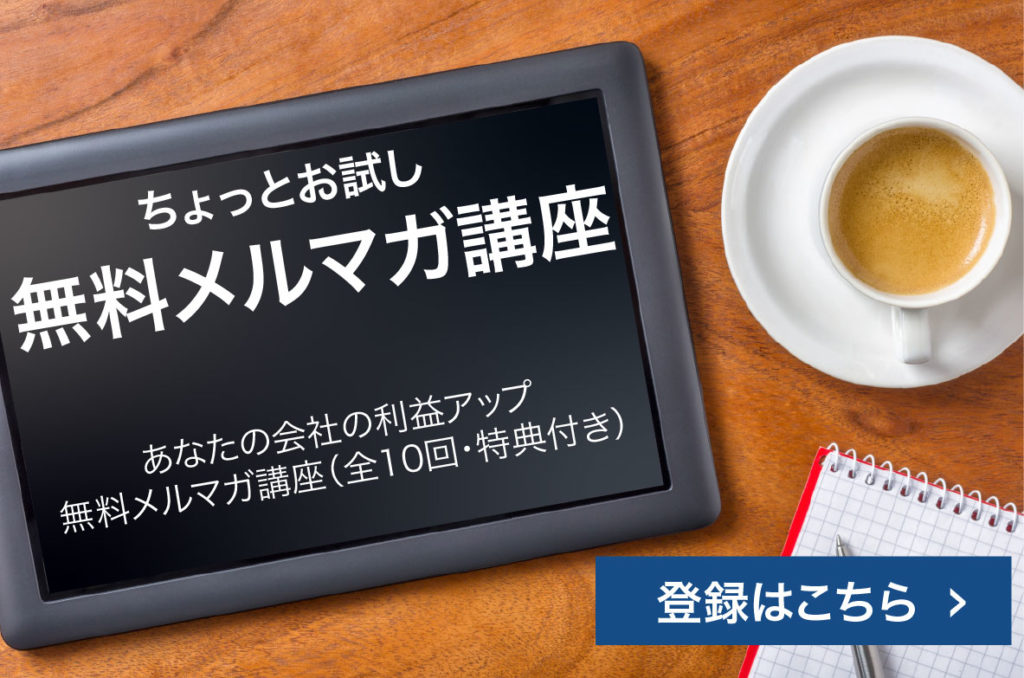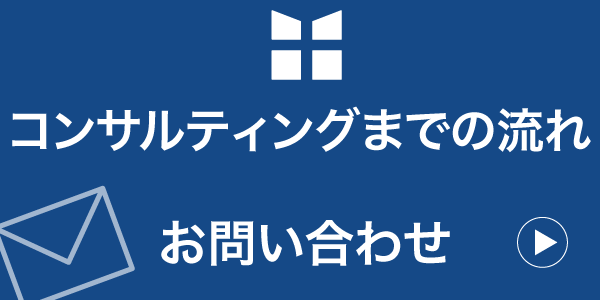中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント 本田信輔です。
「観光市場に出れば売上は伸びる」
そう思って参入し、うまくいかずに撤退した地域密着型菓子店を何社も見てきました。
今回のテーマは「地域密着型菓子店の観光市場参入について」です。
・昨今の価格上昇で既存客の買い控えが続いている。
・地元人口がどんどん減少していて将来の売上が不安。
・近隣に道の駅や観光地があり、そこには多くのお客さんが来ている。
・地元企業として、地域の名物となるような土産菓子を作りたい。
こんな理由から、地域密着型菓子店が観光参入を目指すケースが増えています。
ですが、実際はどうでしょうか。
一部の大きな菓子ブランドが地元に自ら観光拠点を開発し、市場参入を達成するケースはありますが、
多くの地元密着型菓子店は苦戦をしているのが現状です。
一方、
・道の駅や観光物産館に商品を置いてもらったのに、思ったほど売れない。
・観光地の良いところに出店したのに、売上が取れない。
・地元素材を使って、観光向けに商品を開発したのに、全然売れない。
・地域では知られている部類に入る菓子店のはずなのに、なぜ苦戦する?
・良いものを作っているはずなのに、観光では評価されない。
このような悩みは相談を受けることも少なくありません。
なぜ、このようなことが起こるのか。
今回のテーマは地元密着型菓子店が「観光市場で失敗しないコツ」を、ぎゅっとまとめてお伝えします。
【地域密着型菓子店が観光市場で失敗しない6つのコツ】
目次
(1)地域とのつながりを“編集”して観光価値に変える
観光客が求めているのは、「その土地でしか買えない理由」です。
この点は、地縁性の高い地元菓子店が強みにできることなのですが売れない。
なぜならば・・・地縁性を観光用に“編集”していないからです。
よくありがちな、
・地元にある菓子店が作った
・地元の素材を使った菓子
だけだと、「その土地でしか買えない理由」としては弱いんです。
実際に全国の観光市場で売れている菓子を思い出してください。
悲しいことに。全国で売れている名物土産(菓子に限らず)の多くは、地元素材を使っているとは限りません。
観光で売れている菓子の特徴は、“地域の文化・歴史・風土、物語、人物、技術”などのストーリー性を全面に押し出した商品です。
観光市場において地縁性を発揮するためには、“地元の菓子店が、地域の素材を使って作ったお菓子“を当たり前とせず、地域のストーリーを編集して、観光客にとってわかりやすい商品名・商品の形状・パッケージ・POPなどと組み合わせて、落とし込むことが第一歩。
逆に言えば、自店でどれだけ売れている主力商品であっても、観光市場ではパッケージやネーミング、伝え方を変えないと売れるのは難しいことが多いです。
(2)観光客に買ってもらえるように、「お土産規格」に仕立て直す
地元の人に売れていても、観光客に売れない理由はお土産としての「持ち運び・利用シーン」にあっていないことが多いー“お土産としての使いやすさ”がないことです。
観光客は「お土産規格」でなければ、なかなか買いづらい。
・日持ちする(日持ち数ヶ月などは逆に嫌われるが、できれば最低5日程度は欲しい)
・個包装(お土産としての配りやすさ)
・手荷物でも崩れない、運びやすいパッケージ
・持ち運びの温度管理(常温が絶対条件ではない。冷蔵や冷凍で持ち運び可能の場合は保冷を前提としたパッケージや、持ち運び時間等の情報提供対応が必要)
・お土産としての価格設定(500円、1,000円、2,000円が黄金ライン)
もちろん、駅や空港など公共交通機関を主とした観光交通拠点と、車移動を前提とした道の駅や観光地でニーズの違いはありますが、どちらにしても観光規格への対応が必要です。
既存商品を観光市場で展開する場合は、商品の大きさや容量などを変更し、単価を新たに設定しながら、観光価格に対応することも視野に入れて検討します。
これらを考えながら、商品を観光用に見直すだけで、売れる可能性が大きく上がります。
(3)地元の中小菓子店にとって“限定性”は武器になる
大量生産、パッケージを変えただけのどこでも売っているいわゆるレール菓子といったお土産を好まない観光客は間違いなく増えています。
観光客に求められるのは「この場所だから。地元にはないから。今しか・ここでしか買えないから。買う」です。
その点で、中小菓子店が訴求できる“限定性”は大きな強みになります。
・地域やエリア、施設限定(駅や空港限定、店舗限定、○○エリア限定など、地元製造の機動性や小ロットの製造体制を活かす)
・期間限定(定番+春限定、雪国限定)
・数量限定(作りたてや手作りのであることを活かす、1日50箱限定など)
限定性は、ブランド力や商品の価値、話題性を高めます。
自分たちが今持っている技・設備などを上手に活かした”限定性”を考えることで、地元観光に新たな風を吹かせることも可能ですね。
(4)店舗を構えるときは、製造工程・職人技を見える化する設計を重視する
もしも観光立地に店舗を構える場合には、職人の存在、手作り、出来立て感を見える化することに重点をおいた店舗コンセプト・設計をオススメしています。
今の観光においては、お土産を買う以上に、誰かに話すことができる体験が加わった商品・サービスへの価値が高まっています。
職人技や製造工程を見たり、感じたりすることは、自分たちや地元の人にとって当たり前に知っていることであっても、観光客にとっては「非日常の体験」となることがたくさんあります。
それらを“見せる、体験・体感してもらう”ことで話題性が上がったり、お客様自身がSNSに写真や動画を投稿・拡散してもらえるなど、認知度向上や集客力につながるメリットも期待できます。
(5)観光導線を意識して、どこで売上を獲得するか考える
理想は ー 今ある自分のお店に観光客が目的を持って来店してくれることです。
これは、誰もが願うことだと思いますし、当社のクライアントさんにも最終的に自店集客してもらいたいと考えています。
ですが、観光市場で単品やブランドの知名度が上がらないうちは、これがなかなか難しい。
売上を取るためには、どうしても観光客の集まる場所“観光集積地”で商品を展開して、認知度を上げていくことが必要。
・駅や空港などの公共交通拠点
・高速道路のSAやPA
・道の駅や産直施設
・観光物産店
・温泉や景勝地、歴史的建造物などの観光施設やその周辺
特に《道の駅》などは、地域のものを求める観光客が多く集まりやすく、地元企業として入りやすい特徴がありますので、商品作りや売り場づくりを考えた上で展開することが良いと考えています。
ただし。こういった場所に商品を展開する場合は、卸価格・掛け率・販売手数料といった設定も外せません。商品ごとの生産性も考慮して、どういった品種の商品であれば観光マーケットで売れて、会社の収益に貢献できるか、戦略的に考えていく必要があります。
(6)多品種展開はNG。強い単品作りを目指す
よくあるお悩み事に、ー道の駅やお土産店で売り場をもらったのに、売上が取れないー ということがあります。現場を見てみると原因は一目瞭然・・・それは“多品種の商品を並べているから〜並べすぎているから”です。
売上が欲しくて、自分のお店に並んでいる商品を色々陳列したい気持ちはわかりますが、観光客が求めているのは、これぞという単品。バラバラといろいろな商品が並んでいても、スルーされやすい。それが観光マーケットであり、ある程度の品揃えを求められる地元商圏を対象とした商いとの大きな違いです。
多品種展開をしてしまうことで、売り場の中での認知度も下がりますし(観光市場で認知度を上げたいのは、企業ブランドではなく、まずは単品名です)、在庫管理リスクや売上分散といったデメリットも多くなりますので注意してください。
大事なのは、
・まず1品だけ強い単品に集中する
・単品で、パッケージは複数サイズで展開する(入り個数、価格帯ごと)
・認知度と売上が軌道にのったら、横展開の派生商品を投入する
強い単品を軸として認知度を上げることは、結果としてブランド認知度が早く上がることにつながります。
菓子業に限らず、食品業全体に言えることですが、企業名・ブランド名よりも、単品知名度の方が強くなることが多いです。(商品名は知っているかど、製造している企業名は知らないケースが多い)
逆に気をつけて欲しいのは、自分たちの知名度を観光市場で過信しないことです。
長く菓子業に関わっている方にとっては“あそこの地域には、有名な○○という菓子屋がある”と知っている業界ならではの知識や情報があります。ですが、観光客は一般の方々。自分たちが思っているほど店舗名も主力商品も知られていないと思ってスタートした方が良いです。
まとめ
この記事は実際に観光市場に参入を検討、実際に取り組んだ菓子店の相談内容をもとに構成しました。
ここまでお読みいただいて、
「うちはどこから手をつけたら良いんだろう」
そう感じた方がいるかもしれません。
観光市場はやり方を間違えると、時間もコストも浪費し、現場を疲弊させてしまいます。
私は、地域密着型菓子店が「観光という市場に振り回されず」
売上と利益を伸ばす取り組みを現場と一緒に考えてきました。
もしも、
- 今のやり方で本当に良いのか?
- このまま、諦めて撤退する前にやれることはないのか?
- 観光に出るべきか、迷っている
そんな状態であれば、一度整理することだけでも意味があります。
実は、
わざわざ新商品を作ることをしなくても、
既存商品を仕立て直すだけで観光対応できるケースも少なくありません。
中小企業・地元密着型菓子店だからこそ実現できる観光参入があります。
焦らず、振り回されず、
「自社にとって、本当に意味のある形」を考えてください。
観光参入に関する経営相談(初回無料)は下記フォームより受け付けています。