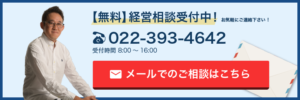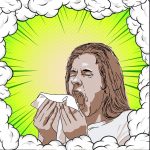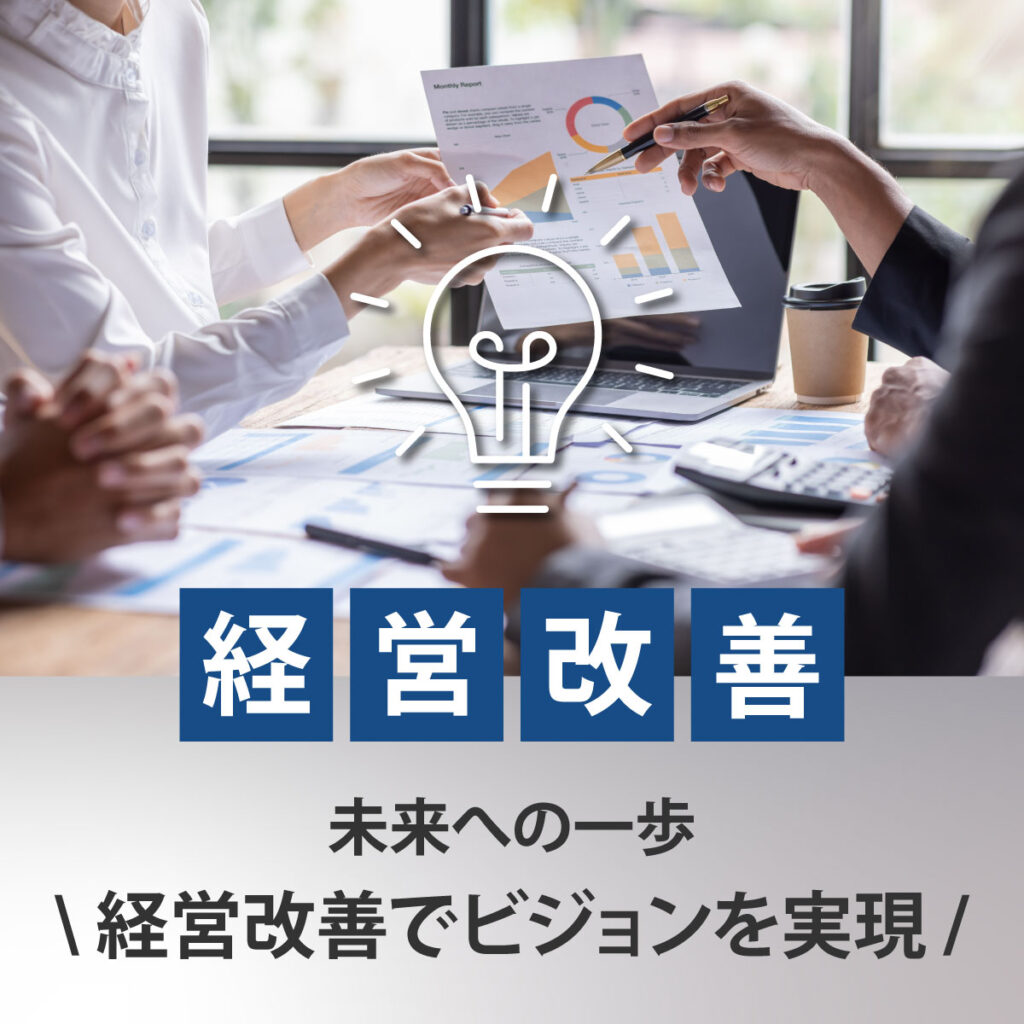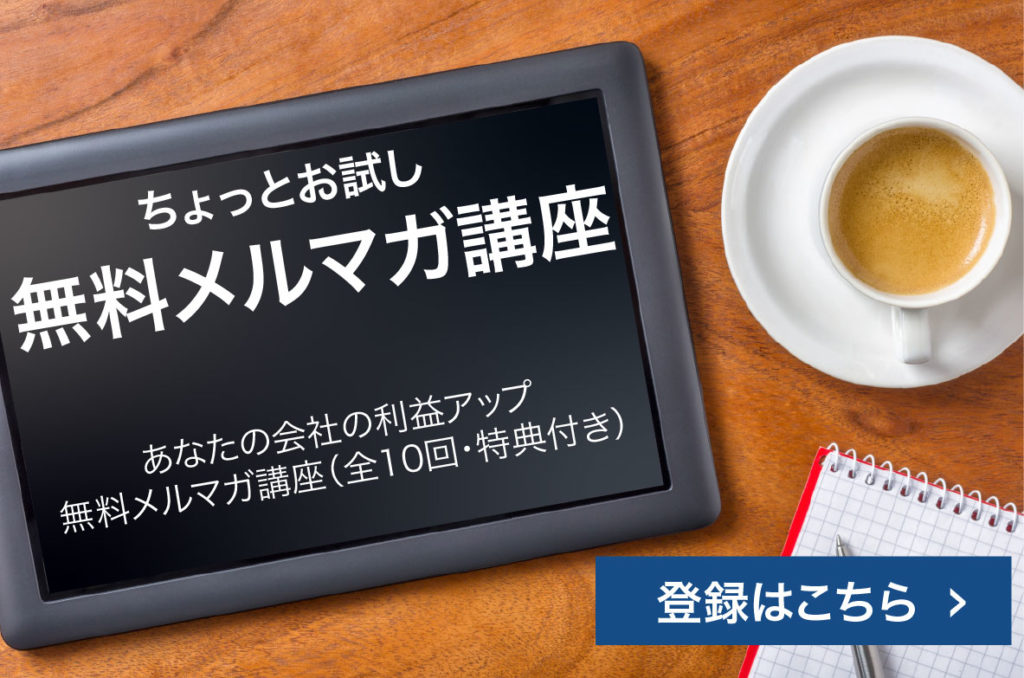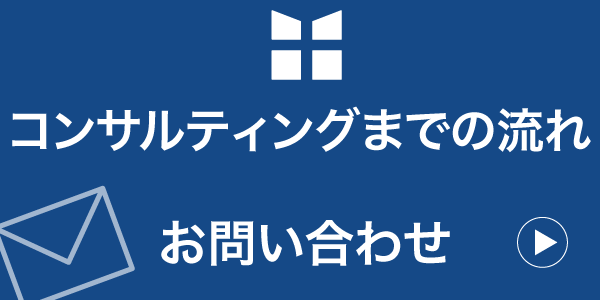中小企業の利益を3倍にする経営コンサルタント 本田信輔です。
今回の事例は利益率を10%高めた飲食店のお話。
「売り上げは悪くないのに、利益が残らなくなってきている」、「近くには大手チェーン店の出店も予定され、競合店も増えてきているし、このままだと将来が不安」という相談を受けました。
事例に挙げる飲食店は東北地方の人口3万人の町にある独立飲食店。手作りと素材にこだわった料理が魅力の人気店。売上は安定していたものの、原材料費・人件費の高騰により、営業利益は低下気味。将来への不安を抱えていました。
実際に話を聞いてみると、人件費や仕入れコストの高騰、非効率なメニュー構成など、いわゆる「よくある課題」が積み重なっていました。
ところが、半年後には営業利益率は3倍。売上に対して10%も大幅に改善。しかも売上も増加。
「利益を高める」施策と決断で、大きな経営改善を実現したのです。
成果が出たあと、事例の飲食店のオーナーは
「長年、この飲食店の商売をしているけど、こんな利益率は見たことがない」とおっしゃいました。
今回は、その実例をご紹介します。
目次
1.【施策①】全メニューを対象とした「価格と価値の再設計」
強みである手作りとこだわり素材は人気店としての強みとなる一方、素材の仕込みや調理には手間がかかり、利益を圧迫する要因となっていました。
そこで、以下の施策を実施
・全メニューを対象として20%を目安に値上げ。メニューごとに一つ一つ検討し、15%〜30%の値上げを実施。
・価格見直しと同時にメニューブックをリニューアル。目玉メニューについて素材や調理法、ストーリー化して伝わるように記載を追加。特に目玉メニューについては、ページの誌面構成を見直し大きく表現することで、価値やストーリーをよる強く伝え、名物的なメニューとして表現。大胆な価格設定を行い、全メニューの基準となる価格として感じてもらえるように訴求。
これにより、「単なる値上げ」ではなく、「価値が見える」ようにすることで、常連さんにも納得してもらえ、売上を落とすことなく利益を高めることができました。
2.【施策②】非効率なメニューの統廃合とプレミアムメニューの投入
実際に話を伺っていると、素材にこだわっているだけに仕込みにはかなりの労力がかかっていました。しかも注文の少ないメニューであっても材料は用意しておかないといけない。
仕込みの手間、材料の在庫コストやロス。メニューが多すぎることによって調理が煩雑化することの非効率。価格の割に手間がかかるメニューなど。
手作りやこだわった素材が強みだからこその課題が出ていました。
これらを改善するために、
・メニューの統廃合を実施。注文が少ないメニューを廃止(全メニューの20%)、注文が季節で集中するメニューを定番から外す。
・素材の仕込みや調理に手間がかかるメニューについては、リニューアルを行い新たなメニューとし、価格を再設定。手間に対してちゃんと利益を得られるように変更。
それに合わせて、
・売れ筋の目玉メニューには新たにプレミアムメニューを新規投入し、値上げを感じさせないようなメニューを構成へと強化。
これらにより仕込みや厨房内の効率は大幅に改善。仕込み時間の短縮や、少ない人員で客数をこなすことが可能になりました。効率化とともにメニュー提供スピードも上がったことから、ピーク時の客数アップ。プレミアムメニューの投入による客単価アップで利益の底上げにつながりました。
3.【施策③】ランチタイムと宴会・宅配オードブルメニューに「高付加価値セット・コース」を追加
売上の柱の一つはランチタイムのセットがありましたが、客数は多いけど客単価が低く、利益貢献は少ない状況でした。
夜の宴会と宅配オードブルについては、2,000円、3,000円のコースが中心であったため、こちらも客数の割に利益貢献が低く、価格を下げていたことで提供する料理が少ない(魅力がない状態)となっており、自分たちの強みを発揮できない状態でした。
そこで、
・ランチタイムについては、複数あったランチセットを2プライスへ絞り込み。厨房の作業効率の高い1,000円メニューと、数量限定の高付加価値型の1,800円“ご褒美・縁起担ぎ”ランチセットを提案。
・宴会、宅配オードブルについては、5,000円、10,000円、15,000円の高付加価値コースを新たに強化。贅沢感があるコースを用意しました。
これにより、原価率は変わらないものの、同じ労力でより大きな売上を獲得(少ない人員で今と同じ売上の獲得)することができるようになりました。また、高単価メニュー・コースの投入は話題となり、利益率の改善だけではなく、そのメニューを目当てにした遠方からのお客様や、地元の法人(特に接待)需要を獲得することができ、商圏距離の拡大や新規売上、満足度向上にもつながっています。
4.まとめ「このままで良いのか?」は改善をスタートさせる第一歩
この飲食店のように、「特別な広告」や「新しい設備等への投資」ではなく、今ある強みに目を向けて、強みを活かす取り組みを強化し、強みを活かせないことをやめる。
これだけで利益率は大きく改善します。
原価率が高い → 各メニューの価値と価格を再設定 → 値上げと価値訴求をセットで行う
手間とロスが多い → メニューの統廃合 → 効率を高めるメニューへの見直し
単価が伸びない → 高付加価値メニューの導入 → 自分たちの強みを活かした価値づけ
競合が増えてきた → 価格ではなく“価値訴求”で差別化
当たり前のことと思うかもしれませんが、今までの常識や概念や思い込みに囚われて、本当の強みを活かすことができていないお店が多くあります。
・大手企業やチェーン店の戦いの中で“価格競争”の意識が強くなりすぎていないか?
・大手ほどは安くできないけどと、中途半端な価格設定やメニュー(商品)でお客様の満足度を下げていないか?
・ただ減らすだけを効率化と思い込んでいないか?
この飲食店のオーナーは「このままで良いのか?」と思ったことが、改善へのきっかけ。
中小企業や独立店には、大手にはできない強みがたくさん眠っています。
あとは、その強みに気づいて、上手に活かしていくことで、利益アップは実現します。
「このままでいいのか」と悩む方、利益を守りながら前に進みたい方へ
物価高騰と人件費増と人手不足など、経営を取り巻く環境が厳しい中でも利益を出している企業や店舗の経営者は、値上げの先にあるものを見据えています。
「利益を守るもの=値上げ」にとどまるのではなく、
・経営者も含めた従業員全体の収入を増やしたい
・地域の中で自分たちの存在が必要とされ、これからも続くようにしたい
・会社で働いてくれる人たちやその家族に、仕事に対する誇りを持てるようにしたい
・まだまだ新しいことにチャレンジして、自分たちの会社の可能性を高めたい
・次の代を見据え、強い経営基盤を作りたい
今回は、これら将来像を社内で共有し、そのための利益を確保するきっかけとして「値上げ」を実施し、利益を高めることに成功した地方にある飲食店の実例をお伝えしました。。
もちろん「値上げ」や「価格の見直し」、今までの考えからの脱却に対する不安は大きいでしょう。その悩みを一度、お話してみませんか?無料ですので、まずは現状を整理するだけでも気軽にご利用ください(※無料経営相談では当方より営業活動を行うことは一切ありません)
無料経営相談は下記フォームより、お申し込みください。