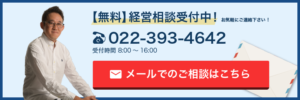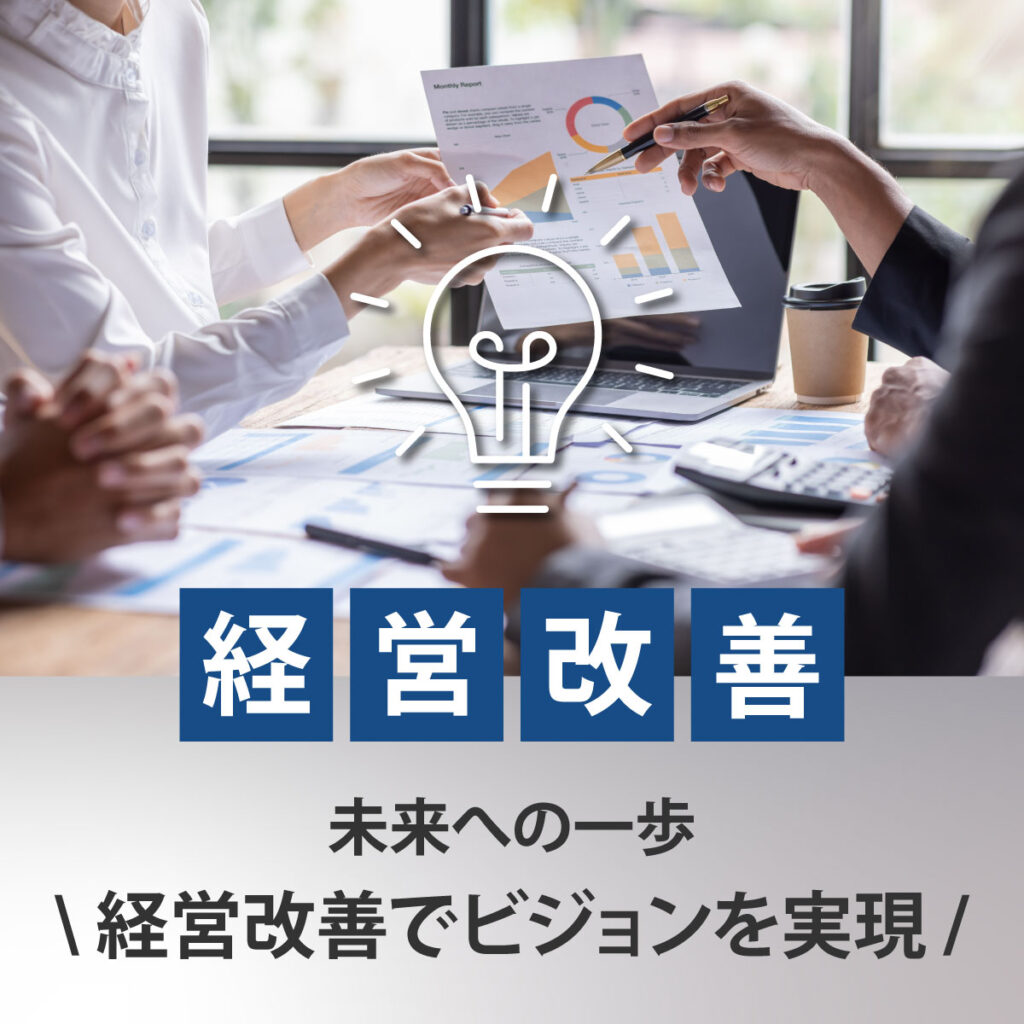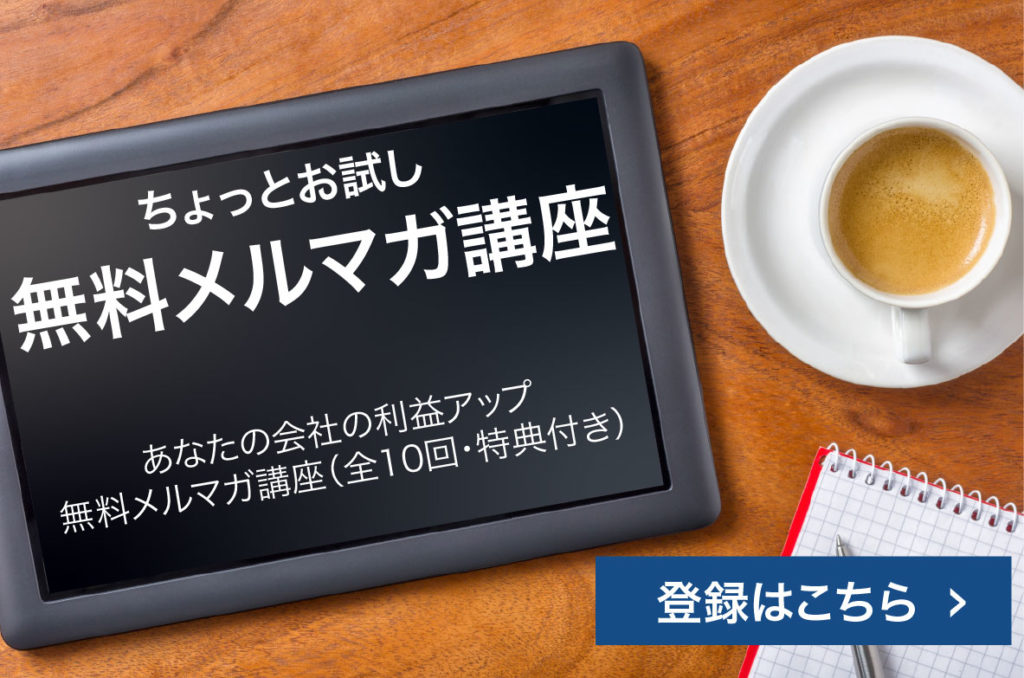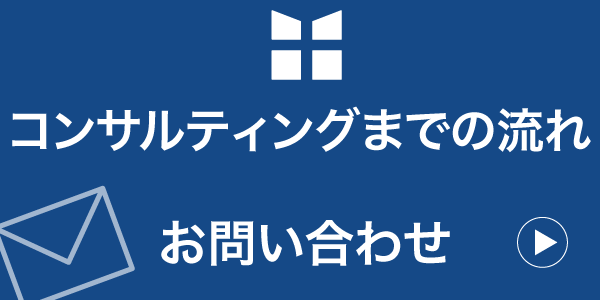中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント 本田信輔です。
今年に入り、中小企業の倒産・事業停止のニュースが毎月のように流れ、どの業界でも過去最多の倒産件数(コンサルティングの業界も例外なく)とも言われ、もはや他人事ではなく、多くの方が次は我が身と実感される状況となっています。
特に切なく感じるのは、「一時代を築き業界内でもモデルとされた企業」「老舗と呼ばれ、地元の経済や、そこに住む人たちの思い出を作った企業」「地域に根づき、看板やそこの主力商品がなくなることが惜しまれ悲しまれる存在」これらの企業が歴史を閉じていくこと。
そして報道やニュースを見ればわかるように、年商かそれ以上の負債を抱えているケースが多く、金融機関からもかなりの支援を受けながら、生き残りの道を模索し、なんとか持ち堪えようとしたけれども、厳しかったということを示しています。
新型コロナ以降も売上が回復しなかった。大手チェーン店の出店で競合環境が厳しくなった。原材料やコストの高騰が経営を圧迫した。どれか一つが理由の原因と済まされる単純なことではなく、複合的な要因が重なった結果であろうと感じます。
この状況の中で、今事業を継続できているということ自体が、すでに価値であり、この記事を読んでいただいている経営者の方には、これまでの経営に自信を持っていただいて良いと思えます。
ただ同時に、これから生き残っていくためには「中小企業として自分たちの経営」を見つめ直し、「これからの時代にどう価値を届け続けるか」を一層真剣に考え、経営戦略や現場に反映させていく必要があります。
1.値上げは覚悟。続けるための意思表示にする
事業停止や破産の要因として、真っ先に挙げられる売上の低迷と、原材料等の高騰による利益率圧迫。この二つが重なり、急激に経営財務や資金繰りを悪化させた。
確かに原材料や人件費などのコスト高騰は間違いない。ただ考えなければならないのはコスト高騰を価格にどれだけ転嫁できたか。上昇するコストに対し値づけ意識をどう変えたかという点です。まさにそこが経営の分水嶺だったと考えます。
実際、倒産に至った企業の多くは
「価格を上げれば、お客様が離れ、買ってもらえなくなる」
「地方の物価に合わない」
「大手チェーン店やコンビニと比較して」
「取引先との契約がネックになっている」
などの理由で、価格を見直すことができなかった、あるいは値上げを少ししかできなかった、値上げに踏み切るまでに時間がかかってしまったケースが目立ちます。
逆に踏み切れた企業は次のように対応をしています。
・値上げしても選ばれる理由を明確にした
・商品構成を見直して、価格転嫁しやすい主力商品に集中した
・サービスや提供方法を見直して、価格以上の「価値・体験」を提供できるようにした
・改めて商品説明や訴求を見直し、消費者へ商品の価値を高める取り組みをした
価格を変えること、値上げするということは、どうしても「失うこと」が先行してしまいます。多くの経営者はここで悩みます。大手チェーン店が競合店と価格で比較される。そんな思いもよくわかります。
ですが、コストの上昇は続くし、高騰したコストが下がることも考えづらい今、「値上げ=逃げ」ではなく、「事業を続けるためのきっかけ」として選択した企業が、結果として残っている。
これは、中小企業の経営として大きく考えていく大事な視点です。
そして、もう一つ。大事なことは
価格転嫁を“できなかった”のではなく、“する準備ができていなかった”のかもしれないということ。
人件費は毎年上昇していました。将来を見据えれば今と同じ仕入れ金額で続けていけないこともわかっていたはず。AIやDXが進む中、さらなる機械化を進める大手企業との価格競争では勝てず、価値で戦うことで生き残っていくとわかっていたはず。
値上げをする、時代ともに価格を上げ続けていく必然性を感じていたはずのなのに。
値上げをするための材料(社内の意思、商品力、人材育成)を整えたり、準備することができていなかった。その点において、生き残っていくための経営を変える第一点は、ある意味「値づけ、値上げに対する覚悟=続けるための意思表示」を持つことだと思います。
「なぜ、価格を上げるのか」を明確にする。その上で何をするかを考えることが必要です。
2.“常識”を超えて、強みを活かした価値を創る 〜中小企業だからこそできる、価格以上の納得づくりサイクルへ〜
前項で値づけ・値上げの意識を変えることについてお伝えしましたが、やはりこれだけ国内で値上げの流れが続いていると、お客様も取引先も単なる値上げではなく、値上げした価格以上の価値を求める意識が高まっていると感じます。
「価値が上がらない、他と変わらないのであれば安いほうが良い」この消費者の視線・意識も厳しくなっています。
値づけ・値上げとともに“価値を高めていくこと”。
その根幹となるのは“あなたの会社の強み”です。
どこだったら、どうやったら「自分たちの強みをいかし、価値を高めることができるのか、自分んたちの強みを活かせる場所はどこか」
このことを、今までの常識を取り払って考えていく時代に入っています。
今、具体策として何をしたら正解かわからない という迷いの多い時代だからこそ、今までの前提(常識)をリセットして、「お客様・取引先の目線」×「自社の強み」から価値を再構築し、具体策へ落とし込んでいくことが、事業を継続するための戦略につながります。
=ある会社の話をします=
この会社は地方にある老舗和菓子店。経営相談を受けた時、経営状況は大きな赤字を抱え、かなり厳しい状態になっていました。金融機関や会計事務所からも経営改善を求められ、全国の優良企業の経営指標と比較して、コストがかかりすぎている項目の改善を指摘される。
その一番の対象となっていたのは製造部門の人件費。利益を出している同業他社から見れば2倍かかっている。誰もがここを指摘し、人件費の削減を求められる状況でした。
ですが一歩深めてみると、この会社の製造人件費は大手チェーン店や競合他社にはない大きな強みになると私は判断しました。なぜなら、、、、この会社は若い年齢のうちから従業員を雇い社内で和菓子職人として育て、工場には「手作りで菓子を作れる」人材が多くいたのです。
私の提案は「和菓子職人が工場ではなく、お店で、しかもお客様から注文をいただいてから菓子を作る」です。
多くの菓子店では工場で菓子が作られ、お店に届けられ、店頭に並びます。お客様は美味しいお菓子を買うことはできても、それを実体験として手で作っている姿を見ることはできない。
これは自分たちの価値をさらに高めるチャンスだと考えました。この和菓子店に来られたお客様は、目の前で和菓子職人が自分の注文したお菓子を一つ一つ作る姿が見える。しかも出来立て(より鮮度が高く、美味しいお菓子)を買うことができる。これにより商品価格を1.2倍以上にしても、満足してもらえる価値を生み出したのです。
この事例はまさに「コスト=悪」ではなく、「コスト=価値の源泉」に転換した事例です。
・自分たちや他者が“弱み”として見るものを“強み”に変えた視点を持つ。
・一般的に削減対象とされる「人件費」を一歩深めて“強み”にする。
・「若手を育てる社風」がある=未来への投資がすでにできている企業文化の強み。
・体験価値として、お菓子を“見る・選ぶ”から、“関わる・待つ”へ。
・他社にはできない商品の“作りたて、出来立て”という時間的な価値が価格に。
・「技術が見える和菓子店」「体験型和菓子ブランド」への進化。
これはあくまでもこの和菓子店の場合。
どの会社にも“強み”はありますが、それが他社と同じということはまずありません。
あなたの会社ならでは強みが輝くところ・ことを考える。
その際、今までの常識や概念を一度、外して考えてみてください。
コンサルティングや経営相談の場で強く感じるのは、
「これが当たり前」「これしかできない」「うちの規模では無理だ」といった、自分たちで作った“限界の枠”にとらわれてしまうこと。ですが時代は大きく変わっています。消費者や取引先、直販に限らず企業間取引でも新しいニーズが生まれています。
その中で、自分たちが作った制限(限界の枠)の外側に、本当の強みを活かせる場があることが多くなっています。
・“効率化”や“標準化”を求めて削ってきた部分に価値が埋まっているかもしれない
・“他社がやってるから”を一度忘れる
・“お客様や取引先が求めていない”という先入観を捨てる
・社内で当たり前になっていることに中に、実はすごいことはないか?
・今まで通りの売上や利益の獲り方でいいのか?
・今まで通りの人の配置・動かし方で良いのか?
中小企業には大手企業ではできない“唯一無二と言える強み”がたくさんあります。
それを「今までの常識を外した視点を持ち、強みを一歩深掘りし、価値として表現・具体化し、価格以上の納得を提供する」サイクルを作ることが、これからの時代の経営において重要になってきています。
今の時代に企業を続けるということは、決して当たり前のことではなく、毎日が選択と覚悟の連続です。ですが、これまで積み重ねてきた歴史、地域との関係、そして自社にしかない強みを未来へつないでいくことは、今だからこそできる価値ある挑戦の時とも感じます。
「このままで良いのか」と悩みを抱えているなら、それは変化のきっかけ。
「どうにかしなければ」と感じているなら、そこにはすでに経営を良くする力があります。
もし、これからの経営を一緒に見つめ直したい、社内の議論を整理したい、自分たちの強みを言語化し戦略に落とし込みたい、そんな想いがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
業種や規模に関係なく、私は「今を乗り越え、これからをつくっていく地方の中小企業」の皆さんと伴走したいと考えています。
一緒に、次の時代に選ばれ続ける企業づくりを始めましょう。
値上げの先にあるものを共に考え、前に進みたい
物価高騰と人件費増と人手不足など、経営を取り巻く環境が厳しい中でも利益を出している企業や店舗の経営者は、値上げの先にあるものを見据えています。
「利益を確保するもの=値上げ」にとどまるのではなく、
・経営者も含めた従業員全体の収入を増やしたい
・地域の中で自分たちの存在が必要とされ、これからも続くようにしたい
・会社で働いてくれる人たちやその家族に、仕事に対する誇りを持てるようにしたい
・まだまだ新しいことにチャレンジして、自分たちの会社の可能性を高めたい
・次の代を見据え、強い経営基盤を作りたい
これら将来像を社内で共有し、そのための利益を確保するきっかけとして「値上げ」を実施し、利益を高めることに成功し、中には業界内でもモデルとなるような高収益企業を生み出しているケースも生まれています。
もちろん「値上げ」や「価格の見直し」、今までの考えからの脱却に対する不安は大きいでしょう。これらをサポートし、経営者と共に“利益を出せる会社づくり”をするためにミタス・パートナーズは存在しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
=PR=