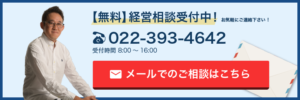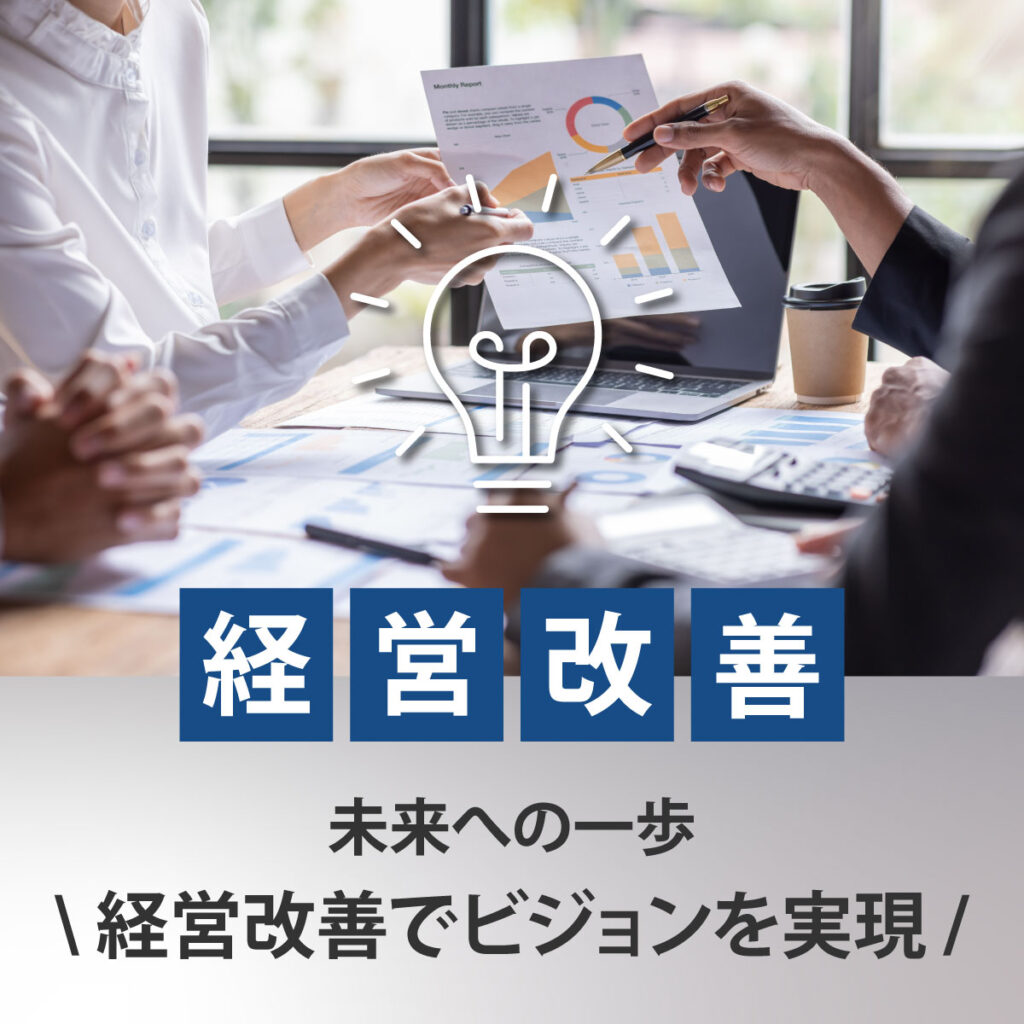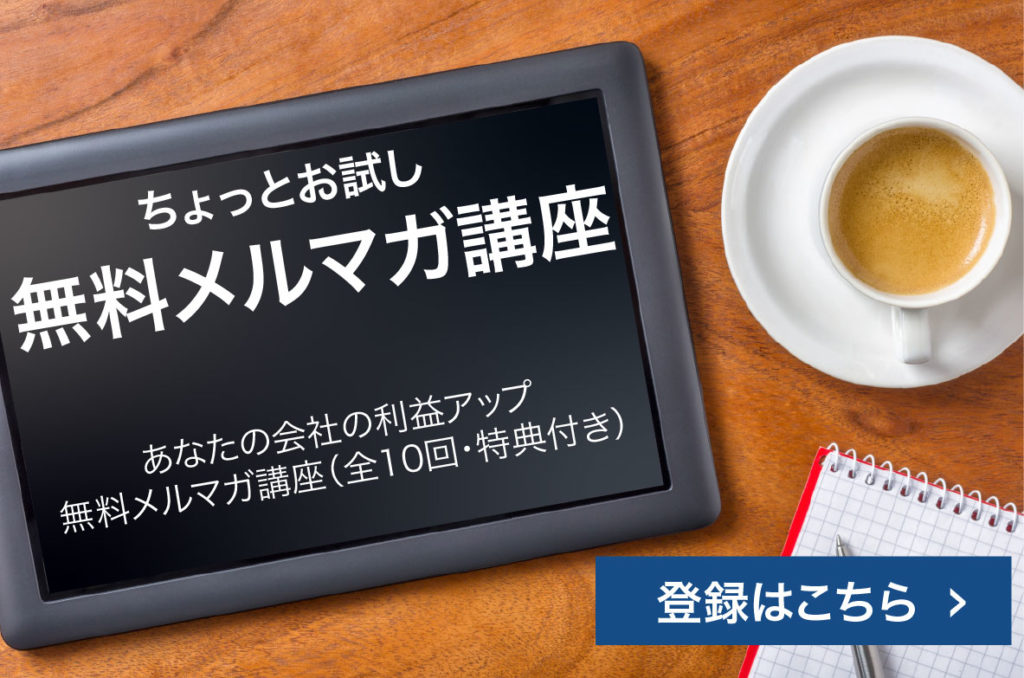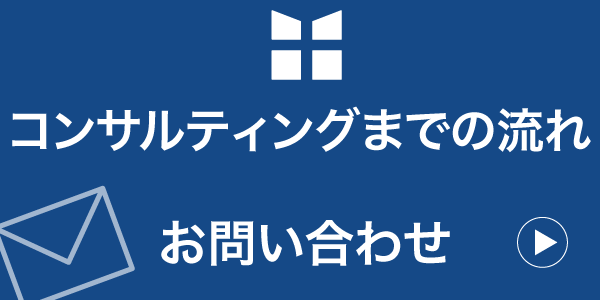中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント 本田信輔です。
今回のテーマは中小企業の菓子企業や食品製造小売業、飲食店における
「これからの時代を生き残っていくための原価率設定について」です。
経営相談の現場でよくある質問にこんなものがあります。
「うちの会社の原価率は正しいのか? 他社と比較してどうか?」
「他社では原価率をどうしているのか?」
この記事を読んでくださる方も、きっと
「同業他社と比較して高いのか?低いのか?」
「原材料やコストが上昇している中で、利益を上げている会社は原価率をどう設定しているのか?」
と気になったことがあるかと思います。
実は、相談に来られる会社と比べて、利益を上げている会社の原価率は“5〜10%も低い”
私たちがサポートしているクライアントさんの多くは、相談をされてきた経営者さんの会社や業界平均と比較して、5%〜10%近く原価率は低いですよ。というのが答えになるのですが。
「え?同じ業種でそんなに差がある?」と思われる方も多いのですが、事実です。
ではなぜ、これほどに原価率が大きく違うのか。
ポイントは「値づけの発想」にあります。
今回は、利益を出している会社の原価率に対する考え方についてお伝えします。
ご自身の会社にあてはめながらお読みください。
目次
1.お客様目線で値づけするから、原価率が下がる。
まず、確認したいのは、
お客様は商品の原価率をわかっているか?という点です。
たとえ同業でない限りほとんどわからないはずです。同業ですら、他社の原価率を知りたいということは同業でも正確に判断することは難しいですよね。
お客様は「原価率は○%だから、原価がかかっているから」ではなく、「この商品やサービスの価値に対し、だいたいこれくらいの値段だと妥当」と考え、買うか買わないかを決めています。
その場合、ポイントになるのは価値に対して「だいたいこれくらいの値段」というところです。
例えばー
お客様が“この大福は一個100円くらいが妥当ね”と判断した場合、
だいたいは80円〜120円の間で価格は収まります。
これがお客様の価格に対する視点です。
逆に言えば、80円〜120円の値づけであれば、お客様は納得して商品を購入してくれるということです。
もしも原材料に30円かかっているとすれば、原価率は以下のようになります。
80円と値づけする → 原価率37.5%
100円と値づけする → 原価率30.0%
120円と値づけする → 原価率25.0%
同じ商品でも、値づけ次第で原価率が10%以上違います。
私どものクライアントが原価率を低く設定できているのは、「単に高く売っている」からではなく、お客様の目線で価格設定をしているからです。
さらに言えば他社と比較して原価率に余裕のある状態だから、昨今の原価上昇等にも耐えやすい経営体質になっていることも事実です。
2.「原価率ありき」旧態の値づけ発想から脱却しよう
値づけをする時、原価率は○%と決めている会社は少なくありません。
「昔から、原価率は○%でと教えられてきた」
「業界では、それが常識だと聞いてきた」
と言われる方もいらっしゃいます。
先に原価率を固定し、かかった原価から値づけをする方法です。
景気の良い時代、原材料やコスト・人件費があまり変動しない時代であれば、これで経営が成り立ってきたということも事実だと思います。
ですが、原価率を決めて値づけする方法はあくまでも“会社・お店側の都合”です。
これからは原価率を固定して決める値づけは、商品やサービスの最低価格を決める一つの指標として位置付けましょう。
そこに“お客様の視点による値づけ”という発想を重ねていくことが、原価率を抑え、利益率を高める大一歩になります。
まとめ
これからの時代、特に中小企業は
「原価率をどう設定するか」の前に、
「どんな価値を、いくらで売るか」を経営の軸にしていくことが肝要です。
例えば。【年間売上5000万円の主力商品の粗利率が5%違ったら】
年間で得られる利益は+250万円も違う。純粋な粗利益で、です。
特に値づけは、経営者が行うこと。
経営者の意思表示そのもの。それは会社の利益を大きく左右する結果になります。
お客様が納得する価値を基準に値づけを見直す。
さらに、あなたの会社に合わせた原価率設定や価格設定などを具体化していく。
自社の原価率設定がどうなっているか、作り手側の目線だけになっていないか。
まずは、ここから始めていきましょう。
「原価率設計はできた。でもそこからどうやって価格に反映させたら良い?」とお悩みの方へ。あなたの設計をプロが診断する無料オンライン相談を活用ください
弊社ではこれまで開業してから約300件のご相談を承り、そのうち約160件の企業・事業者さんのご支援を行いました。
ご自身が設計した結果を、一度プロの視点で診断してみませんか?「この価格で客離れをしないか?」「あといくら、上乗せできるか?」を具体的な根拠とともにお伝えします。
【一日一社限定・無料オンライン診断】無料オンライン相談では、ご要望がない限り営業活動を一切行いません。まずは下記フォームよりお申し込みください。