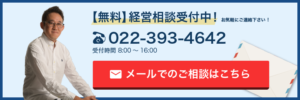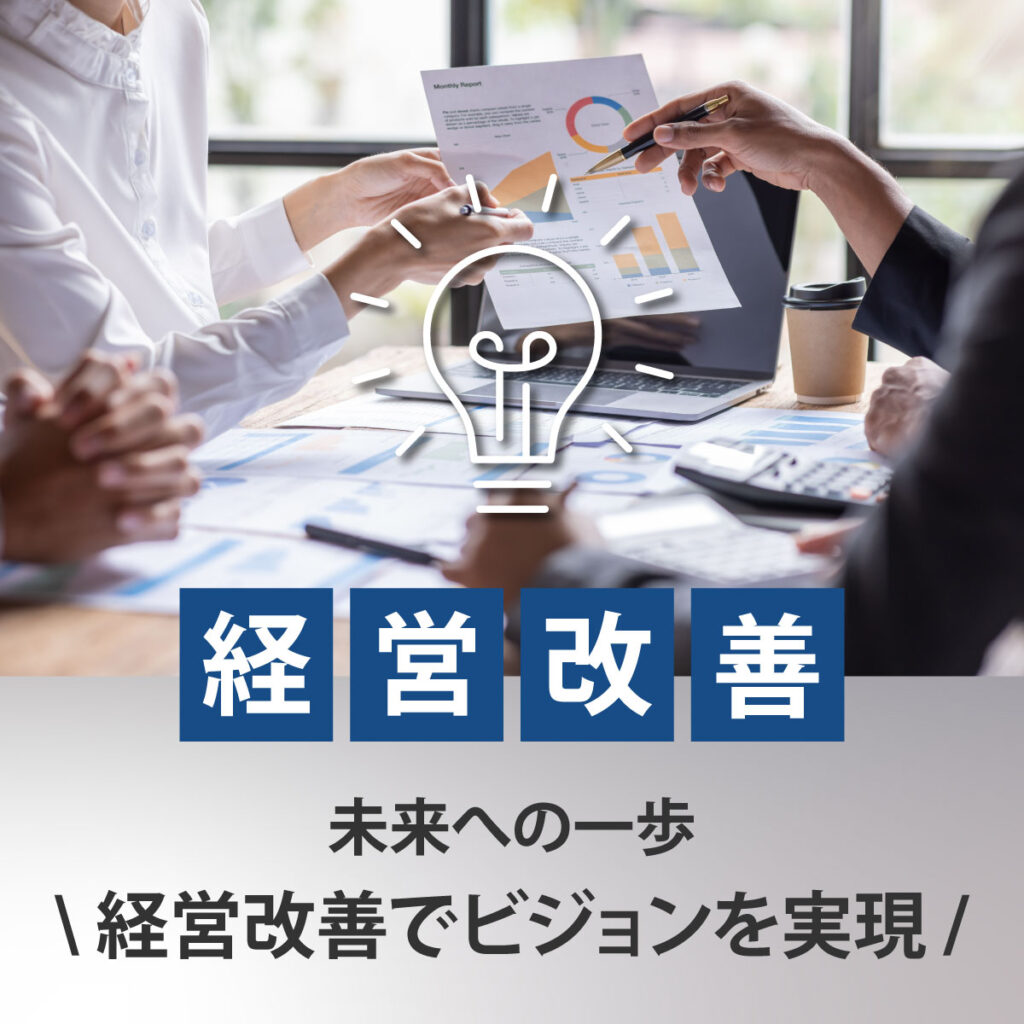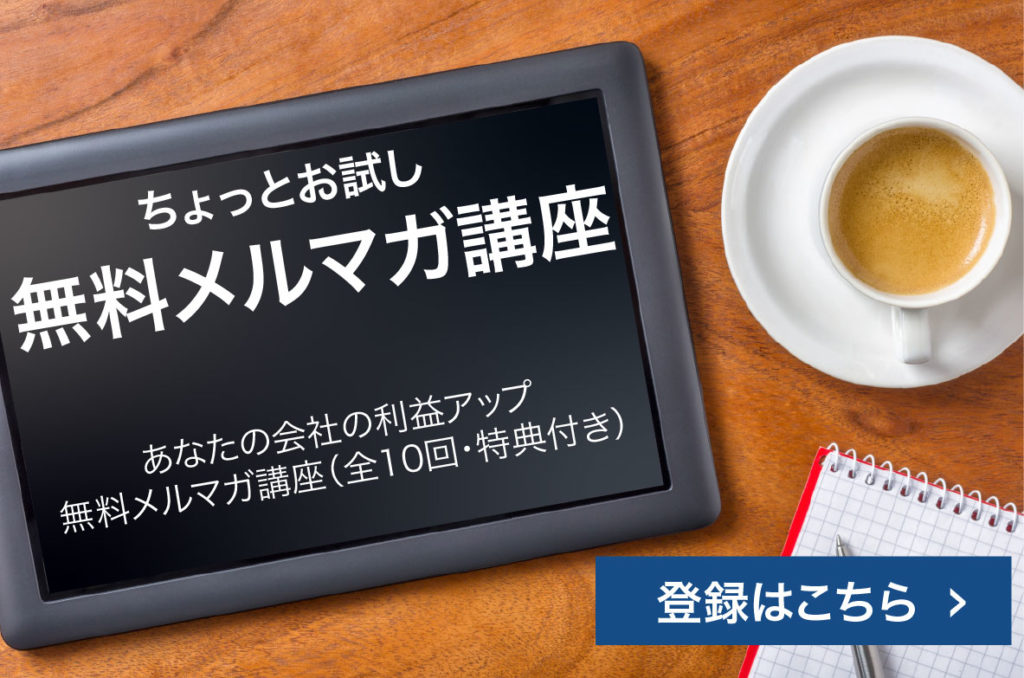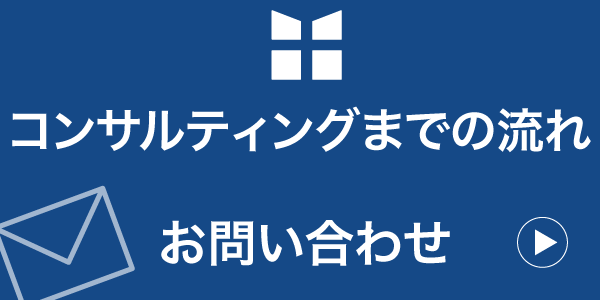中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント本田信輔です。
今回のテーマは業界の常識ともいえる「焼き菓子は儲かる」。これまでに洋菓子店を含め、数百社以上の企業を支援してきた経営コンサルタントとして、焼き菓子が儲かる理由とその方法について再考していきます。
もともと利益を出しづらいと言われる洋菓子店。その中で利益を出すための救世主的な存在として“常識的”に認知されているのが焼き菓子。
原価率が低く、日持ちがして、効率的に製造できる。日持ちのしない洋生やプチガトーとは違いギフトや贈答としても利用されやすい。とかクッキーがたくさん売れる洋菓子店は儲かっているとも言われています。
とはいえ本当に焼き菓子は儲かるか?経営コンサルタントとして洋菓子店の経営や利益を見まくってきた視点で説明しています。
目次
1.焼き菓子は確かに儲かる要素を持っている
原価率が高い、人手がかかる、日持ちがしない、と儲からない要素満載の洋生・プチガトーと比較して、原価率が低く、効率的に製造できて、日持ちがする焼き菓子は確かに儲かる要素を持っています。
焼き菓子がたくさん売れれば利益が上がり、儲かるということは確かに一理あります。業界の常識は正しかったといえます。
ですがこれを100%鵜呑みにはできないのが実際のところ。経営コンサルタントとして様々な洋菓子店をみていると焼き菓子が儲かるようになっているかといえば、そうはなっていないケースが多くあるからです。
焼き菓子自体は確かに儲かる要素を持っているが、売り方や商品構成を間違うと洋生・プリガトー以上に利益を圧迫するケースも多くありました。
そんな事例のパターンを次項よりまとめています。
2.焼き菓子が儲からない典型事例
(1)焼き菓子の種類が多すぎる
焼き菓子部門の売上が大きい洋菓子店でも、儲からない典型パターンは種類が多すぎる場合。何種類もあるクッキー、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、パウンドケーキ、パイ、エンガディナー、タルトなどなど。品種の種類もそうですが、プレーンとチョコレート、フルーツ別など味の違いも入れれば数十種類の焼き菓子を展開している洋菓子店は少なくありません。
パティシエや職人さんの言い分を聞くと。。。
・材料は共通するものが多いから
・材料のロスを軽減するため
・日持ちがするから
・売り場の中を華やかにしたい
・自分の技術を見せたい 等々
理由をたくさん聞くのですが、儲けるという点から見ればマイナス要素がたくさん。
・共通する原材料はあるが、結局のところ種類を多く作る分、仕込みなどの時間がかかる(ロスする原材料の金額よりも、人件費の方がかかっている)
・販売する商品が分散されるため、個々の商品は少量多品種生産となり、製造現場全体の効率は下がる(1品を大量に作る方が効率的)
・明確な主力商品が生まれづらく、広域商圏からの集客や自店の顔となる商品づくりができない→ブランド力が上がらない(お客さんの持つイメージが分散する)
・ギフトや贈答の中心が多品種の詰め合わせとなり、繁忙期にかけて製造現場だけではなく販売現場の効率まで下げてしまう。
商品一つ一つを見れば原価率も低いし製造効率も良いのですが、製造現場全体、会社全体で見れば利益貢献は弱くなってしまっているのが現状。儲けることができる焼き菓子の良さが間違った商品構成によって失われていることになります。
もしも焼き菓子の売上が大きいのに利益は思ったほど出ないを感じているのであれば、まず焼き菓子の商品構成を疑ってみること。種類を減らし焼き菓子の売上が多少落ちても利益が上がる事例が多く存在します。
A:1つの焼き菓子で1000万の売上を作る。
B:30種類の焼き菓子で1000万の売上を作る。
どちらが売上の質が良く、利益を出せるかは誰でもわかりますね。
(2)商品の利益を決める3つの要素
原価率が低いと言われる焼き菓子ですが、商品の利益を決める3つの要素で考えてみるとどうでしょう。
=商品の利益を決める3つの要素=
・原材料
・製造にかかる人件費(製造にかかる時間)
・値づけ
この3つです。
洋菓子店の決算書を拝見すると、よくあるのが人件費を製造・販売で一括りの項目にしているケース。店舗全体や会社全体で見ればそれで良いのですが、実際に製造にかかる人件費はどの程度になっているでしょうか。
空いている時間で作らせているとか、うちは機械化できているから効率が良いと言われるオーナーもいらっしゃいますが、一つの機会を動かすためには準備と後片付けが必要です。
一つの商品を作り続けることができれば準備は1回、後片付けも1回で済みます。
ですが30種類の商品を作ることになれば準備は30回、後片付けが30回必要になる。
1日1種類の商品を作り続けるのか、午前と午後で2種類の商品を作るのか。仮に準備・片付けの時間にかかる時間が2人で30分ずつだとすると、無駄に1回分(準備に30分×2人、片付けに30分×2人 合計2時間の無駄な労働時間。時給900円だとすれば1800円分)増えていることも考えていかなければ本当に儲かる商品かどうかはわかりません。
商品数が多いことで人件費の無駄が出てきます。一つ一つは微々たるものでも年間で見れば大きな金額になります。原価率は低いが、人件費を加味してすると製造効率は悪いということになります。(1日2時間、年間で100日だとすると1800円×100日=18万円の無駄なコストが出ている)
=数字で見ると以下のようなイメージです=
焼き菓子の種類が多いA店:原価率15%、人件費率25%
焼き菓子の種類が少ないB店:原価率15%、人件費率20%
同じ原価率の低い焼き菓子ですが、どちらのお店が利益を出せるかわかりますね。
もう一つ、合わせて考えておきたい要素は値づけ。
原価率だけをみて値づけをしていると、上に記載した製造にかかる人件費ということが抜けてしまいます。原価率は低いが、人件費はかかっている。かかっている人件費分が値づけ段階で加味されていなければ儲かる商品にはならず、人件費比率は上がり、利益も出ないし、給与もあげられないことにつながります。
情緒的なことを言えば、同じ原材料を使っているのに、値づけを間違うということは自分たちの技術や従業員の頑張りは値段に入れていないということ。
これでは、仕事に対するプライドも上がらないし、利益も給与も上がりません。従業員が辞めていく原因にもなってしまいます。
逆にいうと、儲からないと言われる洋生・プチガトーでも値づけを間違わなければ利益は出るということですし、実際に値づけをちゃんと考えている洋菓子店やクライアント先では洋生・プチガトー中心の売上でも高利益を出しています。
菓子業界だけではなく、中小企業や個人経営のオーナー店舗では、特に値づけについて学んでいないことが多くあります。なんとなくの値づけ、昔からの古い感覚や慣習(原価の3倍として値づけする等)によって値づけしていることが業界全体の課題だとも感じます。
利益を出せる値付けの仕方については現在配信中の無料メルマガでも取り扱っていますので、興味のある方は購読してみてください。
3.儲かる焼き菓子8ケ条
実際に、焼き菓子の儲かる特性を生かして高利益を出している洋菓子店さんや、改善によって高利益化している洋菓子店・菓子店事例が生まれています。
その特徴をあげると、以下の8つです。
1.焼き菓子の種類を絞り込んで、単品の売上構成比が15%を超える主力商品を育成している。焼き菓子を単品として考えるのではなく、商品構成全体から見ている。 2.詰め合わせのためだけにある商品は作らない。単品でギフトや箱入りが売れる焼き菓子だけしか作らない。 3.主力商品とかぶる商品を極力販売しない(店内で競合する商品を作らない・売らない。お客さんにしてみればどっちでも良いと判断される商品) 4.主力商品を定期的にブラッシュアップして、商品寿命を長くしている。技術力の表現を種類で示すのではなく、深堀りという形で表現するため他社との差別化ができている。 5.主力商品に特化して、製造効率を上げる投資をしている。そのために投資効果が高い。 6.一つの商品をより多く作ることになるため、製造現場のスピードが上がっている。 7.値づけを真剣に考えている。原材料だけではなく、製造にかかる人件費も考慮している 8.主力商品を育てるための販売戦略、イベント・催事など定期的に行なっているため、会社・店舗の全スタッフが明確な主力商品の共通認識「うちのお店の主力はコレ!」を持っている。そのため、販売におけるセールストークも強化できている。ホームページなどもわかりやすい
儲かる要素を持った焼き菓子の特性を最大限に生かす経営ができているということですし、この特徴は焼き菓子だけでなく、洋生・プチガトーの主力商品を持つ洋菓子店でも同じことが言えます。
4.儲かるが、経営者・オーナー次第
結論として言えるのは「焼き菓子は儲かる要素を持っているが、儲けられるかどうかは経営者・オーナーの裁量にかかっている」ということ。
焼き菓子で儲けられるかどうかは、商品云々ではなく経営者・オーナーの判断です。ケーキ屋さん・洋菓子店をはじめ、中小菓子店や中小企業の多くは利益が出ない原因のほぼ全てを経営者・オーナーが決めています。
=儲ける、利益を出せる焼き菓子づくりのために=
・どんな種類の商品を作り、売るのか
・どの商品を主力商品に据えていくのか
・どのような値づけをするのか
何度も繰り返しますが、これらは全て現場が考えたとしても最終決定権・判断は経営者・オーナーにあります。例えばその典型は値づけ。現場が決めた値段をオーナーは変更することができますが、オーナーがこれと決めた値段を、現場が勝手に変更することはできません。
利益が出ないのは経営者やオーナーの考え・判断が、利益につながらない方向に向かっているためです。逆に言えば、現場が変わらなくても経営者やオーナーの考えが変われば、もともと売上があるだけに大きな利益化を、短期間で実現することができます。
主力商品の育て方については商品構成の見直しのほかにも、販売戦略や主力商品育成などもご相談いただければ、効果抜群の日本一会議企画をはじめ、あなたのお店にとって効果のある具体策をお伝えできます。
5.改善に踏み切れない時の対処
オーナーや経営者が儲かる焼き菓子作りに向けて改善しようとしたら。やはり一番の不安は種類を減らすことによって今までの売上・客数、そして培ってきた評判が落ちることではないでしょうか。値づけを変える不安や、自分の持つお菓子づくりの技術力を否定されているような気がすると言われるオーナーパティシエの方もいらっしゃいます。
そんなオーナーや経営者にお伝えしているのは、
①地域からの評価に自信を持つ
この地域で長年経営し、これだけのお客さんが来てくれている。それは価格の安さが魅力なのか?本当に商品の種類が魅力なのか? 今のお客さんは安さや種類の多さだけでは選択しない。今までの取り組み、商品力の高さがちゃんと評価され売上や客数につながっているということです。
②売上構成比を把握する
実際に売上構成比を把握してみる。焼き菓子部門全体ではなく、個別商品で売上構成比。集計していない場合は、年に何回製造している日があるか?一回にどれくらい作っているか?そこを考えてみる。
③ブランド力の棄損を考慮する
売れない商品や支持されていない商品を店舗に並べていることが、自分たちの技術力やブランド力を棄損していると考える。もしも支持されていない商品が詰め合わせギフトに入って、どこかに贈られている(送られている)としたら。自店の他を知らない人はどんな判断をするだろうかと想像してみる。
④プライドを持って値付けする
値づけは自分たちの技術力や働きを表現する指標。安ければ自分たちの実力も軽く見られるし、従業員の仕事に対するプライドも給与もあげられない。(安い商品を売って自慢しているのは経営者か原価コントロールをしている管理職ぐらいです。従業員の仕事に対するプライドは上がりません)
⑤新たなビジネスモデルを構築
修行という働き方が減っている今、低賃金・超労働時間で回す昔の洋菓子店ビジネスモデルは崩壊していることを認識する。
⑥薄利多売に疑問を
そもそも数を多く売って利益を稼ぐ薄利多売の商いは継続できるか?を考える。
これからの日本を見れば人口減が予測されています。2019年は日本全体で約50万人減っています。毎年県庁所在地クラスの市の人口がなくなる予測が出ています。2年経てば100万人都市である仙台市や新潟市クラスの行政区が1つなくなるほど人口減が進んでいます。その中で今後客数や販売個数を伸ばすことはできるのか?人の胃袋が大きくなって、今の2倍お菓子を食べることができるのか?合併・統合を繰り返す超大型企業と価格競争で勝てるのか?地方であれば、人口減はさらに深刻です。
焼き菓子ということ一つも経営の視点で見ていくことが大事になっていますし、儲け利益を出しやすい要素を持つからこそ、戦略的な取り組みをしていくことが洋菓子店経営での重要度を高めています。
オーナーや経営者の考えが変われば、元々のポテンシャルがあるだけに大きな利益化ができます。
利益化に向けて、不安の解消、具体的な取り組みのアドバイスを行なっております。あなたのお店の強みを生かし、将来をどのようにするかを共に考えていきましょう。一方的に提案することはありません。お互いに理解を共有して前に進みます。利益を出すことは、より良い未来への入り口だと考えます。利益があるからこそ、もっとやりたい未来を描き、理想の実現に向けてチャレンジできる。
必ず良い未来が描けます。
お気軽にご相談ください
弊社ではこれまで開業してから約300件のご相談を承り、そのうち約160件の企業・事業者さんのご支援を行いました。もしお困りのことがございましたら、お力になれる点があるかと思いますので、お気軽にご連絡ください。