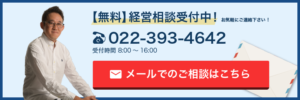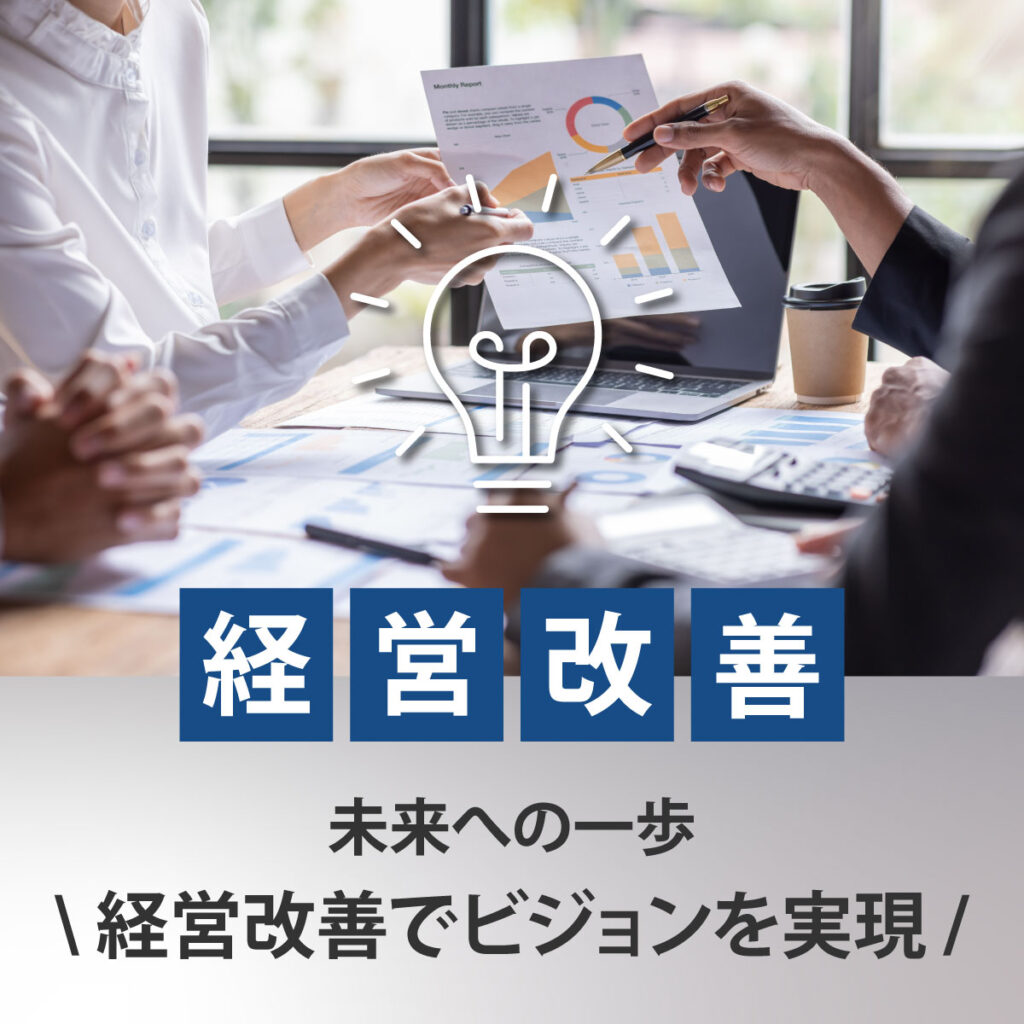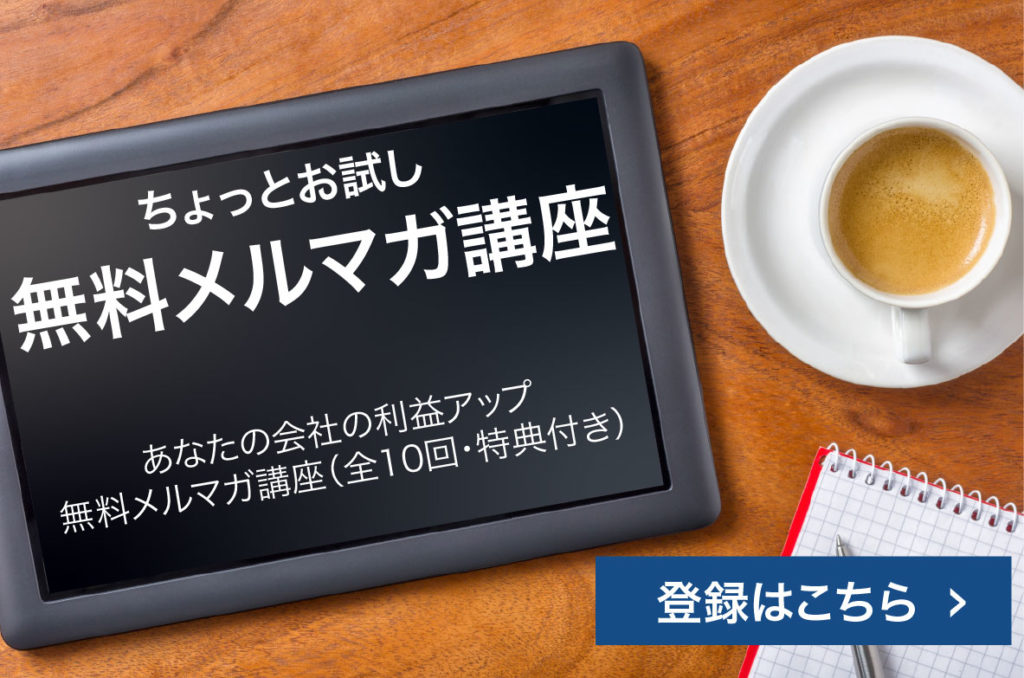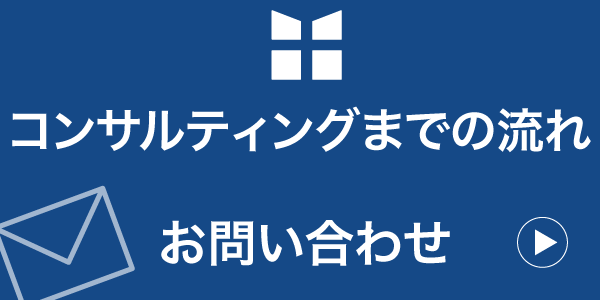中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント 本田信輔です。
今回のテーマは中小企業の菓子企業や食品製造小売業、飲食店における「広告宣伝から戦略的広報への転換」です。
ここ数年、よく質問されることに、「チラシやDMの反応率が落ちたから、SNSを始めたんだけど、全然効果が出ない」があります。
相談を受けて、運用しているSNSの内容を拝見していると、「うーん、これは使い方が違うな、、、」と感じるケースがしばしば。
原因を結論から言うと、「SNSでどれだけ広告宣伝を行なっても反応は生まれにくい。なぜならSNSを利用する人たちが求めているのは“広告”ではなく“広報”だから」です。
そして、今回なぜ“中小企業の戦略的広報”についてお伝えするかというと、
地方の中小企業の利益アップにおいて重要な取り組みになりつつあるからということが一点。
もう一点は、成長している中小企業の多くが広告宣伝から広報へのウェイトを高め、戦略化や取組み強化を進めていて、売上・集客においても重要度は増していることがあるからです。
広告宣伝では反応しづらくなった今の消費者が、ブランドや商品・サービスを選択する新たな基準へのアプローチとして、「価格よりも価値を伝えてる」広報は重要な要素を占め始めました。
今まで「広報といえばなんとなく大企業がやるもの」と思う方も多く、中小企業であまり意識されてきませんでしたが、現実は“ブランドへの温度感”や“人の顔が見える”など大手企業ができない強みを“コストを抑えて発信できる”広報は、中小企業にとって非常に有効な手法として着目されています。
・広告が溢れ、過剰になった時代に、消費者が“売り込み”よりも“信頼できる情報”を重視するようになったこと。
・SNSやwebメデイアの発展・普及で、コストを抑えて中小企業でも自分たちの声を直接届けられる環境が整ったこと。
・“人の顔が見えるブランドへの”や“共感できる物語”が購入動機の決め手になってきたこと
私たちが大事にする“自分たちの価値を高め、利益を獲得していく”を進めていく上でも、消費者の買い物に対する選択基準の変化にアプローチする「中小企業の広報戦略」を真剣に考え、これからの成長エンジンとして考えたら。
次項からは、中小企業の広報について、そのポイントをお伝えしていきます。
1.中小企業にとっての広報とは。広告宣伝との違いを認識しよう
広報?と聞くと、広告宣伝とどう違うのか?と感じる方も多いと思います。
冒頭でお伝えしたとおり
「広報は大企業や行政など、大きな組織がやるもの」
「コストがかかりそう」
と思われる方は非常に多いです。
確かに似ているように思われがちですが、実は、その目的と取り組みは全く異なります。
広告宣伝はチラシやDM、テレビCM等に代表されるように、自社が宣伝費用をかけて、直接的に商品やサービスを訴求する取り組み。短期的な売上や集客の獲得すること。つまり“費用を使って商品やサービスを売り込む活動”です。
一方、広報は大きな費用がかからない代わりに、テレビや新聞へのプレスリリース、SNSでの情報発信、地域イベントへの参加等などで、企業やブランドの信頼を積み重ねる取り組み。直接的に商品やサービスを訴求するのではなく、自社の戦略や将来像を前提に“強み”や“想い・背景”“どんな価値をお届けしたいか”を伝え、知ってもらう取り組み。
広告よりも「信頼」や「共感」、「ブランドや商品の物語」を通じて、選ばれる企業やブランドになることを目的としています。つまり、広報とは“売り込むのではなく、信頼され選ばれる会社やお店になる”ための活動で、その積み重ねが結果として、売上や集客、利益を持続的に高めていきます。
◾️SNS活用でつまずく企業の共通点
「SNSを始めたのに反応がない? 効果が実感できない!」
と相談に来られる方の会社SNSを拝見すると、その投稿内容のほとんどが広告。
・新商品や季節商品の紹介
・イベントや催事の案内
・値引きやお得キャンペーン情報
中にはチラシやDMと同じ内容を投稿している場合も少なくありません。
SNSはそもそもチラシやDMの代わりではありません。今の消費者やSNS利用者の求めているものは“人や企業の姿勢・価値観・信頼できるストーリー”で、企業やお店の「売り込み情報」ではないからです。
本当に知りたいのは、
・なぜ、この商品を作ったのか。作ろうと思ったのか。
・自分たちが一番大切にしている思いや技。
・地域や未来とのつながり
・お客様への感謝や日々の関わり
といった“中小企業だからこそできる発信”で信頼や共感を生む内容。
見方を変えれば。地域で配布するチラシに記載する内容や、お客様の前で手作り菓子を実演して売る取り組みも“広報”として捉えて、組み立て直せば、十分に効果を発揮するケースも多いです。
技術的な問題ではなく、「何を伝える」という中身がズレてしまっていることが、成果につながらない原因と気づいていない。それこそがSNS活用でつまづく企業の共通点です。
2.地方の中小企業が取り組む広報3つのステージ
それでも広報と聞くと、“難しい!”と高いハードルを感じる方もいらっしゃいますので、
できるだけシンプルに3つのステップでお伝えします。
ただし!広報で重要なのは、企業戦略や未来構想との連動です。
現場レベルの対策ではありません、ちゃんと経営という視点が必要な点を踏まえておいてください。
中小企業にとっての広報は、
“自分たちが、どんな想いで、どんな価値をお届けしたいか”を伝え、知ってもらう活動です。
広告よりも「物語」を伝え、「共感」や「信頼」を軸に据えて考えます。
【3つのステージで考える広報】
①知ってもらう(認知)ステージ
SNSやプレスリリースなど、広報で情報発信する媒体は、ある意味 エリアや今までの客層を超えて情報を届けることができます。
そうなると、まず大事になるのが “自分たちは何ものなのか” “どんな会社やお店なのか” を知ってもらうことです。
これもよくあることなのですが、地域密着で長く商売をしてきた会社やお店の認知度を誤解する経営者がいらっしゃいます。
昔からここで店を構え、商売をしてきたのだから、
・地域の人はみんなうちを知っている。
・地域の人はうちの一番商品を知っている
・地域の人はうちの想いや技術力の高さを知っている
まずは、この認識から変えていきましょう。
SNSやプレスリリースの特徴は、距離や客層を超えて情報発信できること。
言い方を変えれば、自分たちの会社やお店、商品を知らない人たちが見てくれるということです。そのために、まずは知ってもらう(認知してもらう)ステージづくりを行います。
◾️SNSの整備
Instagram、YouTube、TikTokなど。写真のトーンを統一する。菓子店であれば「お菓子+職人・手作り+季節」を1枚で伝える画像や動画を考えます。週に2回程度から始めて、お店や工場の日常を発信していきます。
◾️地元メディアとの関係づくり
地方紙やテレビ局・ラジオ局・ケーブルTVとの関係づくり。定期的に「季節の和菓子便り」「地域と連携したイベント」などのプレスリリースを定期的に配信します。特に、地域や未来とつながる取り組みについては、取り上げられやすくなります。今ある商品や企画でも、そういった背景を持つものは積極的に発信していくことがおすすめです。長い目で見れば、上記のようなコンセプトを持つ商品開発やイベント企画を考えていくことも必要になってきます。
◾️ Googleマップ・口コミ対策
これはよく、ミタス・パートナーズHPを管理運営してくれて、クライアントさんにもご紹介するH Pサイトを制作してくれる方からアドバイスをもらう内容です。Googleマップのアカウント管理や、基本情報の入力など、スマホ検索が増えた今、基本的な情報(例えば、お店の休み情報や営業時間などを更新していない会社は信頼されない!)を更新することは信頼への第一歩になっています。お店であれば、ちゃんとしたお店がわかりやすい画像の登録をしたりします。来店型であれば「口コミ=広報」なので、返信にも“人間味”が伝わる内容・言葉を意識します。
②共感してもらうステージ(好きになってもらう)
次のステージは、実際に共感してもらうステージです。
広報の内容は、ここがメインになってきます。
自分たちの想いは何か、強みは何か、どんな価値を提供していくのか。
自分の会社を見つめ直し、しっかりと戦略的な視点を入れて考えていくことが大事です。
◾️ブランドストーリーの発信
「創業」、「大事にしていることや技術」、「季節の風景」、「自分たちが持つ素材や根ざす地域のこと」「商品に込めた想いや背景」といった“物語”を写真+短い文章で表現します。SNSに投稿する内容や、店内POPや販促物、Webサイトとの一貫性を求められます。
◾️地域やお客様との接点を発信
限定販売日、お菓子教室や工場祭などは、まさに情報発信できる大きなチャンス。リアルな現場をお伝えします。実際にリアルな体験ができる機会は、マスメディアやブロガー・インスタグラマーと呼ばれるような人たちとの接点になり、情報発信をしてもらえることも増えてきます。
◾️日常を動画で発信してみよう
手作りを大事にしている会社であれば、“手の動き”や“湯気”“音・声”を画像や短い動画で表現します。工場では手作りしているのに、それがお店やお客様との現場で発信されていないケースは少なくありません。ものすごくもったいないです。他社や大手企業との差別化できる強みであるにも関わらず、それが工場内に止まり、情報としてお客様に伝わっていない。そういったことを見直していくことも広報を進めていく重要な要素です。特に手の動きは動画がおすすめです。短い動画で構わない。職人の顔が映らなくてもしょうがない。まずは手の部分だけでも発信していくことから始めていきます。
=ある地方のお餅屋で、実際に取り組んでもらった事例=
そのお餅屋さんの強みである、毎日、「薪を使い、竈で炊いた餅米」を使うに焦点を当て、毎日 ”竈に焚べた薪火”を撮影して、Instagramに写真投稿してもらったケースがあります。撮影するアングルは毎日同じで構わない。そこに、その日の天気や薪の状態で、少し調整する内容
― 今日は寒い朝でした。前日の雨もあり少し薪は湿り気味。いつもより少し長めに餅米を蒸しました ー
(といった感じ)を文章で記載してくださいと提案し、継続してもらい、それが認知アップ→集客やお問い合わせ増加につながっています。
③信頼してもらうステージ(応援してもらう、他者に紹介してもらう)
3つ目のステージは信頼してもらう。地域の中で支持される存在になる。誰かに伝えたいと思ってもらえるようになる段階です。
◾️地域とのつながりを広報化する
地域生産者や地元企業、アーティストとのコラボ商品や企画。地域全体に波及できる企画を実施し、それらを広報していきます。SNS投稿に加え、プレスリリースなどもセットで考えます。
◾️お客様とのより深い関係を広報化する
お客様のエピソード、○○さんからの手紙、お客様の声を広報していきます。自社の声ではなく、お客様や地域からの声を発信していくことで、信頼度を高めていきます。
◾️パートナーシップの広報化
将来的には、百貨店催事・企業ギフト・地域団体、他企業との連携など、外部の信用を“広報”として発信していきます。
時間はかかるかもしれませんが、1〜2のステージを段階を踏まえて進めていくことが、結果として3つの目のステージにつながることが多いです。
3.中小企業が特に強い広報は何か
資源① 人間味や職人らしさ、家族
「ひとで選ばれるブランド」になる。想いを発信する。日常の風景や会話をキーワードになります。
資源② 地域・素材・季節
地域や生産者との深いつながり。強い素材を持ってる場合は想いや背景を。地域との繋がりであれば伝統文化や季節の風景などをキーワードにします。
資源③ 手作りや技術
機械にはできない“手の動き”、人によるサービス、手間をかけるなど。実際に商品を作っている手元などは、とても効果があります。動画・写真などが中心ですが、店舗やイベントなどの実演でも発信することも良いです。
資源④ 小規模の強み
中小企業としての小回りを発信します。OEM等の小ロット対応、商品の少量生産・少量限定、お客様への個別対応、オーダーメイドなどを強みにしていきます。
これらは大手企業との大きな差別化要素になり、自社の強みを軸として共感や信頼を得る重要なポイントになります。
おすすめは何でもかんでもやろうとするのではなく、自分たちがどこに注力化するかを決めること。最初から全部やろうと思ったら大変です。小さなことからで良いので、少しずつ発信を続けていくことを大事にしてください。
色々と広報資源の選択肢はありますが、どれを大事にして集中していくかを決めていくことが良いです。
4.まとめ
広報の目的は、
「自分たちの商品そのものではなく、“作る人・売る人の心を伝えていく”のが中小企業の広報」
商品よりも「人」、「想い」、「風景」に焦点を当てた広報が最終的なファン客づくりは、中小企業だからこそできる成長エンジンになり、持続的な売上・集客・利益に直結しています。
広告宣伝がお客様の心に届かなくなった時代。“信頼を共感で選ばれる。価格ではなく価値で選択される会社・お店”を目指して、あなたの会社の広報戦略を見直してみてくださいね。
【筆者プロフィール】
中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント
本田信輔(株式会社ミタス・パートナーズ代表)
地方の中小企業を中心に、「強みの再発見と価値化で利益を高める」「価格より価値で選ばれるブランドづくり」を支援。
=PR=