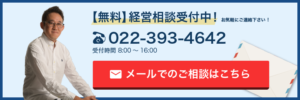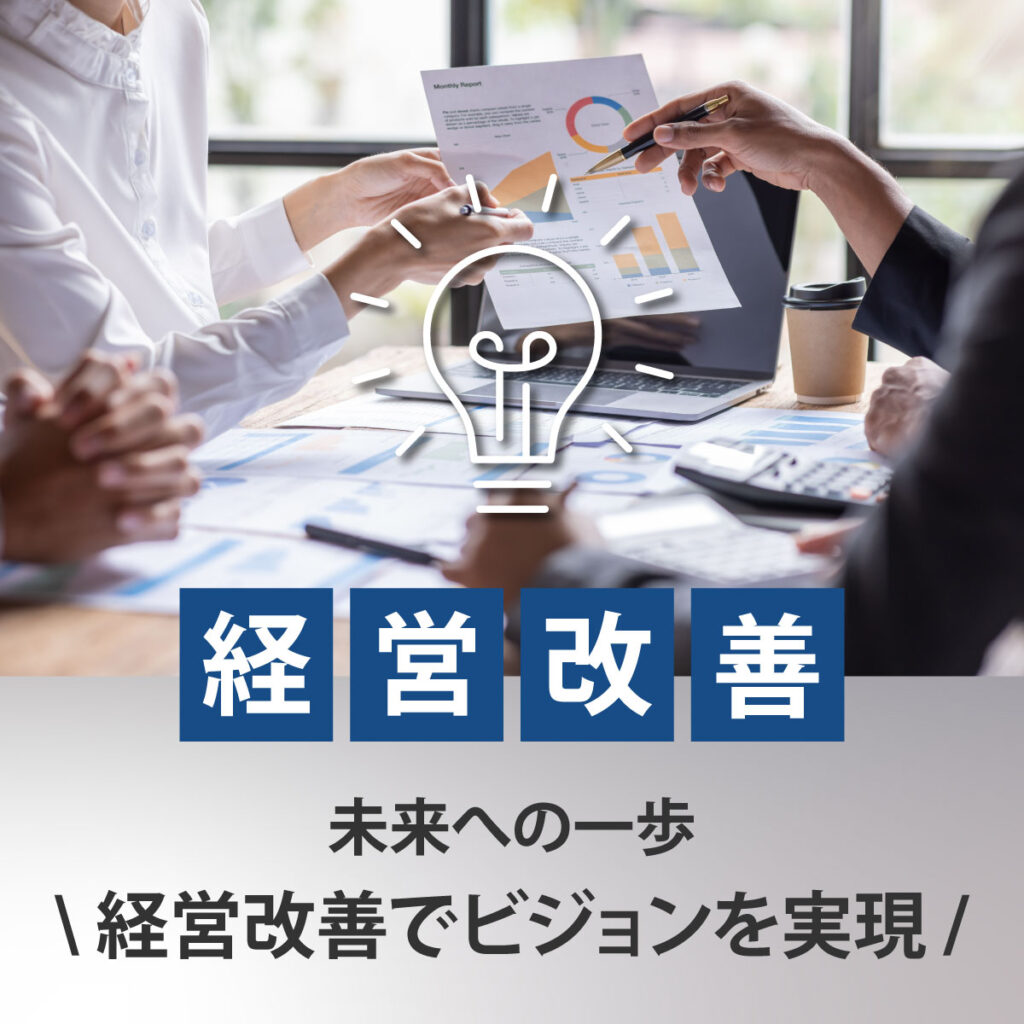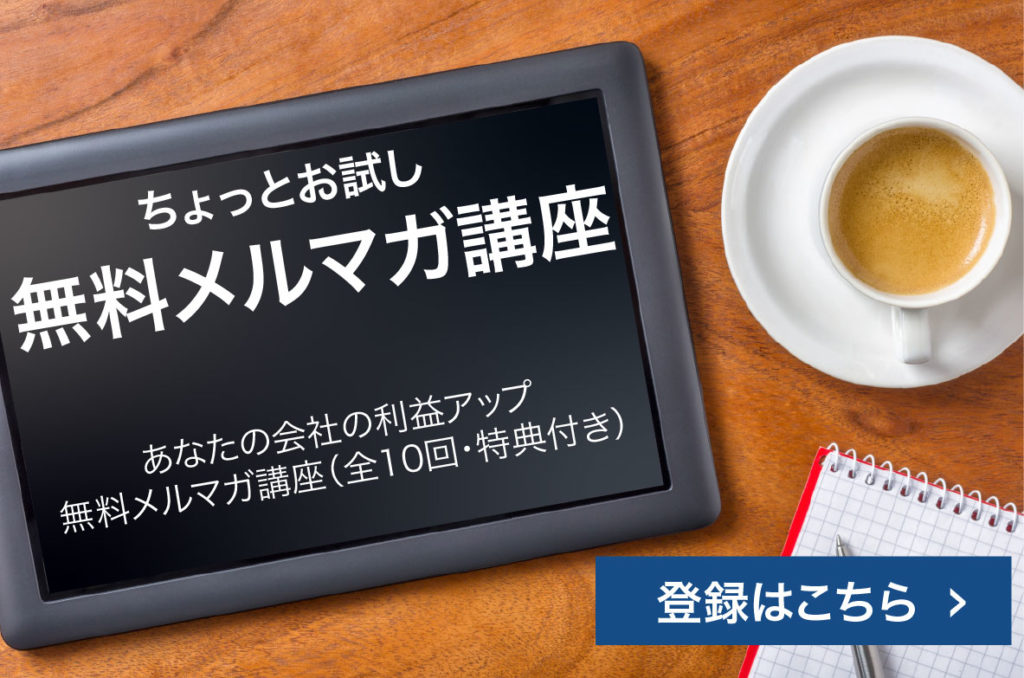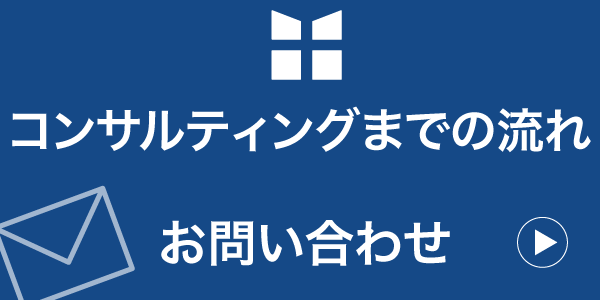今回のテーマは現地現物現人と理論の組み合わせについて。
実際に現地を見る。現物を見る。人を見る。
自分の目で確認し、空気を感じること。
海外ではFact finding!と言われているようです。
生産性向上が課題の中小企業にとっても大事。
改善スピードを上げるために、現場現物現人を意識する経営者は多くいらっしゃいます。
ですが現場主義だけに猛進しすぎた結果、理論をおろそかにし、気合いと根性論になることで、改善のスピードや成果が低下する場合も。
生産性を早く高めるために、本当に大事なのは理論と現場の組み合わせ。
一見違うように見えますが、両方を揃えて取り組むことが一番の近道です。
1.現地現物現人は大事。改善のスピードを上げるけど、何かが足りない。。。
生産性を高める場合でも、新しい店舗を作ったり、リニューアルしたりする場合でも、具体的な商品開発、販促企画を考える時でも、現地で現物を見ながら、打ち合わせするとスピードは早くなりますし、新しい画期的な発想も生まれやすくなります。
それは、なぜか。
理由は簡単です。
“感性と直感力が働くから”
良いと思ったことをすぐにカタチや企画にできるからです。
これは大きなメリット。
会社の中で、机を囲んでああだ、こうだ言っていてもなかなか出てこない。
成果をあげたり、新しいことにどんどん取り組める経営者は、
とにかく現地を見て、現物に触れ、そこにいる人と話をします。
世界的に有名な写真家の先生にも教えていただきました。
“机に座っていても、インスピレーションやアイデアは浮かばない”
“所詮は自分の頭の中にしかないことしか出ない”
“そんなアイデアは、焼き回しにすぎない”
だからこそ、
“外に出ることが大事。いろいろな感性に触れる。そこから新しいことは生まれる”
世界的に有名なアーティストでもそうです。
普通の人が感性を広げたり、直感力を高めるためには、外に出ることが大事ですね。
それが、改善スピードや素晴らしいアイデアを生み出すポイントになりますね。
一方で、短期間で生産性を高めるためには理論も大事。
それはなぜか?
2.理論とは改善の仮説や、現場を観る視点をつくるもの。
さぁ現場に行って改善しましょう!!!
と現場に行って一番困るのは、
“何を見たら良いか、どの視点で見たら良いかわからない”
まさにここにあります。
生産性を高める場合、
・製造ラインや人の動きに問題があるのか?
・商品自体に問題があるのか?
・売り方や営業方法なのか?
・それとも経営の仕方に問題があるのか?
・財務や経理?
・人づくり?
・指示や指揮系統?
現場には様々な要素がありすぎて、どこから見て良いのか?
どこから手をつけるべきなのか?
結果、何もわからないことが起こります。
そこで大事なのが理論。
“生産性を高めるために、どこが課題で、どこから見たら良いか”
この現場を見る視点、改善の仮説を作るものが理論です。
理論から見たら、ここが課題かもしれない。
そう頭の中に考えを入れて現場・現物・現人を見ることで、より効果的に改善のポイントを把握することができます。
もしかしたら、仮説とは違うところが課題を発見するかもしれません。
ですが、それも現場をみる仮説があってこそ。
理論とは違ったけど。仮説とは違ったけど。
それを発見できることも、理論の大事な活かしどころですね。
外部の専門家や、コンサルタント活用のキモはここにあります。
理論的に、外部の視点で。
現場では当たり前と思っていることに、違う視点でメスを入れる。
生産性の高い会社を作っている経営者は、これがとても上手です。
3.中小企業の生産性向上は2ステップで考えよう!
働き方改革や、地方の人不足が進んでいる今、
中小企業の生産性を高めることは、緊急性を要する課題です。
だから生産性を早くあげたいと悩まれる経営者から、相談を受けることが多くなりました。
今は何に取り組んでいますか?と伺うと、
ほとんどの方は“従業員の仕事のスピードアップ。効率化”
と話されます。
さらに質問。
いつになったら、スピードは上がりますか?
社長が目指す生産性目標に、いつ到達しますか?
と伺うと
“人のことだから。時間がかかるかもしれない。人によって成長スピードが違う”
となかなか時間の読めない改善が中心になっているケースが多くあります。
だからこそ、生産性の改善は2ステップで考えることが必要です。
=第一ステップ=
ターゲット設定・商品価値の付け直し・値付けの見直しによる利益アップ(First Step)
これが生産性を短期的に高める改善の内容です。
第一ステップでは、現場にあまり負担をかけることなく、経営者主導で判断・決断し、生産性を短期的に高めることができます。
しかもこの方法は確実性が高く、目に見えて成果をあげることができるため、社内の改善モチベーションを高める効果もあります。
この場合、理論やノウハウの方が力を発揮します。
=第二ステップ=
組織内の効率化(Second Step)
組織内の改善の中心は効率化。新たな仕組みの導入や、人づくり、作業時の手のスピードアップなどが挙げられます。当然、人の慣れ・習熟度に影響され、個人差もありますので、時間をかけて改善していくことが必要です。時間をかけながら継続的に、長期的な視点で会社や事業の生産性を高めていく。
この場合は、理論だけではなく現場現物現人がより必要になります。
この二つのステップを行なっていくことで、生産性をより高いレベルで、長期に渡って高め続けることができます。
これらのステップを効果的に動かしていく考え方が、
“理論と現地現物現人の組み合わせ”
両方を揃えながら、改善を進めていくことで成果は劇的に上がります。
いかがでしょう。
生産性向上は、中小企業にとって喫緊の課題。
特に地方の中小企業は、首都圏に比べても取り組んでいるところは少ないですし、
どうして良いかわからない経営者も多くいます。
現場に改善や効率化を求めすぎている経営者も散見します。
あなたはどうですか?
経営と現場。
経営者と従業員。
中小企業だからこそ、両方がそれぞれの立場で改善できる体制を作りたいところ。
そのために理論と現場現物現人の両方を意識したいですね!
【利益改善事例】年商1.8億円地方の洋菓子店が利益1300万を上乗せ!利益3倍化を実現した1年間の取り組みを大公開!
=PR=