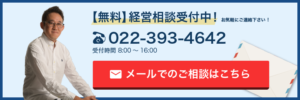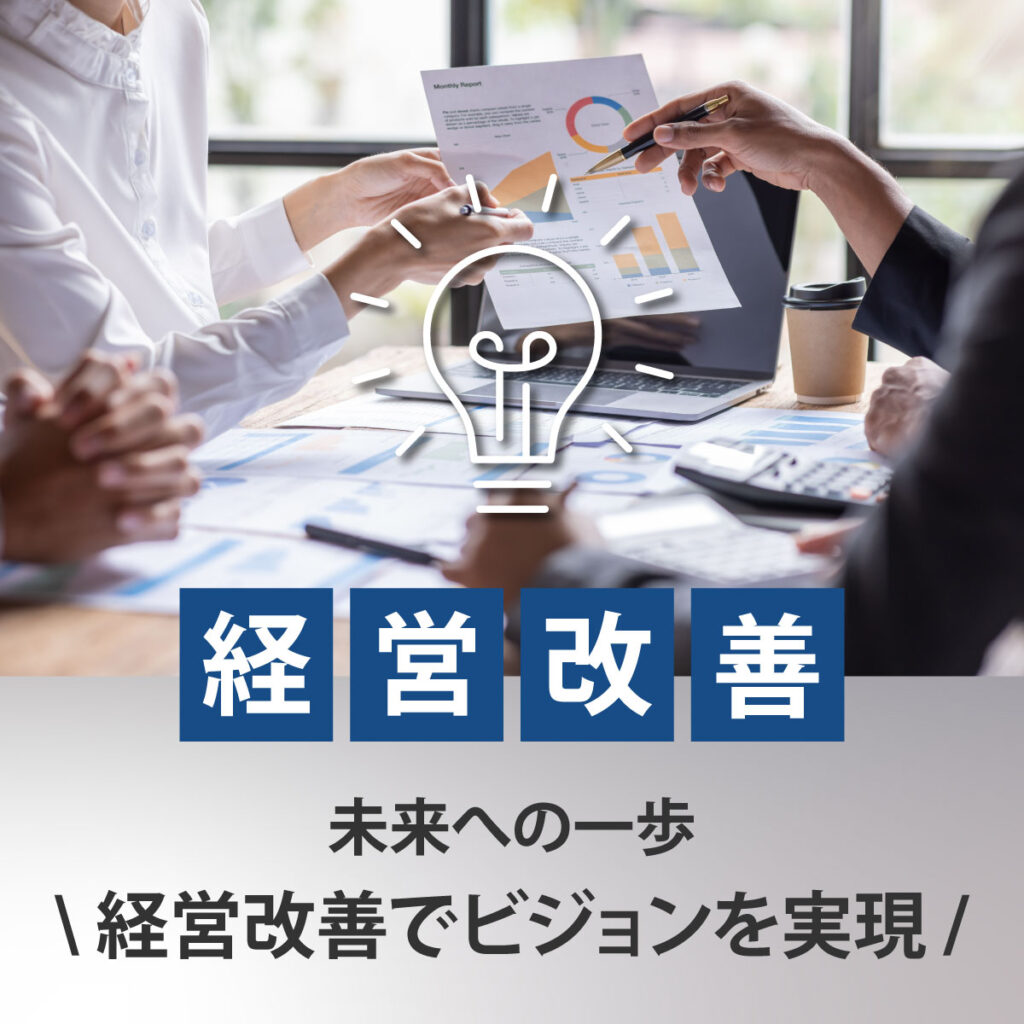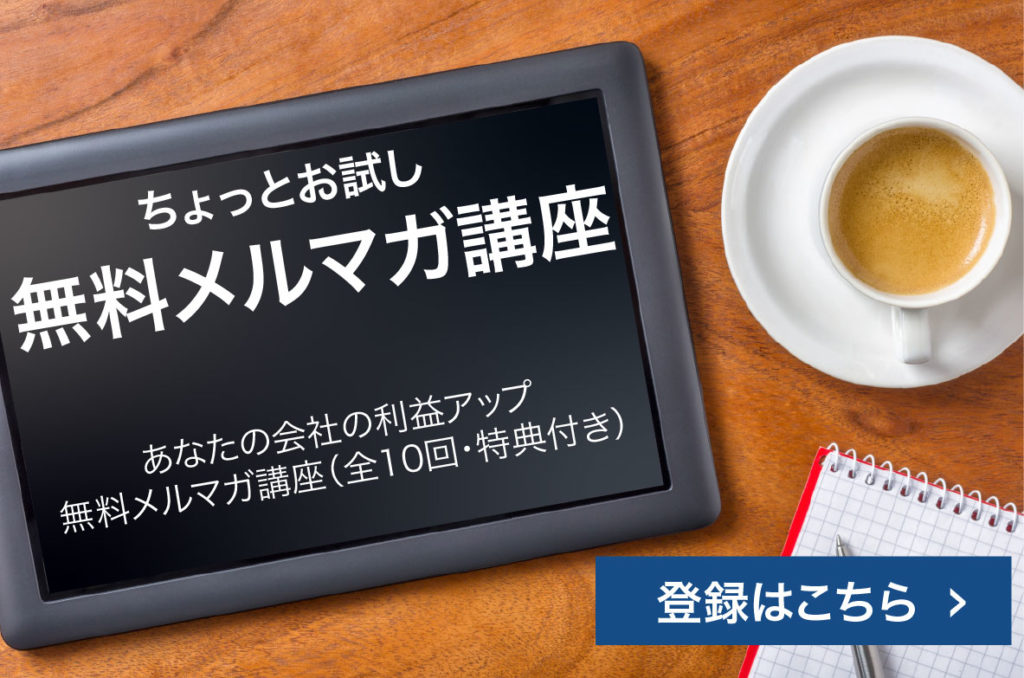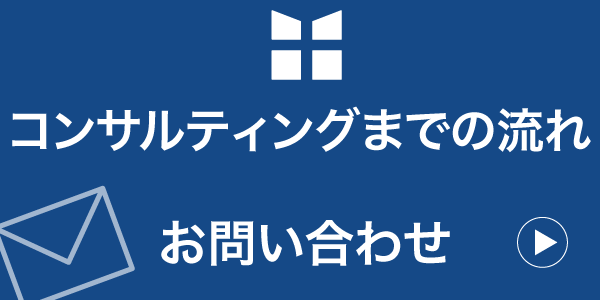中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント本田信輔です。
地方にも、中小企業にも、一次産業にも必ずやってくる働き方改革の流れ。
長時間労働の改善や時短。給与アップ、生産性向上と簡単に言うけれど。
今の仕事はどうする?
給与の元となる利益は?
人も足りないし。募集しても集まらない。
何かしないとダメなのに、どこから手をつけて良いかわからない。
残業代を払わない、あまりに無謀な仕事の押し付けなどは論外として、
中小企業だからこそ、地方だからこその悩みも多いですね。
世の中を見れば、経営サイドが働き方改革への対応を求められているような雰囲気ですが、
働き方改革は、経営陣、雇用されている側、両方に求められている事。
双方の変化があって、良い企業、良い地方、良い日本へと変わっていけますね。
今回は、働き方改革 経営者編。
従業員に変化を求めるのではなく、経営者自身の働き方をどのように変化させていく内容です。
https://met-p.jp/case-study/地方でも%E3%80%82年商1000万でも%E3%80%82小さな飲食店が毎月の/
目次
1.従業員の仕事の価値を高め、生産性を高めることこそ、経営者の働き方改革第一歩。
経営者にとって、働き方改革で最大の悩みは、時短で労働時間を削減しつつ、支払う給与もある程度維持していかないといけない点にあります。
労働時間が減るのだから、給与は下がって当然。と考えていれば、
給与は下がったのに、仕事量は変わらず、時間あたりの荷重が増えたと従業員の不満は高まる。
人手が足りないと現場の声は上がるが、人は集まらない。特に地方は厳しい。
不満が高まり、さらに従業員がやめていく。体や心を病んでいく。ブラック企業のレッテル。
従業員の時短分を経営者や家族で補っていくが、すぐに限界。
そのうち、こなせる仕事の量も質もが下がり、業績も落ちていく。さらに人を雇えない。
どんどんマイナスのスパイラルに陥っていく。
そうならないために、経営者は自身の働き方を変えていくチャレンジが必要です。
まず、経営者が考えるのは、従業員に仕事のスピードアップを求めることではなく、できるだけ短い時間、少ない仕事量で、今以上の利益を得られるようにすること。
現状であれば、今と同じ時間、今と同じ仕事量で、今の倍の利益を得られるように、経営者が自身の仕事のあり方を変えていき、段階的に社会の働き方改革へ近づけていく。
それが、現在働いてくれている従業員の仕事の価値・生産性を高めることにつながります。
これが、経営者本来の仕事であり、働き方改革の第一歩。
経営者は、職人的な働き方から、より経営者らしい働き方へと変わっていくことが求められています。
ではそのために、何をしていくのか。
2.顧客定義を明確にする。値付けをする。経営者しかできない仕事に注力する。
できるだけ短い時間、少ない仕事量で、今以上の利益を得るためには、
“自分たちの商品やサービスの価値をより高く評価してもらい、利益を確保できる適正な価格で購入もらう”ことが必要です。
まずは、経営者が以下の二つを働き方改革として、まずやらなくてはなりません。
・顧客定義、自分たちの商品やサービスに対し満足してもらい、適正な価格で購入してくれるお客様は誰かを明確にする。
・利益のとれる値付けをする。仕事の価値を高め、高い値段でも買ってもらえるようにする。
(1)自分たちのお客様を明確に定める 〜顧客定義
自分たちのお客様は誰か?ということ。ターゲットを明確にするということでもあります。
誰に自分たちの商品やサービスを理解・評価してもらい、ちゃんと利益の取れる値段で購入してもらうのか。
これを経営者であるあなたが、ちゃんと決めることです。
逆に言えば、それに該当しないお客様は断るという可能性もあること。
“あなたはうちにお客様ではありません”
とお客様を断ることを、従業員や現場が勝手にできませんね。
だから、経営者の仕事です。
利益を出せない企業や経営者を見ると、顧客定義ができていない場合がほとんど。
売上を取るために、どんなお客さんでも受け入れる。結果、あらゆるお客さんの満足を目指そうとして、力は分散する。仕事量は増えるが、満足度は最大にならない。
満足度が最大化しない結果、価値が上がらないので価格競争になる。
あちらのお客さんとの価格、こちらのお客さんとの価格で違うわけにもいかないから、安い方の値段にせざるを得ない。
どんどん会社も、従業員も疲弊していく。利益も出ない。
これでは会社自体がダメになってしまいます。
経営者が働き方として、お客様定義をすること。それを社内に発信していくこと。これが第一。
自分たちのお客様を明確に定めることで、商品やサービスの価値をどの視点で抜き出し、どのように伝えていくかが見えてきます。結果として、お客様が満足し、利益の取れる高い値段でも買ってもらえる。
さらに言えば、これから何に投資するか、今の仕事で何が無駄になるかも見えてきます。
(2)利益を決める超重要項目 〜値付けは経営者の仕事
企業や事業の利益は値付けによって決まります。これは間違いないこと。
値付けによって、利益を生み出すこともできますし、簡単に利益を喪失してしまうこともあります。
この重要な事を経営者が自分の仕事として、ちゃんと考えるという事です。
あなたの会社は値付けをどのように決めていますか?
だいたいこれくらい。
他社競合と比べて、あわせて。
キリの良いところで。
原価率を決めて、そこから逆算。
現場に任せている。
このレベルでは経営者が仕事をしているとは言えませんね。
値付けのレベルを上げていくことです。
経営者の仕事は、どれだけの利益を得るか、将来を見据えどれだけの利益が必要か。
これを考え、値付けをすること。
1個100円で売るか、120円で売るのか?
この商品が年間5万個売れていれば、たった一品で利益が年間100万円プラスされる。
たかが20円ですが、効果は絶大。
価格は、今の商品を見てつけるのではなく、
売りたい価格を決め、それに見合った価値を商品につけていく。
これがこれからの値付けです。
これを一つ一つ、決めることが経営者の仕事です。
特に値段を上げることは、従業員や現場はできません。
値付けの重要性をちゃんと認識し、経営者が決めていくこと。
経営者は、
顧客定義を明確にする。
値付けをちゃんとする。
これをベースに企業、商品やサービス、人の価値を段階的に高めていく。
この二つを経営者が自分の仕事としてまず取り組むこと。
今ある商品、サービスでも顧客を定め、価値を見直すことで、地方でも、中小も関係なく、会社や事業の利益は短期間で、確実に、大きく上がります。
現場に今以上の負担をかけず、今の1.5—2倍の利益を獲得できるようになります。
この利益を、これからの給与や、価値向上につながる投資の原資としていく。
将来、時短となって仕事量や生産量が下がったとしても、今と同じ、あるいは今以上の利益を確保し、従業員の給与も維持することができる。
これこそが経営者の仕事であり、経営者として一番の成果です。
3.これからの時短の考え方 〜無駄とは何かを定めて取り組もう
長時間労働の改善に時短。
労働時間を減らす流れができています。労働人口も減っていく。
どうしても手をつける必要性が生まれています。
製造ラインの見直し、オペレーションの効率化。機械やシステムの導入。
できるだけ時間と人手を減らして、効率よく。
今までにも、無駄を減らしているよ。人数もギリギリ。これ以上どうするの?
と多くの経営者が課題に直面し、悩みを抱えています。
残念ですが、今までの発想では、これからの時短には対応できないでしょう。
現場の部分的な効率化では、耐えられません。会社全体で考えること。
では、これはどうやって打破していくか?
まず考えることは、無駄の定義を見直すこと。
では、質問です。
あなたの企業にとって無駄とは何ですか?あなたは、なんと答えますか?
色々と答えはあると思いますが、これからの答えは、
“お客さんの満足、会社の商品やサービス、人の価値が上がらない全てのもの”
そう定義づけると、視点が変わり、社内にある本当に無駄なものが見えてきます。
逆に、減らしてはいけないこと、単純に時間を削減するのではなく、増やすべきことも見えてきます。さらに言えば、同じ時間であっても、仕事の内容や目的が変わってきます。
会社の仕事全てを、この定義で見直してください。
製造、販売・営業、総務・経理、経営、あらゆる場面で行なっていることは、なんのためにしているか。
お客さんの満足に繋がっているか、会社の価値を高めるものか考える。
意外と社員や従業員の方が、そのことをわかっているようにも感じます。
その上で、一つ一つの作業、運営体制、組織体制を見直してみることです。
例えば、会議については見直しが必要な場合が多く存在します。
営業会議、単に数字の報告会になっていないか? 次の仕掛けの説明に終わっていないか。
製造会議、目標の進捗確認で終わっていないか?
企画会議、本当に価値を高める内容が検討されているか?
経営会議、社長や上司の言いたいことを伝えるだけの場になっていないか?
社長や上司の満足・安心を得るための会議になっていないか?
逆に、今まで無駄だと判断されていたもの。
従業員のちょっとした休憩時間や談話の時間。あらゆる仕事に想像力や発想力が求められる今、こういった少しのコミュニケーションから新しい発想が生まれていることは、国内外の高収益型企業で実証されています。
もしかすると、休憩時間を増やし、販売員や営業スタッフ、企画スタッフの気持ちの余裕時間を用意した方が良い場合も。
これも、従業員サイドではなく、経営者サイドで決定、発信することができるものです。
もう一度、“自社にとっての無駄”を考え直す良い機会ですね。
新たな無駄の定義で、会社を見れば、時短のヒントが生まれてきます。
4.働き方改革で従業員に伝えるべきこと 〜会社では何を目的に仕事し、何に対して給与を払うのか?
経営者が働き方を変え、
会社の中で、本当に無駄なものを見直した上で、
経営者が、やらなくてはならないもの。
それが、従業員に対する、自社での働き方、給与の説明です。
“うちの会社は、何を目的として働くのか”
“うちの会社は、何に対して給与を払うのか?”
この質問に、あなたはどう答えますか?
その答えによって、従業員は働き方を考えます。
採用選考時に伝えれば、相手が自社を選択する一つの材料となるでしょう。
時間に対し、給与を払うのであれば、従業員は時間を増やすことで収入を獲得しようと考えます。
成果に対し、給与を払うのであれば、自社における成果は何かを明確にし、それに対し従業員は労働時間の長短関係なく、成果をあげて収入を獲得しようと考えます。
もちろん、時間と成果を掛け算する考え方もありますね。
雇用される側も、働き方を自分で決める時代。それによって、自分の責任で会社を選ぶことも求められます。
特に給与のもらい方は、その人の働き方、働く意欲、自身の成長の方向性を決定づけます。
うちの会社の働き方はこうです。と明確に示すこと。
これも経営者でなければできない仕事です。
そうすることで、双方納得の上で働くことができますね。
いかがでしたか。
これが、経営者の働き方改革。
経営者は、企業の価値を高め、そこから利益を生み出していくのが仕事。
働いてくれる従業員の仕事の価値を高めること。それをより高い利益につなげていくこと。
より短い時間で、より高い利益を生み出せるようにしていくこと。
従業員の雇用と生活を維持し、さらに価値の高い会社や事業へと発展させていく。
それによって、企業はもとより、地方の、日本の生産性が向上していく。
短い時間、減っていく労働人口の中でも高い生産性で永続していく。
これこそが、私たちミタス・パートナーズが推奨している考え方、これからの経営のあり方と繋がるもの。私たちがお手伝いするテーマです。
もちろん労働者、雇用される側も変化を求められていきます。
ですが、まずは変化できる経営者が変わっていく。
どうせ変化しなければならないのであれば、先に少しずつでも進めていくことが良いですね。
不明点や、悩みはどんどん私たちにお問い合わせください。
あなたの会社に合わせて、“これからの働き方”を共に考える機会を作ります。
利益を出したいあなたに読んでいただきたい利益アップのネタをまとめた記事はこちらから。中小企業の生産性が上がる!いろんなお悩み解決記事のまとめ
=従業員は何を変えていくのか?従業員編もご覧ください=
中小企業の働き方改革 〜従業員編”自分なりの働き方を定めよう”
=あなたにオススメのブログ記事はこちらから=
希望はある!量の生産性向上をやめれば中小企業の利益は上がる!
原価率が上がった?高い?と感じたら経営者が確認する3つのこと
=PR=