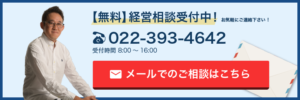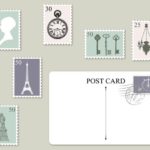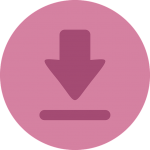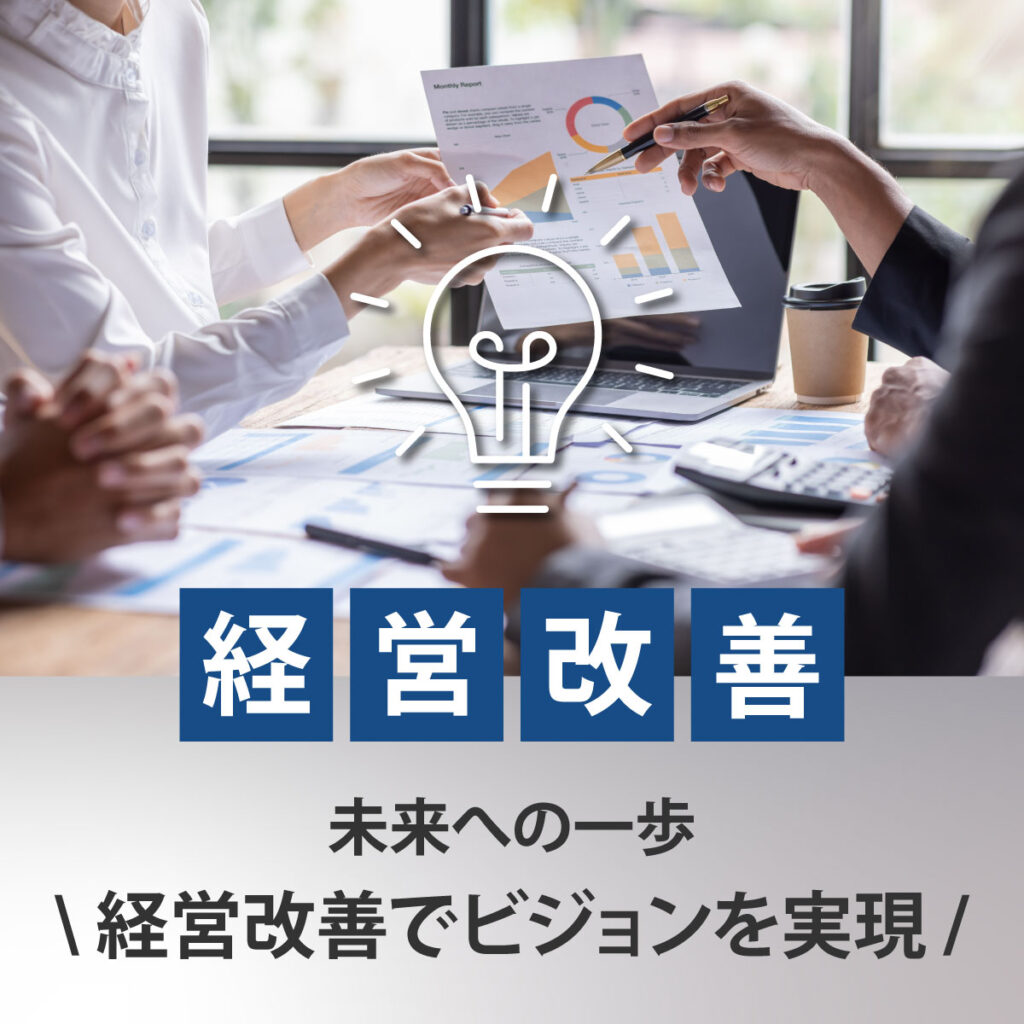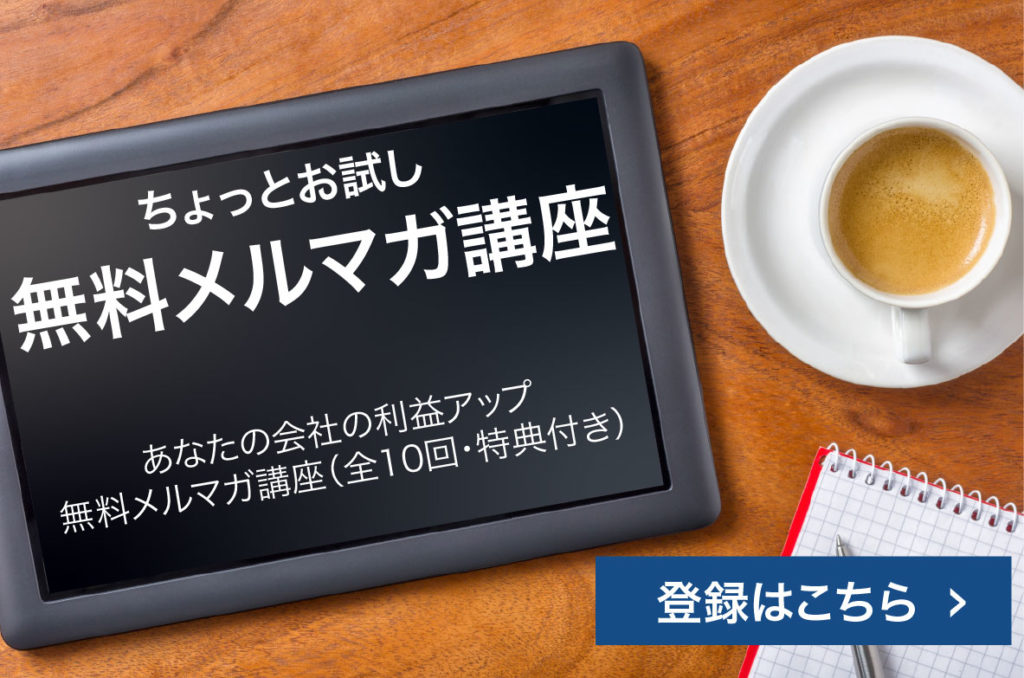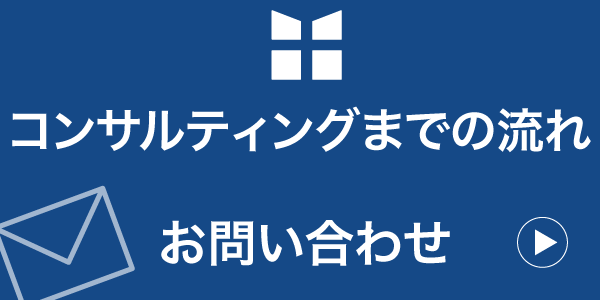中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント本田信輔です。
今回のテーマはお問合せが増えている「急激な原価高騰やコスト上昇への対策」
言い換えれば「急激に失われていく会社利益を守るための対策」についてです。
菓子業を始め食品業全体で原材料や包材、人件費などの経費が急激に上昇し、経営者の多くが悩みを抱えている状態。
クライアントはもちろん、ホームページのお問い合わせからも
「原価の上昇が止まらない。今年に入ってから問屋さんからの値上げ案内が次々と届き、ほぼ全ての経費が上がる」
「コロナやウクライナ情勢の影響で景気が悪いのに、値上げはできるのか?」
と洋菓子・和菓子問わず菓子店の経営者だけではなく、食品業や飲食業など幅広い業種の方から連絡を頂いています。特にコロナウイルスによるパンデミックや、ロシアによるウクライナ侵攻などによって原材料だけでなく、原油をはじめとしたコストも高騰、ここに人件費の高騰が加わっています。
ここ数年、原価やコスト上昇に合わせてクライアント先でも値上げを実施してきましたが、2022年に入り食品大手企業も軒並み大幅値上げ。それも以前のような3%〜5%程度の値上げではなく、8%〜15%近い値上げとなっていることも原価やコストの大きな上昇を物語っています。
大手企業ですらこのような状況ですから、中小企業はさらに厳しく。1年前に値上げした企業でも“再度値上げをしなければ”を議論する事態になっています。
コロナウイルスの感染拡大と、ウクライナ情勢によって停滞した経済の中で値上げをする不安もあるかと思います。お客さんの収入が減っている時に高い商品を買ってくれるのかと考えてしまうことも一理です。とはいえ企業として利益を確保し存続していくためにどのように対策を立てて対処していくかが重要。企業を守り、雇用を守り、地域の産業として生き残っていく。
今、この瞬間を危機と捉えるか、これをチャンス好機と捉え様々な対策で“会社を強くしていく”と考えるか。経営者がどちらの考え方をとるか、それによって企業存続が左右される時期であることは間違いないと思います。
目次
1.時間が経てば落ち着くは甘い!原価もコストも下がらない。
今は
「コロナウイルスの影響があり、生産地で製造が滞っているから」
「ウクライナ情勢の影響で」
と原価やコストの高騰は一時的と考える方もいらっしゃるでしょう。
ですが、よくよく考えてみて欲しいと思います。
以前から原材料やコストは上昇をしてきました。
その理由は、人不足と日本経済の停滞にあります。食品や原材料の多くを輸入に頼る日本の経済は世界各国の成長からは遅れ、停滞・衰退にも近い状況です。“日本の円”の力が弱くなっている状況。円安は進み、海外から仕入れるものの値段は上がっていきます。世界各国と比較すれば、日本のコロナウイルスによる経済停滞からの復活は明らかに遅れています。日本人の慎重な資質が経済回復を遅らせているという見方もあるかもしれません。
ですが、そうでは無いように思います。日本の経済自体が停滞している。たまたまコロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢によって原材料やコストが急騰しただけで、長い目で見れば製造原価もコストも下がることは難しいと考えています。
同じように人件費も下がらない。先進国の中でも給与水準の低い日本で、これ以上人件費が下がることも期待できない。むしろ人件費を上げていかなければ優秀な人材どころか、働き手すら確保できない状況にきています。
このことを踏まえれば、「今の原材料やコストの上昇は一時的。自社が利益を減らしても今を耐え忍べばなんとかなる」と考えるのは大きなリスク。「今後、さらに原材料やコストは上がることを想定する」ことが大事です。
2.値上げのタイミングはいつか?どのようにするか?
(1)値上げのタイミングは
今の原材料やコストの上昇を考えれば値上げを躊躇できる状況ではありません。今年に入ってから種類を問わず原材料は高騰、包材や経費も軒並み上がっています。小麦粉をはじめとした主要原材料、原油高騰によって輸送コストや保管コスト、包材、水光熱費など、ほとんどのコストが急騰し企業の利益率は大きく低下しています。それもわずか数ヶ月の間にです。
「利益が出ないかも」「今年は厳しいかも」と経営者が感じたら既に危ない。すぐに動くこと。
月次損益がマイナスに転落してからの対処では、会社に大きなダメージになります。
=値上げ時期を考えるポイント=
・値上げのタイミングは3週間〜2ヶ月間以内の閑散期。
・お客様へは3週間から1ヶ月の告知期間を経て値上げする
・値上げ告知は、昨今の原材料やコストの上昇を理由として記載。価格改訂のご案内として、各商品がいくらになるかは記載しない(値上げ後の価格検討は、値上げ告知期間中に行う)
・値上げの価格検討と、値上げ告知を同時並行で行う
これによって、値上げのスピードを上げていくことができます。原価やコストの上昇が緩やかであれば、【値上げの価格検討→値上げ告知】と時間を経てとの流れをとることもできるのですが、今はスピードが重要です。
(2)値上げ率、値上げ幅はどうするか
過去1〜2年以内に値上げを行い、原価高騰前に営業利益が8〜10%前後確保されていた状態であれば、今回の値上げ率は20%を前後に検討して良いと考えます。
値上げ率や方法については、こちらの記事でも詳しく書いていますが、
“お客様にとって、5%の値上げも、10%の値上げも、20%の値上げも変わらない。値上げによる一定の客数減を想定すれば、値上げ率を5〜10%で設定することの方がマイナス”ということです。
一方、値上げを2年以上していない会社の場合、20%以上の値上げを必要とする商品が出てきます。実際に最近のクライアント先でも値上げ率が35%となるような商品もあります。前述した通り20%までの値上げはそれほど影響ありませんが、20%を超える値上げとなる場合、値上げの影響が出やすくなるので次に記載する商品構成の見直し、各商品自体の見直しも合わせて具体化していくことで、値上げの影響を軽減していく取り組みの重要性も上がってきます。
値上げ率については、大手企業ですら8%〜15%近い値上げをしなければならない状況で、中小企業が10%前後の値上げだけで耐えられる状況にないことは理解していただけると思います。
(3)商品構成の見直し、各商品自体の見直しも行う
値上げとともに具体化しておきたいのは
①一番最優先に考えるのは主力商品 →主力商品のリニューアル、訴求内容の見直しなどは一番効果が高い
②全商品について商品品質の確認、仕上げや包装のクオリティを高める
③値上げに耐えられない商品の改廃(スクラップ&リニューアル)
④特に値上げ率の高い商品は大きな商品のリニューアルを検討する →原材料や包材だけではなく、形状や大きさ・内容量、ギフトであれば箱の入り個数なども見直していく。簡易な変更ではなく、大胆に変更して違う商品となるくらいに変えることも視野に入ります。
⑤新商品の投入 →値上げ上げと同時ではなくも良いが、値上げ後2ヶ月以内には新商品を出す。
今回の値上げは大きな値上げになる会社がほとんどです。実際に相談をいただくケースでも
「今の商品のままで、値上げに耐えられるだろうか不安」
「会社の規模から考えて、全ての商品に手をつけることは難しい。何を優先的に取り組んでいったら良いかを教えてほしい」
「大きく値上げしたことで、今までの値頃感をどう表現するかわからない」
などの不安や疑問を言われるケースも少なくありません。
値上げと並行して商品構成や商品自体の見直し、新商品の投入を行うことで値上げのマイナスを軽減することができますし、クライアントへは商品自体のリニューアルによって今の時代に合った、お客様にとってより買い易い商品開発も具体化してもらっています。
3.“不況なのに”を考える。抱えている不安はどうするか?
不況なのに値上げして買ってもらえるか?ということ。
世の中の景気が悪くて、個人の収入も上がっていない。こんな時に値上げして高い商品を買ってもらえるのか?という不安は多く聞かれます。確かに価格訴求を続けてきた企業や業態では、今後さらに価格競争が激化していくことになると想定しています。価格競争が進むのは、コスト改善やスケールメリットの大きな大企業。さらなるスケールメリットを高めるために大手企業同士の合併や買収といったことも増えてきて、最終的に価格競争は業界一番企業が圧倒的に有利になるでしょう。
当然、中小企業に太刀打ちできる余力はありません。
一方、価値で訴求してきた中小企業にとって、消費者の収入減による影響が大きいのは来店頻度や購買頻度の減少。お客さんは収入が減っても、今まで経験してきた生活レベル(商品やサービスのレベル)を下げることはできません。少し高くなったなと思っても、品質の劣る安い商品やサービスに変えることはできない。求めるレベルを維持しつつ、頻度を減らすためです。
例えば。今まで美容室に通っていた女性が、収入が減ったからといって10分カットのような業態で髪を切ることはしない。同じレベルの美容室には通うが、通う頻度は月1回から月2回に減らす。そのために2ヶ月間維持できる髪型に変える。そのためにちょっと高くてもベストの技術を持つ美容室を選択する。というイメージです。
来店頻度や購入頻度が減りますから。中小企業にとって価格を下げる、価格競争でという選択は死活問題。客数が減った上に、客単価まで下がるということにつながるからです。
そう考えると、
中小企業にとってこの不況という環境下で値上げをおこなっていく方向性としては、
①商品価値を高めながら、値上げを具体化していく
②安いものが良い風潮が世の中に溢れるが、それは大企業だけができることと方向性を決める。中小企業は価値重視で、高くなっても買ってもらえるように商品もサービスも向上・進化・変化させていく。
③今の不況は客数や購入点数の減少につながるため、客数ではなく客単価を重視する。
ことです。
4.今は経営者主導。合議制などをとっている時間は少ない
これだけ企業を取り巻く環境が物凄いスピードで変わっている今、経営もスピードが重要です。ある企業で実際にあったのは、各部門・グループ会社間でのすり合わせに時間がかかっている事象。値上げ一つを決めるのにも、各部門長が集まり、会議をし、さまざまな部門の状況や都合を言い合い、値上げの実施が半年や1年などというケースです。
原材料が高騰し、会社の利益率は急速に悪化している。仮に企業年商10億だとして、原価率が5%上がれば、年間粗利ベースで5000万、半年としても2500万の利益が失われることになります。会社の利益は失われ、キャッシュフローは悪化し、財務状況に大きな打撃を与える。そんな状況が目の前で進んでいる。
各部門の言い分を聞いて、すり合わせている間に会社が滅ぶ。
だからこそ今は経営者主導、スピード重視で進んだ方が良い。
社内のさまざまな都合や軋轢、急な変化による従業員からの不安や突き上げもあるかもしれない。だが、今はそれを乗り越える状況だということです。
値上げは経営者がスピード感を持って決断し、具体化の指示を出していく。その上で従業員や各部門とともに考え、具体化してほしいことは、“値上げ後にお客様へどのような商品やサービスを提供していくか。値上げ後の価格に相応しい商品やサービスの向上”についてです。
5.これからを生き残る次なる一手は
今が危機か、チャンスかと聞かれれば今はチャンスだとお伝えています。確かに値上げは大きな危機かもしれません。ですが私たちのクライアントは危機のように見える“値上げ”をチャンスに変えています。
一例を挙げれば。
・値上げとともに現場の危機感が上がり、商品の品質安定や仕上げ、包装など当たり前の品質を向上させることができた。
・値上げに耐えられない主力商品を大胆に見直し、今の家族構成や消費者のニーズに合わせた規格(大きさ、量、形状)や提供方法に変えることで、さらに強い主力商品へと成長させることができた。
・値上げだけに頼ってはいけないと現場の意識が変わり、現場のコストや生産性や効率に対する意識アップ、具体的な取り組みにつながった。
など。値上げはマイナス面を見るのではなく、利益改善に加え社内外に対するプラスの効果もあるということです。
さらに、これら経営者が値上げの次の一手として取り組み始めているのは
- 新分野への展開、異なるマーケットへの参入
- 品目の異なる商品群の付加
- 新たな販売方法による商圏の拡大や新規顧客の獲得
による新たな売上獲得や来店頻度向上です。
近年は菓子業が商品構成に菓子以外の品目やサービスを増やすケースも提案しています。ベーカリー、ヨーグルトをはじめとした乳製品、健康食品、発酵食品、地元の加工食品や素材、農産品や畜産品、新たな“付加価値型”業務用食材への展開、法人需要の獲得を目指した商品・サービスなど。
菓子のマーケットにこだわらず、自社の強みや地域の産品・文化などを活かした新たな展開です。コロナウイルス感染症の拡大によって生まれた中小企業向けの補助金“事業再構築補助金”を活用するケースも増えています。こういった取り組みは店舗への来店頻度を増やしたり、利益率や生産性をより改善したり、自社の苦手な部分(閑散期、販路)などの改善を図ることを目指しています。
これら経営者の方々に共通しているのは
「苦しい今こそ攻める時。苦しい今、守りに入れば会社は滅ぶ」の一点。
将来が見通せず、不明確な未来に様々な不安を抱えているのはどの経営者でも同じ。
ですが、今動くかどうか、事態を静観するかどうかは経営者の考え一つです。
これは、値上げをする経営者やオーナーに毎回お伝えしていることですが、まず大事なのは、自分達の評価を高めること。
地域でこれだけ評価されていることへの自信を持つことです。
地域で長年経営し、支持され、店舗が継続できていること。これが地域のお客様の評価です。それは価格の安さなのか?品揃えなのか?商品の美味しさなのか?コンビニが菓子業の競合と言われて久しいがちゃんと来店してくれて、買い物してくださるお客様がいる。価格の安さや利便性ではなく、あなたの会社の今までの取り組みや商品の品質を認めてくれていると考えることです。
値づけは自分達の技術力や働きを表現する指標。安ければ自分達の実力も軽く見られ、それは従業員のプライドも給与も下げることにつながる。これから人口が減っていく中で、数を売って利益を稼ぐ薄利多売のビジネスモデルが中小企業に合うかどうか。
こういったことを考えながら、今の状況を突破していく。急激な原材料やコストの上昇という状況を、チャンスとして活かしていく。これが対処法であり、対策だと考えています。
利益化に向けて、不安の解消、具体的な取り組みのアドバイスを行なっております。
急なご相談についても、できる限り対応いたします。
あなたのお店の強みを生かし、将来をどのようにするかを共に考えていきましょう。
一方的に提案することはありません。お互いに理解を共有して前に進みます。
利益を出すことは、より良い未来への入り口だと考えます。
利益があるからこそ、もっとやりたい未来を描き、理想の実現に向けてチャレンジできる。
必ず良い未来が描けます。
気軽にご相談ください
弊社ではこれまで開業してから約350件のご相談を承り、そのうち約180件の企業・事業者さんのご支援を行いました。もしお困りのことがございましたら、お力になれる点があるかと思いますので、お気軽にご連絡ください。
=PR=