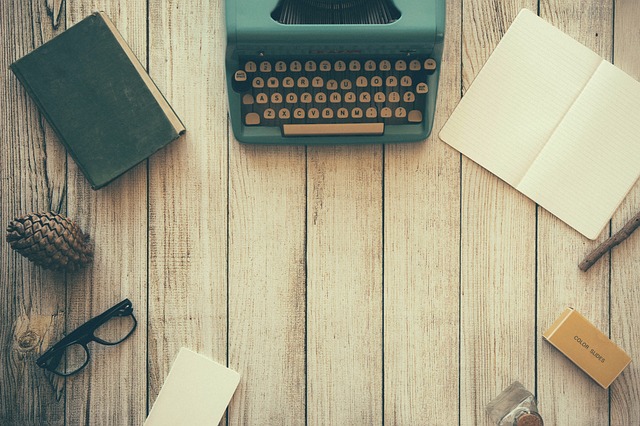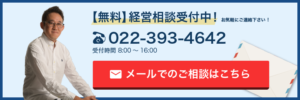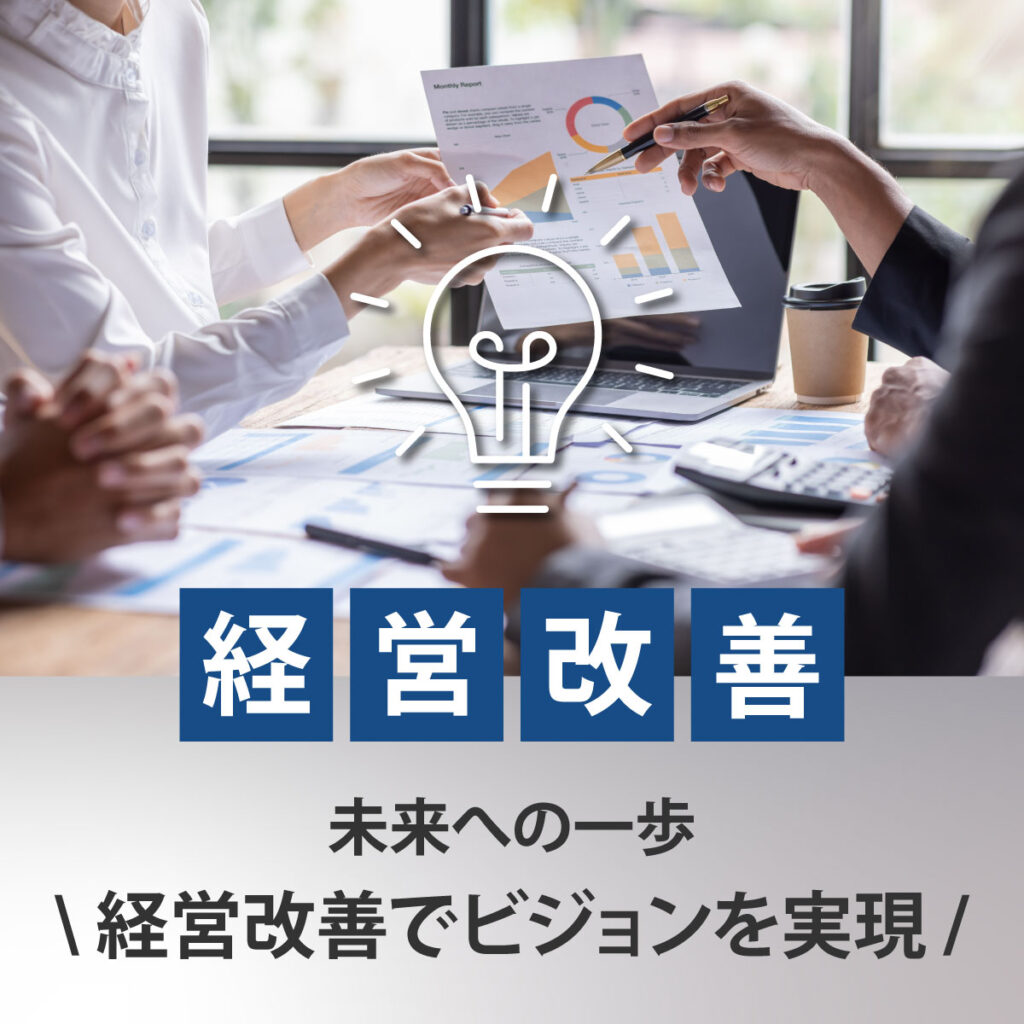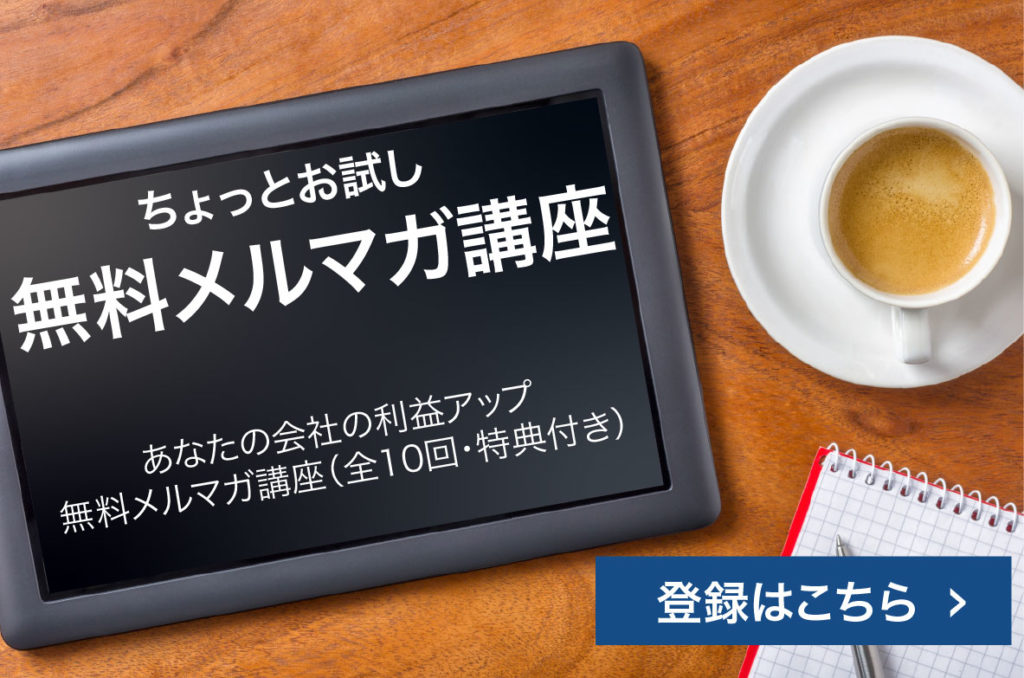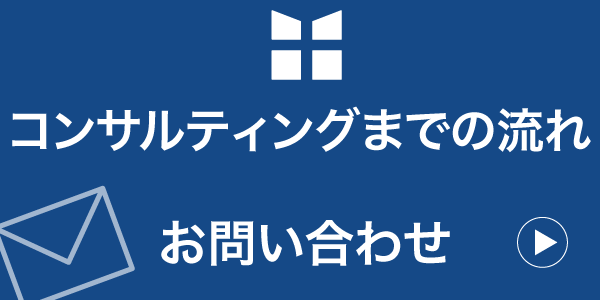本田さん、マニュアルを作ろうと思うんだけど・・・。
これは最近、実際にあった相談。
現場で気になるところがあったようで。
その時にお伝えした、マニュアル作り3か条をお伝えします。
しかも、ただルールを決めるだけではありません。
ちゃんとマニュアルが
・ルールを守り、継続でき、
・ブランド力アップに役立つ
・従業員の成長にもつながる
ようにするためのポイントです。
1.マニュアルルールは3個〜10個に絞る
経営者としては、現場で気になることがたくさん。
守って欲しいことがたくさん。
うちは基礎的なことすら守れない。
あれもこれも、ルールを決めて・・・。
そうすると、マニュアルの項目はどんどん増えていきます。
ですが、ここはグッと我慢。
初めて作るマニュアルは、あえて項目を10個以内(理想は3個)に絞ります。
理由は簡単。
多くの項目を作っても、ほとんどの場合、覚えていない、忘れている、全部やりきれない。
項目が多く、一気に全部できないという理由で、マニュアルがなし崩しになっていく。
1年後には、マニュアル自体の存在も忘れ、何も守られていない状態に。
これで、マニュアルを作った労力と時間が無駄に。
トドメに、ルールを守らないという風土文化が生まれます。
それよりは、絞り込んだ項目を深く、徹底して一年間継続する方が、お客様も変化や価値を感じ、ブランド力の向上につながります。
一つ一つ目標をクリアしていくことで、現場にも達成感があり、次の課題に臨むモチベーションも上がりますね。
実際に、ある百貨店では”お釣りのお札を新札で”を徹底をしている事例も。
小さなことですが、
“些事に神は宿る”
と言われるように、ブランド力とは小さなところで感じるもの。
実際にその百貨店の近くには、売上も、立地も、売場面積も、品揃えも上の競合百貨店があります。ですが、いざという時、その百貨店は地域の人から頼りにされ、ブランド力もより上位におかれています。
一つの項目を徹底できない状態で、多くの項目やルールを守ることは難しい事。
多くの項目を虫食い状態で具体化していくよりも、まずは本当に必要な項目を絞り込み、精度高く徹底継続できるマニュアル作りをした方が効果が感じられますし、ブランド力の向上にもつながりますね。
2.マニュアルの3割は経営者、7割は従業員が決める。
ルールを作るとき、従業員やスタッフを交えてと話される経営者は結構いらっしゃいます。
プロジェクトチームを作り、ミーティングで一つ一つ決めていく。
流れとしては間違いないのですが、気になるのはミーティング中の経営者の声の大きさ。
“みんなで決めていく”という割に、経営者やリーダーの声が大きい。
こうしたい・ああしたいも強い。モデル店や知り合いの店も見ているし、話し慣れもしている経営者の影響力は大きい。
結局のところ、
みんなで決めたよねと言っても、社長のやりたいように決まったよね。
はよくあること。
ルールを具体的にやるとき、“みんなで決めたことでしょう”という言葉が上滑り。
経営者が決めるのは、全体の3割が上限。
経営者は”これだけは絶対に貫きたい”というところを絞り込んで決めること。
10個のルールを決めるのであれば、3個までが経営者。
3個のルールであれば、1個まで。
このルールを明確にしておくことで、従業員が自分たちで考え、納得して決めたと実感し、より実行度の高いマニュアルが出来上がります。
3.うまく外部の声を取り込むと、新しい視点が見えてくる
マニュアルは自分たちで作れます。
ですが、自分たちだけで作るデメリットは、自分たちのできる範囲に収まってしまったり、都合やできない理由を考えすぎて低い目標設定になりがちなこと。
そんなとき、お客様、モニター会員、外部の研修機関や専門家、コンサルタント、アドバイザーを要所で活用することもオススメ。
マニュアルは、自分たちの力を高めるもので、現状でできることだけを考えても効果はない。
どうやったら、自分たちの力を高められるか、外部の目線で見てもらい、評価してもらったり、より高い目標設定をしてもらうことが肝要ですね。
いかがでしたか。
伸びている企業や組織は、シンプルに物事を進めているところがほとんど。
多くの項目を定めるやり方は、減ってきています。
多くの項目を定めたマニュアルがあっても、それが活かされていない組織も多いのが現状。
細かく、ルールをガチガチに定めていくよりも、
考え方や将来像を見据え、一つ一つを丁寧に、より高いレベルでできるよう、
時間をかけて育てていくカタチを考えては。
マニュアルが活かされ、
現場で継続され、
しかも、ブランド力が高まる
もしも、あなたが会社のマニュアルを作りたいと思ったとき、どうしますか。
今のマニュアルは本当に活かされていますか。
=PR=