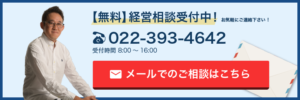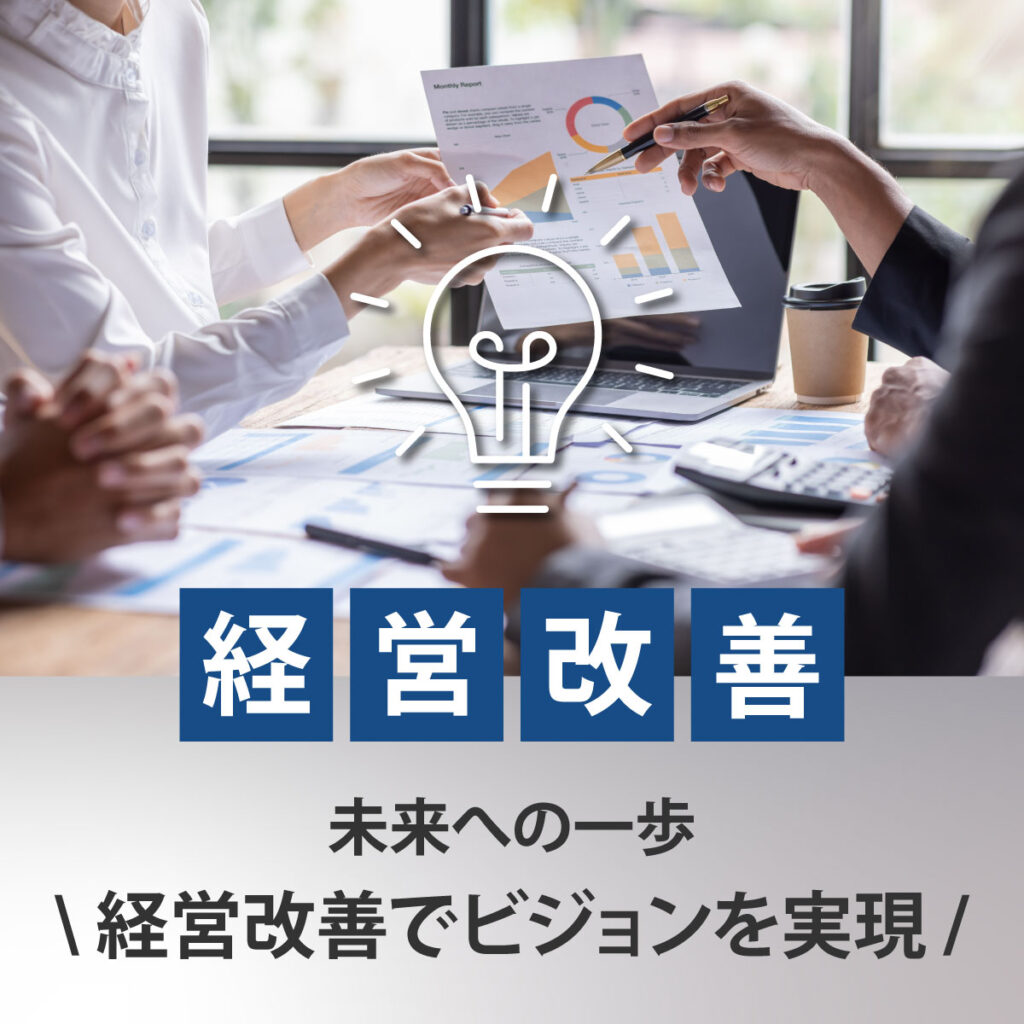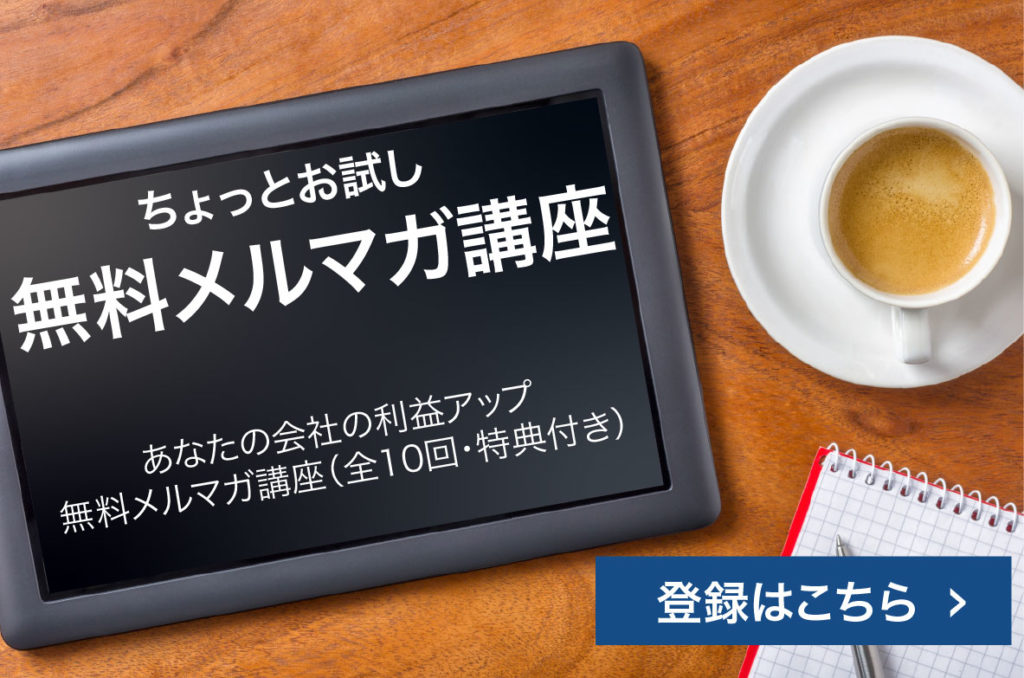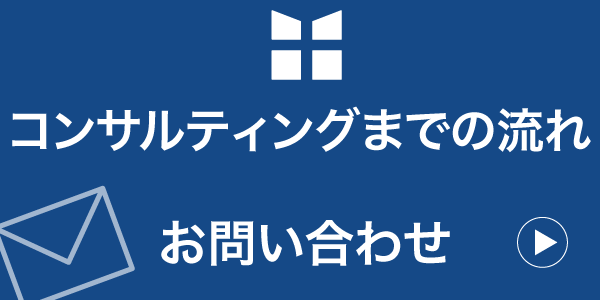利益を3倍にする経営改善コンサルタント本田信輔です。
経営改善はよく耳にする言葉だと思います。経営改善計画という言い方もそうですが、行政機関でも経営改善をサポートする組織・団体があり、経営改善のための助成金・補助金なども用意されています。
聞き慣れた言葉といっても、会社の急激に業績が悪化した。赤字が数年間続いて銀行や会計事務所から経営改善をしてくださいとか、新規融資や返済条件の緩和をするためには経営改善計画書の作成が必要ですと言われた時。
なんとなく日頃から「会社の業績を立て直しておかないと」と思っていても。
ある日「経営改善の必要性」とか「経営改善計画書を作成しないとお金を貸せない」と言われると、肝がスッと冷える感じがする。そう言われる経営者も多くいます。
逆に今の経営状況が順調でも、事業の見通しや、会社の将来のことを考えたり、後継者への事業承継を視野に入れて、早い段階から経営の収益性を強化したいと“早期経営改善”に着手する経営者もいらっしゃいます。
では、経営改善とは何をすることなのか。
会社の業績を立て直したり、さらに高めていく秘訣はどこにあるか。
このブログ記事では経営改善の基本をお伝えしています。
1.経営改善とは何をすることか? 大事なことは?
経営改善とは読んで字のごとく、経営を改善することです。
なんとなく想像するのは、売上を上げる。利益を上げる。
これらをひっくるめて、業績を改善するという表現をします。
会社や事業を存続させるために商いの仕方を見直し、販売促進や営業体制の強化、商品開発、人事体制の見直し、コスト削減等を行い収益をアップさせる。
特に業績を改善することで最も大事なのは“利益を生み出す”こと。
経営者によっては売上アップや回復ばかりに目が行く方もいらっしゃいますが、どんなに売上を上げても、会社に利益が残らなければ(増えなければ)意味がありません。
その点で考えると、ただ単に売上アップとかコスト削減をするような改善だけではなく、戦略的にビジネスの利益構造全体を俯瞰して改善することが経営改善と言えます。
当たり前のことですが、経営改善は個々の会社によって方向性が異なります。
経営者の思考や性格や特性、業種、規模、置かれている環境、地域特性、自社の強みなど総合的・客観的に診断する力が必要で、私も経営コンサルタントとして中小業種様々な企業の経営改善の相談を受けてきましたが、正しく方向性を定めて経営改善をしている企業は意外と多くありません。
実際に企業に訪問して経営者の方の相談を受けると、他社競合の成功した例をそのまま真似したように取り組んでしまい、結果として改善がうまく進んでいないケースが50%以上を占めているように感じます。
唯一全ての会社の経営改善にある共通点。それは経営者の考え方・思考をより良くする(改善する)ことです。
読んで字のごとく、経営改善とは。
経営を良くすること。つまり経営者が変わる・改善することです。
経営者自身が変わると強く決断しなければ、経営改善は進まないし、成果を生み出すこともありません。
時々“経営改善”という名で“現場改善”をイメージされる経営者もいらっしゃいますが、現場改善は経営が改善された次のステップです。
経営者が変わることが経営改善。どの会社でもまずはそこから始まる。この認識を持ち、誤った経営改善を進めてしまわないようにすることが必要です。
2.経営改善の進め方
経営改善を計画化する、具体化する上で一番最初にすることは、
「目指したい将来の姿・理想像を明確にすること」
・売上や、利益はどのくらいにしたいのか?
・社員の待遇、福利厚生などはどうしてあげたいか?
・5年後、10年後に実現したい将来像は?
・経営者としての夢や理想の会社は?
などを明確にし、目標や目的を定めることが大事です。
(経営者によっては「数年後の事業承継に向けてより良い形で手渡せるよう準備をしたい」と言われる方もいらっしゃいます)
将来の姿・理想像を明確にし、目的や目標設定をすることで解決すべき今の課題と優先順位が見えてきます。
これはとても大事なプロセスで、経営改善が正しい方向へ進むことにつながります。
せっかく経営が改善されたとしても、その改善が将来につながらないものであれば意味がない。無駄な回り道を選択したことになるからです。
簡単な例で言えば、
今目先の売上を上げるために値引き戦略を選択したとする。
でも、将来は価格ではなく、価値で消費者に選択してもらう企業を目指したいとする。
そう考えると、目先の売上を上げるための値引き戦略は、将来の会社にとってマイナスのイメージを植え付けることになる。
つまり、マイナスの経営改善が進んでしまうということです。
経営改善をより良く進めたいのであれば。将来につながるものにしたいのであれば。
目指したい将来像・理想像を定める
↓
将来像・理想像を実現するために、解決すべき課題を抽出する
↓
課題解決のための施策を検討し、具体的な行動へ移す
この流れを大事にすることです。
その中でミタス・パートナーズが意識しているのは、理想像や将来像を実現するために必要な資金はどれくらいなのか、“どれだけの利益化”が必要なのかということ。
“利益”を出すことを経営改善の第一段階目標として設定しています。
“利益”がなければ会社や事業を存続させることができない。
“利益”がある程度なければ、経営者は動くことに躊躇しやすい。
“利益”があるからこそ、全力で新しいことにチャレンジできる。
と考えているからです。
3.経営改善は、いつ、誰とするか?
経営改善を銀行や会計事務所などから求められるのは、
・急速に業績(売上・利益)が悪化した
・2〜3年間、赤字が続いた
・赤字で融資やリスケを依頼しなければならなくなった
が多いです。外部から指摘されて、経営改善や経営改善計画書の作成に着手するケースが多いと感じます。
とはいえ、経営者にしてみればそれ以前に経営改善の必要性を感じている場合がほとんど。
一方で、財務状況が良い時に「いつまでも今と同じような、良い状況は続かない」と危機感を持って、次なる経営改善に取り組む経営者がいることも事実。
経営改善はいつ始めたら良いという目安はありません。
経営者が何かしら、少しでも危機感を感じたら取り組む。というのがベストと考えています。
そして。
経営改善は誰とするか。誰と考えるか。
経営改善の目的は、会社や事業を継続するために「業績を上げること」「理想の実現に向けて今ある課題を解消すること」、何よりも「経営者の考え方・発想をより良くすること」にあり、個々の会社で方向性も具体策も大きく変わり、無限の方法論があると言えます。
そのような経営改善を成功させ、より大きな成果に結びつけたい場合には、下記のような一定以上の経営能力・ノウハウが重要です。
・銀行や会計事務所といった財務・数値面からの指摘だけではなく、企業戦略・組織論・人材育成・マーケティング・改善のための具体策といった幅広い領域を知っていること。
・世の中の将来予測や、時流予測を経営者と話し合うことができること。
・あなたの会社を客観的に、今とは違う視点で見て、評価・診断できること。
もちろん全てを任せて作ってもらうというのは論外ですが、これら能力を持った人と経営改善をすることが成功につながります。
経営者は、どうしても自分の会社を色眼鏡で見てしまう場合があります。
自分の会社を知りすぎていることによる過小評価・過大評価は良くあることで、そのほかにも過去の成功体験、世代間ギャップなど。経営改善の判断を誤ってしまう要因に注意が必要です。
4.経営改善 チェックポイント
経営改善について、以下の点で該当するものがあれば経営改善の能力が欠けている可能性があります。せっかくの経営改善が、あなたの会社の将来にとってマイナスになる。無駄な回り道をしてしまう結果に繋がることも多く起きています。
=チェックしてほしいポイント=
①決算書が読めない・読んでいない・よくわからない
②改善するポイントがわからない
③改善するところはたくさんあるが、どこから手をつけて良いかわからない
④セミナーやビジネス本・経営書を読んでも参考にできない
⑤会社の問題点や課題がどこにあるか、発見できない
⑥利益が上がってこない。努力したぶんの成果が出ていないと感じる
⑦経営者自身が疲弊している。従業員も疲弊している。
⑧なんとなく将来に不安を感じている
⑨経営改善の効果が実感できない
⑩社内の雰囲気が悪化している。退職する従業員が増えている
NEXT→中小企業の経営改善を効率的に成功させる4つのポイント
=PR=