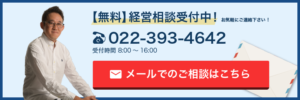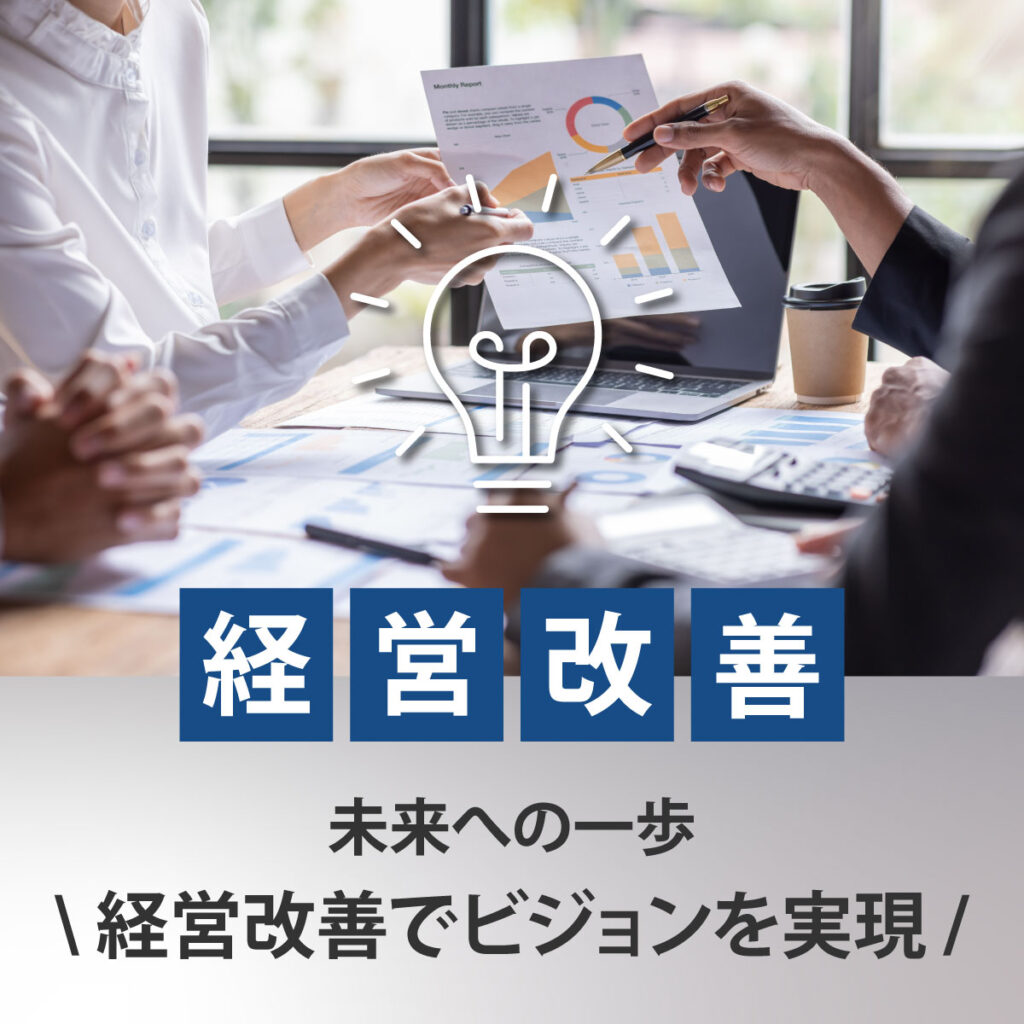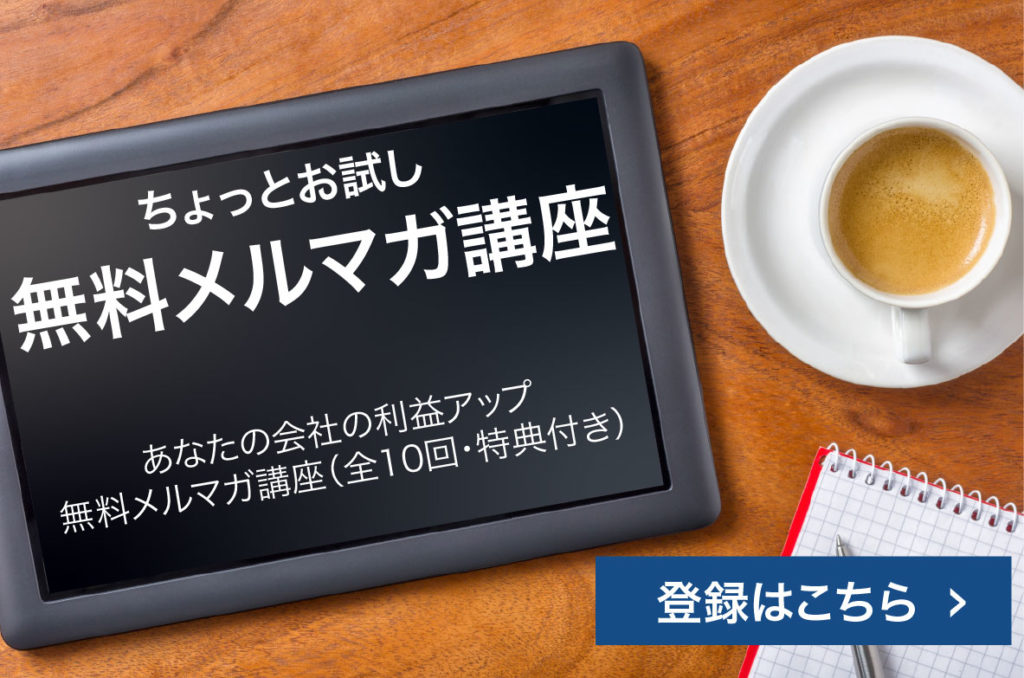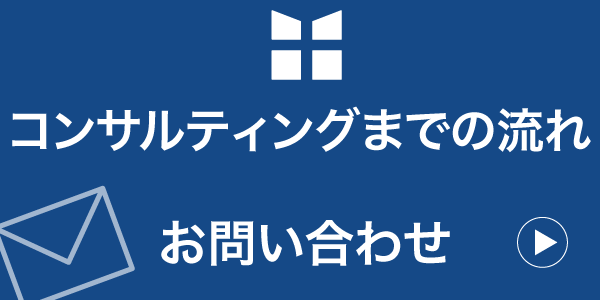今回の記事は2022年(令和4年度)に、菓子店やケーキ屋さんをはじめとして、中小企業や食品製造小売業で使える補助金・助成金についてのメリットや、活用にあたっての注意点やデメリットをまとめています。
ミタス・パートナーズでも補助金や助成金の申請サポートを行なっていますが、最近はコロナ禍の影響や消費者心理の変化、原価やコストの高騰などの影響もあり、これらのお問合せや実際にご支援するクライアントも増えています。
国・自治体としても様々な支援プランの一つとして、販路拡大から商品開発、設備投資や新規事業展開など様々な補助金・助成金を用意していますので、上手にこれを活用していただけると良いなと思います。
とはいえ、大前提として私たちがお伝えしているのは“補助金や助成金ありきの事業や取り組みはしない”ということ。「こういう新しい事業をしたいけど、補助金があれば助かる」や「社内の効率化や省エネをするんだけど、何か補助してくれるものはないか」などは積極的に応援しますが、「補助金が出たらやる」や「まずは補助金を探してから」という“補助金ありき”のケースはお受けしないことにしています。
“補助金ありき”で物事を進めた結果、スピードが遅くなったり、好機を逃すケースもたくさんあるし、実際に補助金の採択を受けても“自分達にとって使いづらい補助金”になるのであれば、無理しない方が良いともお伝えします。
補助金は上手に活用するもの。補助金頼みにならないこと。自分達がやりたいことをサポートしてくれるもの。補助金や助成金を上手に活用できる会社ほど、このスタンスを崩していません。
あなたの会社でどのような取り組みをしたいのか、将来的なビジョンも踏まえて、この記事を読んでいただければ良いなと思います。
国で2022年(令和4年度)に発表れされている補助金・助成金のうち、特に菓子店やケーキ屋さんで効果的に使えそうなものを選定し、活用する上でのデメリットや注意点も記載しました。
※このほかにも、各都道府県や市町村で独自に用意している補助金や助成金もありますので、そちらはご自身の地域自治体でご確認ください。
目次
まず最初に。中小企業と小規模事業者の違いを知っておいてください
補助金や助成金を申請・活用する上で、最低限抑えておいてほしいのは、「中小企業」と「小規模事業者」の区分についてです。自分の会社がどちらに該当するかで対象になるかどうかや、補助金の上限・補助率などが異なる事があります。これらの区分や定義は中小企業基本法という法律で決まっていますので、補助金によってこの定義が異なることはありません。
ちなみに従業員数については、雇用形態を問わないケースが多いので、基本的には正社員・パートの区別はなく従業員数に換算します。
=中小企業の定義=
下記条件のうち、従業員数もしくは資本金のどちらかで該当すれば、中小企業として認められます。
製造業・その他の場合:従業員300人以下 又は 資本金3億円以下
卸売業の場合:従業員100人以下 又は 資本金1億円以下
小売業の場合:従業員50人以下 又は 資本金5,000万以下
サービス業の場合:従業員100人以下 又は 資本金5,000万以下
=小規模事業者の定義=
製造業・その他の場合:従業員数20人以下
商業・サービス業の場合:従業員数5名以下
菓子店・ケーキ屋さんの場合、ほとんどは製造業・小売業のどちらかに該当するかと思います。
では、次項より具体的な補助金についてお伝えしていきましょう。
1.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ご存じ“ものづくり補助金”です。中小企業や小規模事業者が行う革新的(これは自社にとって)なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援する補助金です。今までの生産体制を効率化したり、新たな販路開拓や事業拡大に向けて生産量を強化するための設備投資に使うケースが多く、既存商品の生産性向上のための機械導入などで利用された方もいらっしゃるかもしれません。菓子業の場合、製造機械の他にも包装機だったり、商品をカットする機械だったりが比較的多いようです。
補助金の上限額は、従業員数によって決められており、
従業員数21人以上:1,250万
従業員数6〜20人:1,000万
従業員数5人以下:750万
となっています。補助率は中小企業で2分の1、小規模事業者で3分の2です。
補助金としても知名度が高く、この記事を読んでいらっしゃる方の中には一度は検討・申請された方もいるかもしれません。
年度中に3〜4回(3ヶ月おき)の公募があるため、自社の状況に合わせて申請することができますし、中小企業にとって大きな投資となる設備投資が対象となるため、リスクの軽減や効率化に向けた積極的チャレンジを後押ししてくれます。
ちなみに直近第9次公募の採択率は約60%です。
=デメリット・注意点=
・多くの方に知られているだけに競争率はそこそこ高く。申請のために必要な事業計画書も数字的な根拠や外部環境分析などの作り込みが不可欠です。
・複数回の申請・採択も可能ですが、採択回数が増えるごとに審査点が減点されるため、回を重ねていくと採択されづらくなっていきます。
・申請から採択後までの事務作業の負担も多いことも大変。金額的にはそれなりの額が補助金として出ますが、基本的には補助金は後払いなので、補助金支払いまでのキャッシュについても確保しておく必要があります。
ものづくり補助金の総合サイトはこちら
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
2.IT導入補助金
サービス業を中心とした中小企業・書規模事業者が生産性を向上させるために、新たなソフトウェアやITツールを導入する際に、補助を受けることができ、今後の労働人口減少、従業員減などをカバーする社内のD X推進などに活かし、効率化や業績向上につながります。
受発注ソフト、ECソフト、クラウドサービス導入の初期費用、PCやタブレット、レジ等も導入の対象になるので、生産と受発注の連動、販売管理と顧客管理などで社内にシステム導入したい方は検討して良いかと思います。
補助率は2分の1〜4分の3、補助金の額も30万〜450万と幅広くなっています。
2021年の採択率は54%ですが、全体的には低くなっており、採択率が20%の公募回もあったようです。ものづくり補助金と同様に、複数の公募機会があります。
=デメリット・注意点=
・最大のデメリットは登録されているI Tツールのみが対象であること。つまり補助金の事務局が認定登録した会社(IT導入支援事業者)との取引に限定されます。
・補助金の申請にあたっては、自分の会社の事業エリアをカバーし、それらのソフトウェアツールを販売している会社(IT導入支援事業者)を決定、その会社にサポートを受けながら申請するため、“補助金ありきの価格設定”となりやすいことから、想定以上に自社の持ち出しが増えるケースがあります。
・I TやDX導入にあたっては、それらを社内で運用させることも考えなければなりません。せっかく導入したのに、現場が使えないなどのことがあれば、補助金を活用して買ったとしても無駄な投資になる可能性もあります。
I T導入補助金サイトはこちら
3.先進的省エネルギー投資促進補助金
工場や店舗、事務所などの既存設備を省エネ設備に更新する際に、設備費用の一部を補助する補助金です。以前は省エネ補助金とも言われていましたが、令和3年度より新しい事業として再スタートしており、令和4年度も募集があります。
エアコンなどの空調、冷蔵冷凍庫、冷蔵ケース(オープン冷ケースも対象)、給湯器やボイラーなどが対象となっており、菓子企業でも使える設備は意外と多い知る人ぞ知る補助金。
近年、コスト増の中には電気代上昇の影響も大きく、契約電力会社によっては1年で20%近い値上げが進んでいるため、コスト減(維持)のために、これらの取り組みも今後考えていく経営者の方も増えています。エアコンなどの空調を専門に扱う会社の社長に伺うと、10年前と最新の設備を比較すると、電力消費量が20%〜30%近く改善されているため、省エネ効果が大きいとのこと。
加えて昨年から設備の導入に対しては、補助率ではなく定額補助(設備の容量・大きさごとに設定)となったため、設備を安く提供してくれる業者さんとお付き合いがある場合はより補助率の高い補助金となります。(見積もり額の半分よりも多い補助金はもらえません)
また、この補助金は同一法人でも事業所が違う場合は複数回活用できることが大きなメリットです。自社の財務状況や各店舗・工場の状況に応じて申請が可能です。残り約9年は続く計画の補助金なので、複数店舗を持っている企業では「今年は本店、来年はB店とC店、再来年は工場」のように、拠点別に分けて数年間の計画的な活用も検討すると良いですね。
全体的な採択率は60%前後ですが、私どもがお手伝いした案件は全て採択されています(採択率100%)。傾向としてはちゃんと申請書・書類が作成でき、事務局の要請(各種修正等)に対して適切に対応できる事務能力があれば、採択率は上がると考えています。
=デメリット・注意点=
・大きなデメリットは年度内の公募機会が1回から2回と少ないこと。毎年5月〜6月末にかけての公募がほとんどで、時々年度末に補正予算による公募がある程度のため、公募を逃すと1年先の公募を狙うことになり、前もって計画的に申請や準備をする必要があります。
・この補助金は“既存設備の更新”が前提のため、新たに増設・新設する設備は対象になりません。故障して止まっている設備の更新も対象外、それらの設備導入にかかる工事なども対象外です。
先進的省エネルギー投資促進補助金はこちら
4.小規模事業者持続化補助金
従業員数が5名以下(製造業の場合は20名以下・・・製造されているケースが多いので、ほとんどはこちらかと思います)の場合に限定された、小規模事業者や家族経営、個人事業主向けの補助金です。
売上アップ・販路拡大のための店内設備や製造設備の新規導入、チラシやカタログや看板などの販促物作成やDM発送、ホームページの作成、新商品のパッケージ開発(デザイン等)等々に活用できます。
申請に必要な事業計画書はシンプルで、社内でも作成準備できる場合も多いですが、商工会議所と連動した申請プロセスがあるので注意してください。(活用を検討されている方は、まず地元の商工会議所へ連絡してみてください)
補助率は3分の2と高くなっています。補助額の上限は50万〜200万と条件によって異なります。年に複数回の公募があるので、自分達の都合や時期を考えて計画的に使うことができます。
売上を上げる、新規客の獲得、新商品開発など、企業規模に関係なく取り組んでいかなければならないテーマを目的とした補助金なので、条件が合うのであれば新しいチャレンジへの起爆剤として活用し、事業の新たな成長ステップにもつなげていくことができます。
うちの会社は小さいから、大きな投資はできない。難しい事業計画書は作れないと場合に、まずは少しの補助があれば助かるというケースであれば、検討して良い補助金と思います。
=デメリット・注意点=
・小規模事業者を対象とした補助金なので、補助額の上限は低いです。
・地元の商工会議所と連携して申請する補助金なのですが、時々相談されるのは、地元の商工会議所がこういった補助金のサポートについて積極的に支援してくれないことや、担当者が知識不足・経験不足といったことです。
・公募の回を重ねるごとに制度や条件の変更も行われていますので、ご自身が申請するタイミングで、公募要項をちゃんと確認して、本当に使えるか、使いたい内容が含まれているかどうかを判断する必要があります。
小規模事業者補助金はこちら
https://r3.jizokukahojokin.info
5.中小企業事業再構築補助金
コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や、緊急事態宣言やまん延防止措置によって売上が減少した中小会社が、思い切った新しい分野への展開や、業態変換、業種変換などの取り組みを行なって事業規模の拡大を目指すことを支援する補助金が事業再構築補助金です。
(単なるリニューアルや、既存業態の新規出店等には使えませんので、どういったリニューアルであれば使えるかはご相談ください)
菓子業で言えば、菓子以外の新しい商品分野・領域への展開や、販売形態を店舗型から宅配型への転換、小売店だけではなく飲食店も展開するなどの取り組みなどが多いです。
最大の特徴は店舗や施設の建築・改修工事が補助対象になっていること。中小企業向けの補助金として建物関係が補助対象になっているケースは少ないので、この事業再構築補助金に注目している会社は多いです。建物の他にも設備装置やシステム、外注費(デザインや設計)、広告宣伝・販促費など幅広く補助対象となっています。
実際に菓子業で、一部の既存店舗を改修して小売店から飲食・カフェ業態に転換するケースや、工場の一部を改修・増築して菓子以外の新しい商品を開発・製造するケース、菓子に加え地域の農産物を扱う産直業態を展開するケース、新たに宅配事業へ参入するなど、自社の強みや地域課題と連携した取り組みで採択される案件があります。
補助率は3分の2と高く、補助額の上限も従業員数に合わせて2,000〜8,000万と高額です。今後、人口減少が続く日本において今までのマーケットだけを対象にしていて良いのかという相談も増えていますし、今後の高齢化を見据えて店舗の集客力や企業の収益力を高めるために新たなマーケットの獲得や、新しい販売方法への参入を目指す戦略が重要になってきています。
事業再構築補助金と自分達の強みを活かして、菓子専業からヨーグルトやチーズ、ジェラート(菓子需要の落ちる夏場への対策としても効果的)などの乳製品の製造販売へ展開(新分野展開)、一般顧客から企業向けの原材料販売へと販路拡大、宅配事業の展開など、会社にとっても大きな変革・転換点となる大きなチャレンジに取り組むことで、自社や地域の課題を踏まえ、次の時代を見据えた新たな将来ビジョンを具体化していくことができます。
新型コロナウイルスの影響によって生まれた大きな補助金だけに、どの程度の年数継続されるかは不明ですが、少なくとも令和4年度の期間中に3回〜4回程度の公募が発表されています。(ただし公募内容は変更される場合があります)
また一度公募で採択されなかったとしても再チャレンジができますし、どうして採択されなかったのかという理由も聞くことができるので、活用を検討されているのであれば早めに動くことをオススメしています。
=デメリット・注意点=
・当社でもご支援をさせていただき当社案件は採択率100%ですが、とにかく採択に向けて難易度の高い補助金です。採択率が30%〜40%台と低いこともありますが、申請に必要な事業計画書(10ページ、もしくは15ページ)で求められている内容が高く、アイデアはもちろん、綿密な計画づくりや各項目の検討、数値の落とし込みや根拠の説明なども必要です。資料作成の技量も求められます。ものづくり補助金よりも内容的には難しいというのが業界の共通認識です。
・申請する前の準備が必要です。前述した内容に加え、事業再構築補助金で定められている事業期間は採択から14ヶ月以内、交付申請から12ヶ月以内とほぼ1年間で全ての事業を終えなくてはいけません。例えば新しい業態を考え、土地や物件を決め、設計やデザインを検討・確定し、見積もりを精査して、建物を建てて営業までということが1年で全てできるかどうか。実際には相当タイトなスケジュールです。採択にあたっては事業の実現可能性も見られています。内容の実現だけではなく、事業期間中に完了できるかもポイントになっていると考えています。
・少なくても申請する時点で、事業を行う物件や土地は決まっていることが前提(自社物件であれば問題ないです)になります。計画も補助金の採択を待ってから具体的に開始しても間に合うかどうかはかなり難しい。また事業に係る費用も専門業者による概算見積もり程度は準備しておいた方がよいとお伝えしています。建築コストの高騰などによって、補助金が採択された後に増額しようとしてもできないからです。自己資金でカバーすると言っても持ち出しが高額となるので、申請する時点である程度現実的な見積もりを準備することをオススメしています。
・ものづくり補助金同様、申請から採択後までの事務作業の負担も多いことも大変。金額的にはそれなりの額が補助金として出ますが、基本的には補助金は後払いなので、補助金支払いまでのキャッシュについても確保しておく必要があります。補助額の上限が高いだけに投資も高額となります。一時的に自社で全ての費用を払うことになるので、金融機関との融資等に関する調整も必要です。
・単なるリニューアルや、既存業態の新規出店には対象外となります。今とは違う新しい取り組みに対する補助金なので注意してください。(少しややこしいです)
事業再構築補助金はコチラ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp
6.最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業(業務改善助成金)
この助成金は厚生労働省のもので、賃金の引き上げ(事業場内の最低賃金引き上げ)を前提として、生産性向上のための設備投資やコンサルティング導入を支援するものです。
引き上げる最低賃金と従業員数によって、30万〜600万円の助成を受けることができます。助成率は4分の3、5分の4、10分の9と条件によって異なりますが、どれでもかなり高い補助を受けることができます。
製菓製パン業で事例を見ていくと、原料充填機、カッター、パン発酵機、包装機、冷凍冷蔵庫、POSレジシステムなど日々の作業に関わる設備の多くが対象となっています。
これらを活用して生産性を向上させていくことで、少ない人員でも今以上の収益を獲得することができれば、給与アップだけではなく、会社の収益化にもつながってきますし、今後の人員不足(働き手不足)で悩んでいる地方の企業にとっても、課題の軽減が見えてきます。
賃金を上げることが前提なので、人件費の固定費が増えることはありますが、それ以上の効果を考えることができれば、メリットがあります。
地域別最低賃金は毎年上昇しており、今後も上がっていくことが想定されますので、将来を見据えれば賃上げをしなくてはならない時期が来ることは確実です。
それを見越して、チャレンジしていくことも視野に入りますね。
公募締め切りというのはなく、随時申請ができるようですが、予算がなくなれば終了ということになるとのこと。(都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)まで問い合わせてみてください)
申請書自体もそれほど難易度は高くありません。
=デメリット・注意点=
・なんと言っても賃金アップが前提ということ。賞与などではなく、時給アップが前提なので固定費が上がります。原材料やコストが上昇し企業利益が減少している中で固定費が上がるのは経営にとって大きな不安要素になりますね。
・申請期限はないものの、予算がなくなれば終了とのこと。
業務改善助成金はコチラ
7.補助金や助成金の活用でよくある質問について
補助金や助成金のご質問や相談で多いのは、自分達の会社や、取り組みたい内容が補助金や助成金の対象になるかどうかです。どうしても対象となる条件が複数あり、分厚い公募要項を読んでもよくわからないという方からのお問合せです。
次に増えているのは、一度自分たちで申請したけど採択されなかったというケース。どこが悪かったのか、何が足りなかったのかを知りたいという方です。銀行や信用金庫などの金融機関や、会計事務所などに手伝ってもらったのに、採択されなかったというケースも少なくありません。
もちろん案件ごとに課題や改善点は違うのですが、全体的にみると計画内容の落とし込みや具体性や数字根拠が乏しかったり、公募要項で求められている必要な項目を網羅できていないことにあると感じています。
あとはやはりということでしょうか。“補助金ありき”の事業というのは難しいように思います。以前にある会社の社長さんが話されていましたが、「補助金のために仕事をしているんじゃない」ということ。補助金を採ることが目的ではなく、自分たちがやりたいことが主で、補助金はあくまでも補助ということと思います。
補助金を採るために、補助金に合わせた事業計画を作るのではなく、自分たちのやりたいことに合わせて補助金を上手に組み合わせていくこと。
その結果として“使える補助金”を獲得することができます。補助金の採択を受けたあと、実際に事業を始めてみたら“使えない補助金”だったということが往々にして起こっています。
この点は、補助金申請をサポートする会社や専門家とちゃんとすり合わせをすることをオススメしています。極端に言えば、補助金専門の会社や専門家はより高額の補助金が採択されて、より多くの報酬が入ることが主になりがちなので、“補助金をより多く採るための事業計画”を作ろうとします。そうではなくて、自社にとって“本当に必要で、使える補助金を採る”ことを考えてくれる方と一緒にやることが良いと考えています。
補助金は上手に活用するもの。補助金に振り回されてはいけない。
補助金を上手に活用して、自分たちが目指す未来や取り組みのチャレンジを後押ししてもらうことです。
補助金申請に向けて、具体的な方法のアドバイスを行なっております。急なご相談についても、できる限り対応いたします。あなたの会社の強みを生かし、将来をどのようにするかを共に考えていきましょう。
一方的に提案することはありません。お互いに理解を共有して前に進みます。
時代が大きく変わった今、経営や会社も大きな転換点を迎えていると考えている方もいらっしゃると思います。補助金云々の前に、自社はどうした方が良いか。自分はこう考えているけど・・・どう思うか。などまだまだやる事が見えていない方もご相談ください。共に考えていきましょう。
=PR=