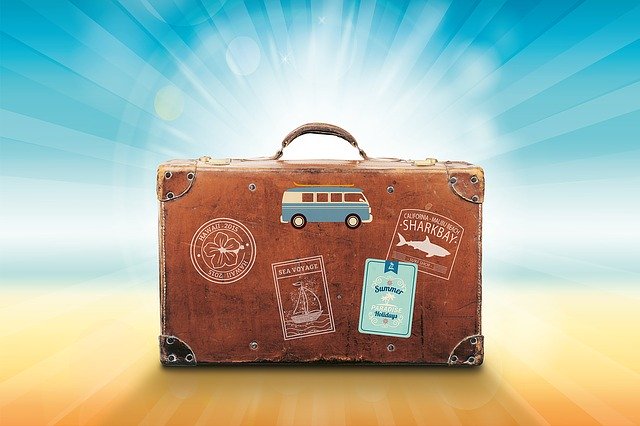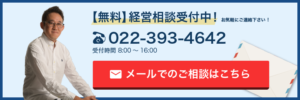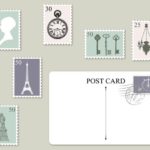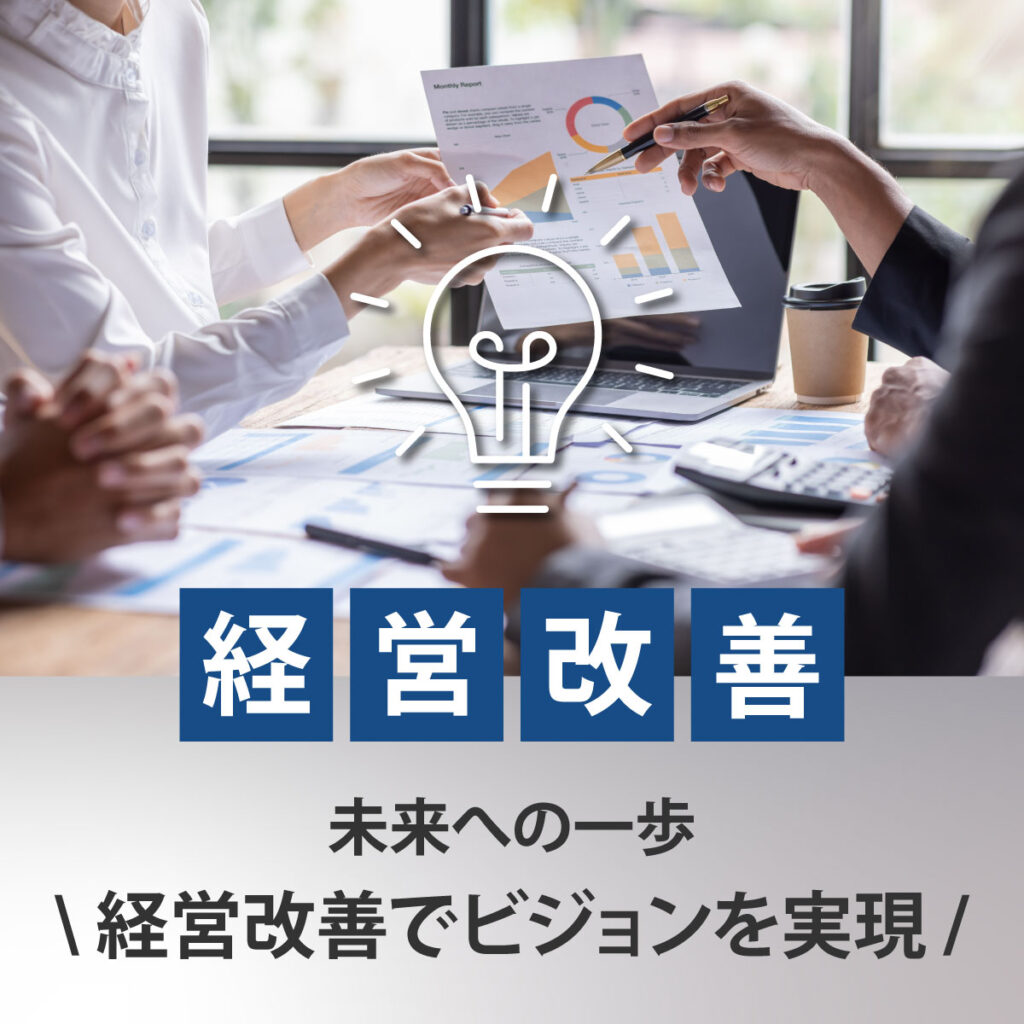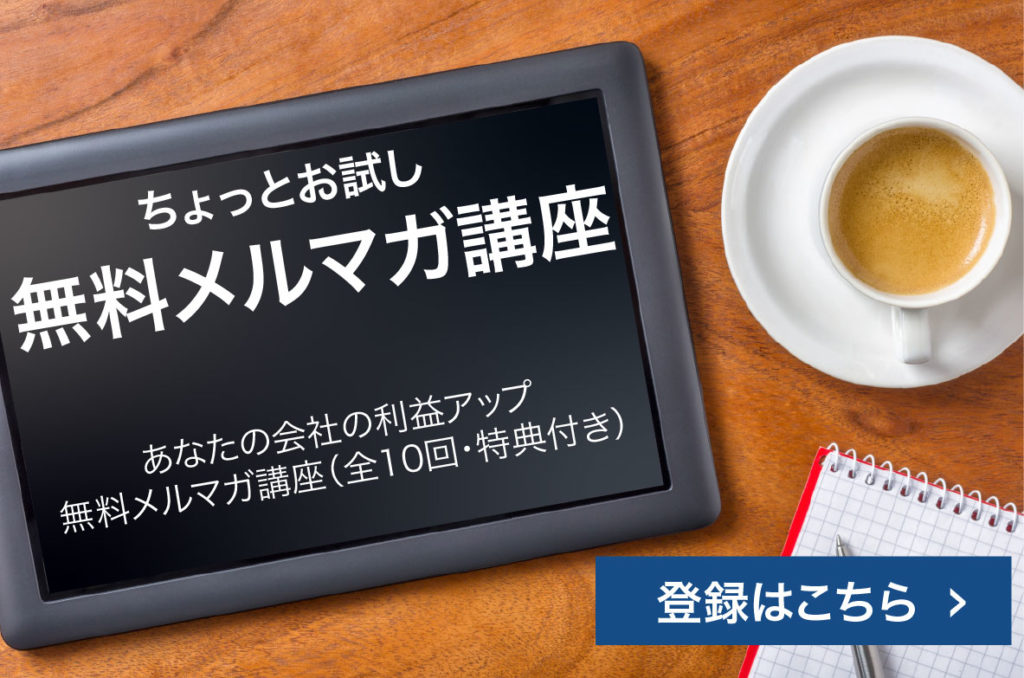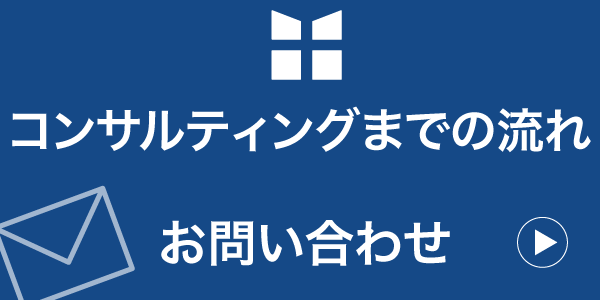中小企業の利益を3倍にする経営コンサルタント 本田信輔です。
実は今、地域密着型の菓子業にとって大きなチャンス。新しい追い風が吹こうとしています。
次なる売上・マーケット獲得への追い風は、2016年の春頃から胎動し始めているのですが、今回の新型コロナウイルスによる消費者の変化より明確に顕在化し、今後さらに強くなると確信できるレベルにまで達しています。
そのキーワードは“新しい観光マーケット””新しい観光業”
「新型コロナウイルスで観光は壊滅してるけど。こんな時に観光!?」
そう思われるかもしれません。
(政府の主導するGoTo Travelキャンペーンなどに対し、様々な賛否の意見があるのは承知していますが、どちらにしても遅かれ早かれ観光マーケットは動き出すと考えています)
とはいえ、よく考えて欲しいのは。
新型コロナウイルスへのワクチンや特効薬が開発され、コロナウイルスは完全に消滅されなくとも人々の生活に普通に入ってくる時代はそう遠くない。(捉え方としてはインフルエンザのような位置付けになる)
その一方、新型コロナウイルスによって引き起こされた様々な事象(マスコミ、SNSでの情報発信なども含め)によって、
消費者の観光スタイルやお土産に対するココロは既に変化している。
どういうことかというと、
観光地には、観光客が戻ってくる。
だけど。
どのようなものを買うか・消費するかは変わるということ。
以前に売れていたもの、道の駅やサービスエリア・土産店の売場を占めていた商品が存在感を失い、新たな商品がそのポジションを奪うことを意味します。
そこに地元密着型菓子店の新たな追い風が吹く。
“新観光”マーケットを獲得するチャンスがあります。
ポイントを挙げるとすれば、以下の3つにまとめられます。
①新しい食品表示法と新型コロナウイルスがレール菓子にトドメを刺したこと
②新しい観光マーケットにおいて、地方の菓子店・食品店が有利に立てること
③単品を日本一レベルに育てることが、これからとても重要になること
新観光マーケットが取れれば、新たな売上と利益を生み出すことができます。
あなたはそのチャンスを狙う準備、進めていますか?
目次
1.新しい食品表示法の移行期間終了と新型コロナウイルスがレール菓子に“トドメ”を刺した。
2015年にJAS法と食品衛生法が統合されて、新しい食品表示法が施工されました。
さらに2016年4月には製造所固有記号制度が加わり、一定の条件を除いて(同一商品を2箇所以上の製造所で製造する場合を除く)は製造所の表記をすることが義務付けられ。
これにより、お客さんは“このお菓子がどこで作られたのか”わかるようになりました。
この法律の更新期限は2020年3月末。
つまり。
2020年4月からは、
「仙台土産だと思って買ったら、作っているところは新潟だった」
「博多でお土産を買おうと思って土産店を見たら、名前を聞いたことがない北陸地方や愛知県の会社で製造されたお菓子ばかりだったので、買うのをやめた」
「温泉で買ったお土産をよく見たら、製造されたのは自分の住んでいる県だった」
などのケースが続発することになります。
その影響をモロに受ける商品が“レール菓子”や専業企業が製造した“OEM商品”
商品自体が似ている(パッケージを変えただけ、焼印が変わっただけ、中身の餡を変えただけの饅頭やクリームを変えただけのお菓子なども入る)。日持ちがする。
値段が安い。バラマキのお土産に丁度良いなど。
旧来の観光では強みを発揮し、土産店やサービスエリア、駅や空港、道の駅、旅館やホテル売店など。観光の売場で大きな面積を占めていましたが、今では商品や売場が縮小され、バイヤーの求める商品も変わりつつあります。
そこに今回の新型コロナウイルスによる影響。
観光のスタイルは変わり、日帰り観光・近距離観光(県内・隣県観光、国内、宿泊数が少ない、車を使った距離に行ける観光など)が中心に。
さらに経済不況が重なり、お土産として買う商品には3つの傾向が出てきます。
①日持ちするお菓子はいらない(すぐに帰るから。ご近所や職場へバラまくお土産は買わないから)
②美味しいお菓子が欲しい(自分たちが美味しく食べたいものを買うから)
③その地域でしか食べられないもの、売っていないものが買いたい(土産を少なくし、その場で食べるテイクアウトなどの需要割合が増える)
今まで観光土産の中心だったレール菓子・専業企業の作るOEM商品は、新しい食品表示法と新型コロナウイルスにトドメを刺されています。
新型コロナウイルスが人々の日常に馴染み、ワクチンや特効薬ができるようになった時には観光業界の勢力図は大きく塗り替わっている。
間違いなく言えるのは、そこに地元密着型菓子店・菓子業の“新観光マーケット”に参入する追い風が吹くということ。絶好の機会がまもなく訪れるということです。
仮説として想定しているタイミングは来年1月頃。早くなること・遅くなることも考えられますが、チャンスが来た時に動いては遅い。これだけはわかっています。
「地元の菓子業が対策を打つことで、新たなマーケットを獲得できるチャンスは今から始まっている」
を考えておいて欲しいと思います。
2.新しい観光マーケットを狙う商品開発のポイントは。
日本全国、各地には強い観光銘菓、名物単品と呼ばれる商品があります。
北海道の白い恋人や開拓おかき、広島のもみじまんじゅう、伊勢の赤福、博多の博多通りもん、福島郡山の薄皮まんじゅう、京都の八つ橋などなど。
「◯◯(地域名) 名物 お菓子」
でインターネット検索すると、トップに出てくるようなお菓子です。
菓子業の経営者で、地域を代表するお菓子を作りたい。地域の名物と言われるようなご当地銘菓を作りたいと思っている方々は多くいらっしゃると思います。
この他にも、地域の菓子業で地元銘菓を作り上げている企業はありますが、これらの商品づくりにはポイントがあります。
今後、観光マーケットで売れる商品としてお伝えしている商品開発のポイントは、
①地元素材・産品か文化を取り入れた商品(最低限、素材もしくは文化のどちらかが入っている)
地元の素材を原材料として使用していること、できれば地域を代表するような素材が良いが、穴場的な素材でも良い。比較的、菓子に相性の良い畜産品・フルーツ、農産品のほか、海の素材等も発想によっては商品化可能です。
素材でなくても地元の食・菓子文化を取り入れた商品でも可能(例えば、宮城県のずんだ餅の原料となる枝豆はほとんどが県外・海外産)、文化を上手に取り入れ新しい商品を作る切り口も候補に入れた商品を考えてみる。
観光で買われる商品は必ずと言って良いほど、素材もしくは文化、どちらかの要素が入っています。この辺りは地元密着型の商品づくりと大きく違うところです。
②その地に行かなければ味わえない(食べられない)商品、買えない商品
理想を言えば商品の販売だけではなく、出来立て商品・作りたて商品の販売もできる商品。
直営店だけではなく、地域の観光土産店・道の駅・サービスエリア、旅館などでの展開も考える場合は、半製品で供給ができるようにする(焼く・揚げる・蒸すなどの一次調理で、飲食・テイクアウト部門で出来立てを提供することができる)
完成品だけを売るのではなく、簡易パッケージの半製品で供給でき“その地でしか食べられない”を取り込める商品であれば、さらに良いですし、将来的には単品型業態開発なども視野に入ってきます。
新観光マーケットを狙う新商品は、できる限りギフト(土産)、デイリー(出来立て、自家消費)の両方で展開できるように考えます。
③日持ちはしなくて良いから、本当に美味しいものを。
今までの観光菓子は日持ちによって品質が左右されていました。
地元ではなく遠方で作るから、輸送や店舗での保管・在庫を考えて日持ちを長く。
遠方から来るお客さんや、会社等でバラまきに対応するために日持ちを長く。
少し不味くなっても、日持ちが優先された。
今後は日持ちについての制約が外れると考えます。
地元で作り、すぐに店頭(地元の観光店舗なども)に並ぶから在庫も少なく、日持ちが短くて良い。
近距離観光が増えたり、バラまきに対応しなくて良いから日持ちは短くて良い。
そのかわり、本当に美味しいものを。
出来立てを食べることができる、持ち帰りであっても日持ちは1〜2日、1週間もあれば十分。
車で来るからパッケージの形状やチルド・冷凍(保冷バッグ等)の融通もきく。
大福や蒸し饅頭などの朝生商品、プリンやシュークリーム、ロールケーキなどの洋生商品なども視野に入れることができますし、既存の焼き菓子なども出来立てを組み入れることで新たな商品展開が可能になったということ。
今までの観光菓子に対する概念が大きく変わったことで、地元密着型の菓子業・菓子店にとってより強みを発揮できる流れがきています。
④土産マーケットおける売れ筋価格は変わらないが、入り個数は変わる。
観光用のお土産は1箱500円・1000円が主流です。多少の前後はありますが、原則変わりません。理由は贈り物・お土産はあげる相手がいるから。
あまりに安くなったり、高くなったりすると相手に失礼だと思ったり、恐縮させると考えるからです。
職場やご近所へのバラマキ型土産が減るといっても、お土産のマーケットはゼロにはなりません。家族や親しい人へのお土産は残ります。
一方で変わるのは箱に入っているお菓子の入り個数。バラマキ型のお菓子にありがちな、品質がイマイチでも安いお菓子が小包装でたくさん入っている。
これは変わります。職場など多くの人にバラまく必要がないからです。
家族や親しい人へのお土産であれば、美味しいものを少量・数で良い。
何が言いたいかというと。箱の値段は変わらないが、お菓子1個あたりの単価は上がって良いということ。
今まで10個入って500円(1個あたり50円)や10個1000円(1個あたり100円)が必要だったのに、
これからは3個で500円(1個あたり約165円)や5個入り1000円(1個あたり200円)で良いということになります。
今までの感覚に残っている、“無理して安いものをたくさん入れる”必要は無くなります。
原材料も自分たちが良いと思ったものを使い。自分たちの強みである技術力をさらに発揮し、もちろん美味しいお菓子を。ちゃんと利益が取れる価格で販売する。このことを前提として商品を考えていくことができます。
⑤利益を取れなければ意味がない。直売販売のほかも視野に入れて考える価格設定
地元密着型の菓子店であれば、当然最初の販路は自分のお店・直営店を考えます。
ですが、観光マーケットの場合。観光客が集まるところ(観光拠点・サービスエリア、道の駅、ホテルや旅館の売店、地元の物産館など)への商品展開も考えておく必要があります。
そうなると抑えておきたいのは掛け率等の問題。
クライアントへは最低でも掛け率80%、理想を言えば掛け率70%〜60%でもちゃんと利益が取れるように価格設定を提案しています。
例えば。行政・地域公社など運営する道の駅・観光施設等であれば掛け率80%程度が目安。
駅や空港、観光土産店、旅館やホテルなどの売店など民間施設や業者であれば掛け率60%程度のところがあります。
さらにいうと。経営判断として掛け率60%以下になるところへは展開しないと決める。
これが利益を獲得するためのルールです。
直売価格で考えるのではなく、卸を想定した価格で考えておく。
もちろん製造における既存機械の活用、効率性・製造個数能力なども大事になってきますが、合わせて大事なのは価格設定。今までの商品よりも利益性を高めに設定しておくことが必要。
これからさらに世の中の経済は厳しくなり、企業経営にとって利益が大事になりますので、ちゃんと考えておきたいところです。
3.観光における最大の販促方針は“名物単品”にすること。単品を日本レベルまで高めるための取り組みを進めよう!
観光マーケットを狙おうとしたとき、抑えるべき成功ポイントは以下の3つです。
①観光は単品で認知度が決まる。
今、全国で売れているご当地の銘菓。これには一つ特徴があって、
・白い恋人(石屋製菓)
・開拓おかき(北菓楼)
・もみじまんじゅう(にしき堂)
・博多通りもん(明月堂)
・薄皮まんじゅう(柏屋)
・京都の八つ橋(本家西尾八つ橋)
その他にも、
・萩の月(菓匠三全)
・東京ばなな(グレープストーン)
・かもめのたまご(さいとう製菓)
・うなぎパイ(春華堂)
これら地元の銘菓と呼ばれるお菓子の特徴は、商品名は知られているが、それを製造・販売している企業名は商品名ほど知られていないということ。→商品自体の知名度は高いが、企業の知名度はそこまでではない。
菓子業界に関わる人であれば当たり前のような知識ですが、お客さんにとってはそんなものです。
このことを地元密着型の菓子店は理解しておく必要があります。
地元であれば店舗名・企業名で買ってくれる。
一方、観光の場合はどんな地元の有名店であっても地域の名物単品を作れなければ、育てられなければ観光マーケットは取れないということ。
観光で売れる商品のポイントを押さえ、単品として育てる取り組みを行う。
今までの商品をそのまま観光用として展開してもマーケットは獲得できません。
新商品開発でも、既存商品のリニューアルでもアイテムを広げるのではなく単品に集中することが大事になります。
どのようなお菓子を作るのかに加え、商品名なども観光用に考える必要があります。
②全国レベルに単品の知名度を狙う取り組みを!
これからの観光は団体から個人へ大幅にシフトします。団体観光はほとんどなくなるでしょう。
そうなると重要になるのは、個人向けのWebサイドやSNSを活用した認知度アップの取り組み。
団体であればバスガイドさんの情報などが効果を発揮しましたが、これからの観光客は自分のスマホを使って情報収集してきます。
・「◯◯(地域) 名物 お菓子」で検索されたとき、ちゃんと紹介できるWebサイトがあるか。
・「◯◯◯(商品名)」や、その地域の観光で検索されるワード(例えば史跡・観光拠点、他の名物)でもWebページが引っかかるようにSEO対策をしているか。
・twitterやInstagramなど、拡散型で旬のSNSによる定期発信を行なっているか。
などが観光客に選ばれるための不可欠要素になります。
そして。
同じくらい大事なのは自分たち、スタッフがこの商品を地元と銘菓として育てていくための自信を持つことができるか。社内での意識づくりも大事に。
狙うのは日本一の単品。地元客と違い、全国がターゲットだからです。
ここでしか食べられない、買えないをさらに強化し、単品知名度を高めるためのキーワードです。
これから地元密着型の菓子業にとって大きな大きな追い風が吹く。
最初にお伝えした通り、チャンスの神様は今から準備しておかなければ掴むことはできません。そのチャンスを掴まなければ、他の菓子業が入ってくるか、その地域の観光や菓子業自体が衰退する結果になる。
今までの観光マーケットを忌避している方もいるかと思います。
価格の安さ、品質が悪くてもイメージだけで売れる。うちの商品をそのレベルと同じ扱いにして欲しくない。
そんな時代は終わりを迎えました。あなたの認識も変えていく必要があるかもしれません。
間違いなく、これからの観光客は。
地元のお菓子屋さんが作った、美味しいお菓子を、食べたい・買いたいと思って観光に訪れます。そこに新しい売上が生まれる。
この話をすると、多くの人は理解してくれます。
ですが結局。多くの経営者はいつ収束するかわからない新型コロナウイルスの影響に対して「いつ収束するかわからないから」「これは長期戦になる」と、
人の心理や、世の中の流れ、観光の流れ、ウイルスへの対策が短い周期で変わることへの対策や意識が抜けてしまう。まだ間に合うと思うのか、他が動きはじめたらと思ってしまう。
今日の、なんとなくの不安を理由に
明日の売上のチャンスを捨ててるわけです。
私どものクライアントは着実に準備を始めています。
未来のために時間、お金、資源、人材をどこに投資していますか。
あなたは、何の準備をはじめていますか?
=追伸=
すでに成果を上げている地元洋菓子業のクライアントも増えています。
コロナウイルスによって観光業の新しい流れは顕著になり、アフターコロナ・withコロナに移行しつつあるマスコミ、SNS等での注目も獲得しやすいですよ!
=PR=