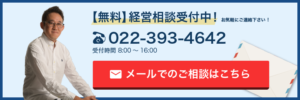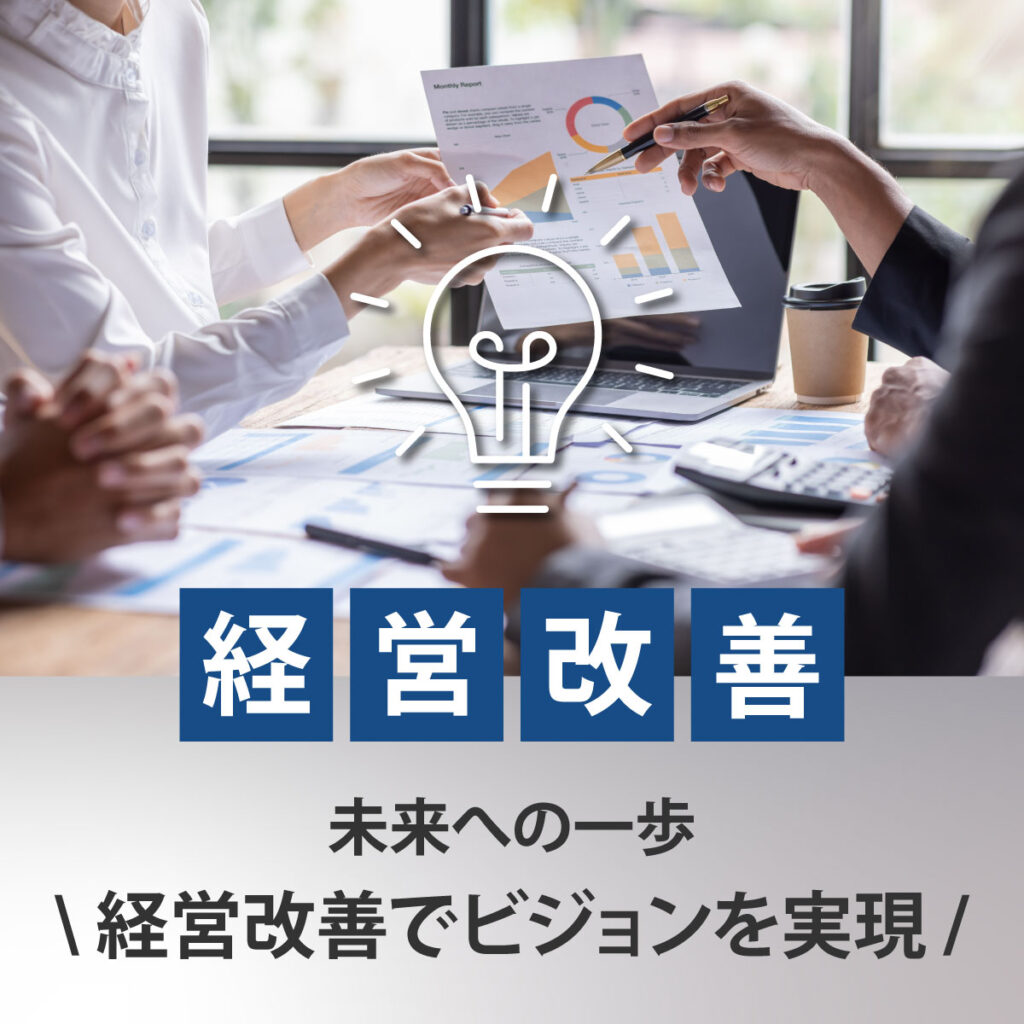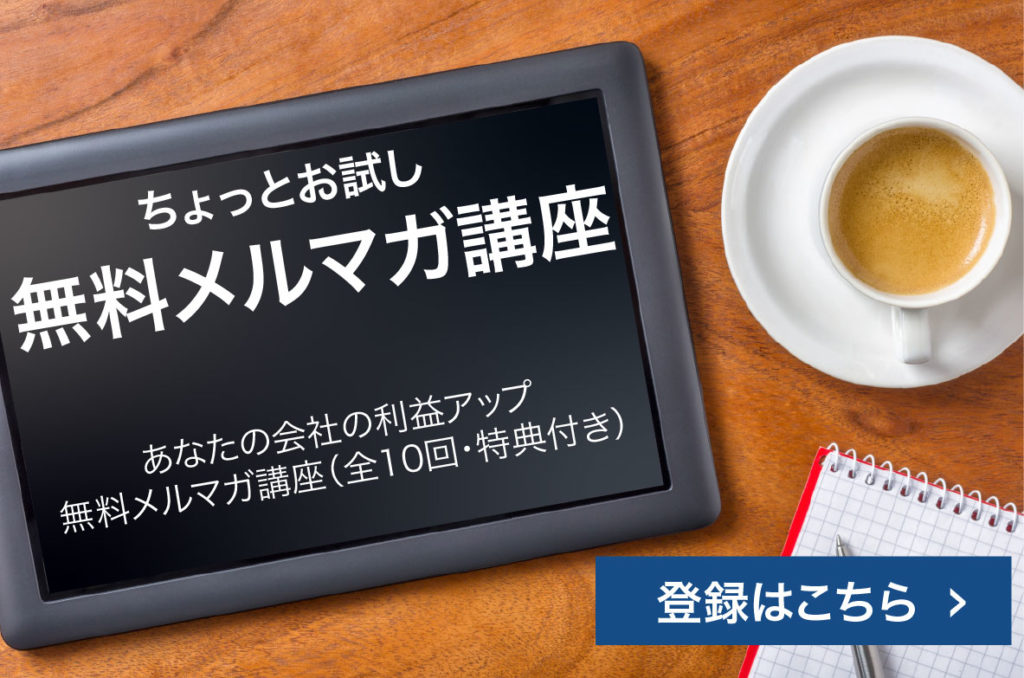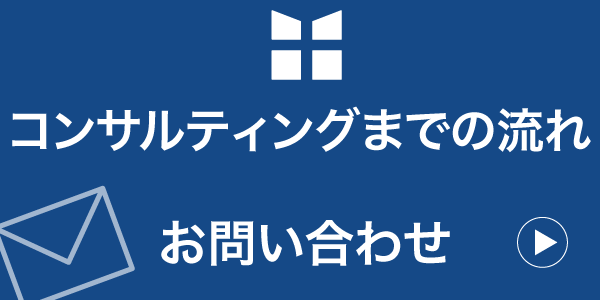中小企業の利益を3倍にする経営コンサルタント 本田信輔です。
今回のお悩みテーマは
「繁盛店が利益を出す経営改善」
言い方を変えると、
「繁盛店なのに、ある程度売上はあるのに利益が出ない(少ない)」です。
コンサルタントとして全国の洋菓子店・和菓子店などの経営相談を受けてきていますが、ここ数年、特に多くなってきたなと感じるテーマの一つ。
クライアントのオーナーさんから「知り合いなんだけど、そっちのお店も相談にのってあげてよ」と紹介されることも増えています。
地域一番店あるいは二番店。その地域の中でも注目されるお店の一角。
行列もできるし、客数も他店に比べると多い。
売上も1店舗で8000万円超え、1店舗で年商1億〜3億円と業界内でも明らかに繁盛店と言われる店舗オーナーさんの相談も少なくありません。
もともと菓子業は他業種と比較して収益性が高く、日銭も入る商いとして、資金繰りや財務体質が良いと言われてきた業種の一つ。
とはいえ、周りの人がイメージしているほど利益を出せていない企業や店舗が多いのも事実です。
「まだまだ売上もあるし、資金繰りにもあまり困らなかった」経験をしているオーナーや経営者にしてみれば、
利益を改善するために「社内で少し強めのコスト削減を行えばなんとかなる」「現場の効率化ができれば利益は出る」「現場を見てもらって、効率化できるところをアドバイスして欲しい」
そう考える方もいらっしゃるのですが、ほとんどのケース、原因はそこではありませんとお伝えしています。
ポイントは違うところにあるのですが、そこにオーナーや経営者が気付くかどうか。
実際。経営相談を通じて、その本質的原因とポイントをご理解いただいた上で、経営改善のご支援をさせて頂いた菓子店は、2ヶ月〜3ヶ月で利益アップの成果が出てくるというのが多数。しかも利益率で5%〜10%近い改善を実現しています。
今回は、繁盛店で利益を出す経営改善法。頑張った分、ちゃんと儲けを出す方法をお伝えします。
目次
1.利益を出す方向性はとてもシンプルです。
色々と利益を上げる方法はありますが、
当たり前に言われる基本は
・売上を上げる
・粗利率を上げる(原価率を低減する)
・経費を下げる
この3つです。
ミタス・パートナーズではこの3つ少し変化させ、
・売上の“質”を上げる
・粗利率を上げる(原価率を低減する)
・経費を“適正化”する
としています。
最初に書いた当たり前と言われる3つの基本(売上を上げる、粗利率を上げる、経費を下げる)に照らし合わせると、繁盛店なのに利益が出ない落とし穴が見えてきます。
繁盛店を当たり前の3つに照らし合わせて考えれば、
・売上はある。
・粗利率が上がりやすい(仕入れが多くなるので原価率が下がりやすい)
・経費率は下がりやすい(大量に作る、売れるので作業効率が上がりやすい)
があるので、周囲から見ても繁盛店は儲かっているように見えるのです。
実際に繁盛店のオーナーも陥りやすいポイント。
では、ミタス・パートナーズなりの基本で“繁盛店なのに利益が出ない・上がらない”原因をお伝えします。
2.繁盛店なのに利益が出ない原因は?ミタス・パートナーズ的なみかた。
ミタス・パートナーズなりの3つの見方は先ほど書いた通り。
①売上の“質”を上げる
②粗利率を上げる(原価率を低減する)
③経費を“適正化”する
この3つで見てみると、
(1)売上の質はどうか?
どんなに売上が大きくても、その売上の質・中身が良くなければ利益は出ません。
売上がどのように構成されているかを見ます。
売上と同じくらい、売上構成比が大事です。
簡単にいえば、
A:1の商品で1億円の売上を作る。
B:100の商品で1億円の売上を作る。
どちらが、売上の質が良いか、誰でもわかります。
さらに洋菓子店で多く見受けられるケースは、利益を出せると言われている焼き菓子・ギフトにも現れます。
・どれくらいの種類の焼き菓子が作っているか。
・詰め合わせ中心のギフトばかりになっていないか?(単品のギフトはあるか)
・焼き菓子の主力商品は育成されているか? 等々
これらは製造現場の効率だけではなく、販売現場の効率にも影響を与えます。
そもそも利益を出せる商品構成ではない。ギフトの作り方ではない。ということです。
(2)粗利率は上がるか?・・・原価率は下がるか?
繁盛店で利益が出ないケースの多くは粗利率が低い。
売上や客数・商品の販売個数が多いので、粗利率が多少低くても利益は出てくる。
つまり・・・薄利多売で利益を出しているケースです。
こういう店舗のオーナーに多いのは、
「うちは現場が効率化できれば、利益は上がる」
「現場の効率・生産性が悪いから、利益が出ない」
と原価率を抑えるのではなく、経費を下げることを考えていること。
特に洋菓子店や中小企業の場合、オーナーや経営者が現場に精通しているため、現場のムダに気づくし、利益アップ・生産性向上の面で見ても、人の作業効率の改善(つまり、手のスピードが早くなるか)はとても大事なのです。
確かに大事なのです。ですが残念、ほとんどのケース「それでは目に見えた改善には繋がりません」とお伝えします。
なぜなら。利益アップ・生産性向上にとって最も重要な、人の作業スピードを上げるための改善には時間がかかること、個々人の成長度合いも違うため、どれだけの成果になるか、いつ成果が出てくるかが読めないところがあるから。
頑張ったぶんの成果が上がるかと言われれば、効果を出すのに時間がかかる上、利益の上がり幅も少なくなるケースがほとんどだからです。
現場の効率化。特に作業スピードの改善には時間がかかるというのが前提。特に手作業の多い洋菓子店や中小の菓子企業にとっては、時間もかかるし、成果もなかなか見えづらいので結構大変なことになるのです。
まず最初にすることは粗利率を上げる。つまり原価率を下げる。かといって原材料の質を下げて、商品の品質自体を下げるのは致命的ですので、
私たちは“利益の取れる価格・値づけ”であるか?
粗利率から考えた“値づけ”ができているか?
を最初にチェックし、値づけから改善していきます。
思うような利益が出ない時、最大の原因になっているのはほぼ“値づけ”です。
ケーキや洋生類、生菓子、焼き菓子、ギフト。あらゆるものが対象。
最も効果が高く、優先順位が高く、改善スピードも早いのが“値づけの見直しによる粗利率の改善”なのです。
そもそも利益を得られる商品を売っていない(利益の出る価格で売っていない)ので、そこから改善していきましょうということです。
(3)経費は適正か?・・経費を適正に使っているか?
よく。うちは●●費が高いから、そこを改善できれば。。。と言われるケース。
ほとんどの場合、この●●に入るのは人件費です。
この人件費。
何をもって高いというのでしょうか?
業界平均、利益を出している同業他社・モデル企業の指標など色々ありますし、確かに目安というものはあります。
ですがそれ以上に大事なのは、人件費に見合った価値を生み出しているかどうかを見極めることが必要です。
人件費は高い。でも現場の技術力によって、高い値段で商品が売れる。
結果、粗利率は高い。
数字を挙げて見ると、以下のようなイメージ
A店:原価率25%、人件費率15%
B店:原価率15%、人件費率25%
会社や店舗にとって、どちらの場合もあります。
・原材料にこだわり、原価率が高めでも、人件費を抑えて利益化する。
・原材料は普通でも(最高品質ではなくても)、人の技術で商品の魅力を高めて利益化する。
どちらの方法でもアリです。
大事なのは人件費に見合った商品力で、その商品力に見合う価格で売れているか。
製造の力、販売の力、そして経営の力を見ることです。
まずは自分たちの会社がどちらなのか。
もしも原材料も最高のもの(材料にもお金をかける)、人の技術力も大事にしていく(従業員により多くの給与を払いたい)のであれば、経営や販売の力で高い値づけでも売れる取り組みをしていくことを目指します。
経費のことで言えば、人件費以外にも気になるのは広告宣伝・販売促進費。
押さえるポイントは2つ。
・値引き中心のイベント催事になっていないか?
イベント限定商品や特別商品を中心に催事を企画し、価値重視のイベント催事にすることで同じ経費をかけても利益化できる方法があります。
・未来への投資として広告宣伝・販売促進費を使っているか?
利益を出そうとして経費だけを削っていないか。主力商品の育成(日本一会議企画がオススメ!)や、店舗webサイトの見直し(webの世界は変化スピードが早い。ちゃんとついていけているか)などには、費用をかける必要があります。
怖いのは、全く使っていないというケース。売上に対して1%台しか経費をかけていないのであれば、大事なことをしていない場合があります。
経費を抑えることは大事です。否定しません。ですが・・・。
それ以上に大事なのは“経費が適正に使われているか?”
経費削減をする前に“本当にこの経費を抑えて良いのか?”
自店の将来戦略や強みなどを考え、
“経費を使うべきところにはちゃんと使う、価値を生み出さない経費は思い込みなく見直す“
を考えてもらいたいとお伝えしています。
繁盛店であれば、もともと売上はあります。それでも利益が出ないというのは、
そもそも利益を得られるように経費を使っていない・活かしていないということです。
3.繁盛店なのに利益が出ない責任は誰にあるか?
これは間違いなく、経営者・オーナーの責任です。
ケーキ屋さん・洋菓子店をはじめ、中小菓子店や中小企業の多くは、利益が出ない原因のほぼ全てを経営者・オーナーが決めています。
=利益を出せる商品構成作り=
・どんな種類の商品を作り、売るのか
・どの商品を主力商品に据えていくのか
・どのようなギフト構成を軸とするのか
=利益を出せる商品づくり=
・どのような値づけ値決めをするのか
=利益を出せる経費の使い方=
・人件費に対して、どのような価値を求め、育てていくのか
・どのような販売促進・広告宣伝費の使い方をするのか
・値引き中心の催事を続けるか?見直すか?
これらは全て、現場が考えたとしても最終決定権・判断は経営者・オーナーにあります。
例えばその典型は値づけ。
現場が決めた値段をオーナーは変更することができますが、
オーナーがこれと決めた値段を、現場が勝手に変更することはできません。
繁盛店なのに、利益が出ないのは経営者やオーナーの考え・判断が、利益につながらない方向に向かっているためです。
逆に言えば、現場が変わらなくても経営者やオーナーの考えが変われば、もともと売上があるだけに大きな利益化を、短期間で実現することができます。
値づけの考えを見直せば、製造現場に利益の出る商品を製造させることができます。
もともと利益の出ない商品を、無理やり現場の改善で利益が出る商品にするよりもはるかに効果的に、現場にも負担をかけないやり方です。
現場が変わる前に経営者・オーナーが変わる。とは言え、不安もたくさんあります。
そうは分かっていても、なかなか決断できない。変化が怖いのは。。。
4.それでもやっぱり不安・・・。繁盛店の経営者・オーナーならではの悩みは。
やはり一番の不安は、今までの売上・客数、そして培ってきた評判が落ちることではないでしょうか。地域の中でも注目されていることも、不安を増幅する要因です。
そんなオーナーや経営者にお伝えしているのは、
=地域でこれだけ評価されている自信を持つ=
この地域で長年経営し、これだけのお客さんが来てくれている。それは価格の安さが魅力なのか? 今のお客さんは安さだけでは選択しない。今までの取り組み、商品力の高さがちゃんと評価され売上や客数につながっているということです。
=地域の繁盛店(地域一番店クラス)が動かなければ、それに追従する同業、地域の業界全体が衰退していく=
繁盛店は当たり前ですが、それに追従する2番店以下、新たなに参入する若いオーナーのベンチマークとなる存在です。
地域一番店と呼ばれる繁盛店が商品の価格を安いままで維持してしまえば、ほかの店舗も価格を変えづらくなる。結果として、各社・各店の利益は下がり、従業員の給与も上がらなくなる。若い人材が業界に入ってこなくなる。地域の業界全体が衰退する。ことにつながるのです。
これからの消費者や地域は、地域一番店のあり方を見ています。自分たちだけが良いのではなく、同業や地域全体にとって大事な存在であるかどうか。売上が一番大きいということだけではなく、地域や業界までを考えていく店舗こそが、これからの地域一番店として認められる時代になったのです。
=そもそも薄利多売の商いは継続できるか?を考える=
これからの日本を見れば人口減が予測されています。2019年は日本全体で約50万人減っています。毎年金沢市や大分市、倉敷市クラスの町の人口がなくなっている計算です。2年経てば、100万人都市が1つなくなるほど人口減が進んでいます。
その中で今後客数を伸ばすことはできるのか?人の胃袋が大きくなって、今の2倍お菓子を食べることができるのか?合併・統合を繰り返す超大型企業と価格競争で勝てるのか?地方であれば、人口減はさらに深刻です。
その中で、今までの売上・客数の大きさに頼った利益の出し方を見直す時期になっているのです。
・今までのことをちゃんと評価し、自信につなげること。
・地域1番店、地域で注目される繁盛店として、地域の業界全体を牽引する存在になること
・人口減の中で、新たな利益を出す経営に転換していくこと。
このことが、変化できたオーナー・経営者にご理解いただくことですし、
経営相談に来られた際に、私たちからお伝えしていることです。
あなたのお店、ちゃんと利益を出せますか?
繁盛しているということは頑張っているということ。
それで利益が出ないのはオーナーも従業員も、みんな悲しい。
売上は地域の中でもトップクラス、地域の人も同業他社からも注目される存在。
内情を知らない人からは「それだけ繁盛しているなら、儲かっているでしょう」と言われ、内心「そんなことないよ!!!」と叫んでいる方。
繁盛しているからこその悩みがあると思います。
逆にオーナーや経営者の考えが変われば、元々のポテンシャルがあるだけに大きな利益化ができます。
利益化に向けて、不安の解消、具体的な取り組みのアドバイスを行なっております。
あなたのお店の強みを生かし、将来をどのようにするかは共に考えていきましょう。一方的に提案することはありません。お互いに理解を共有して前に進みます。
利益を出すことは、より良い未来への入り口だと考えます。利益があるからこそ、もっとやりたい未来を描き、理想の実現に向けてチャレンジできる。
必ず、良い未来が描けます。
=PR=