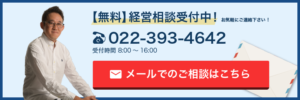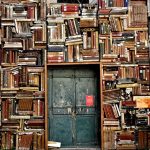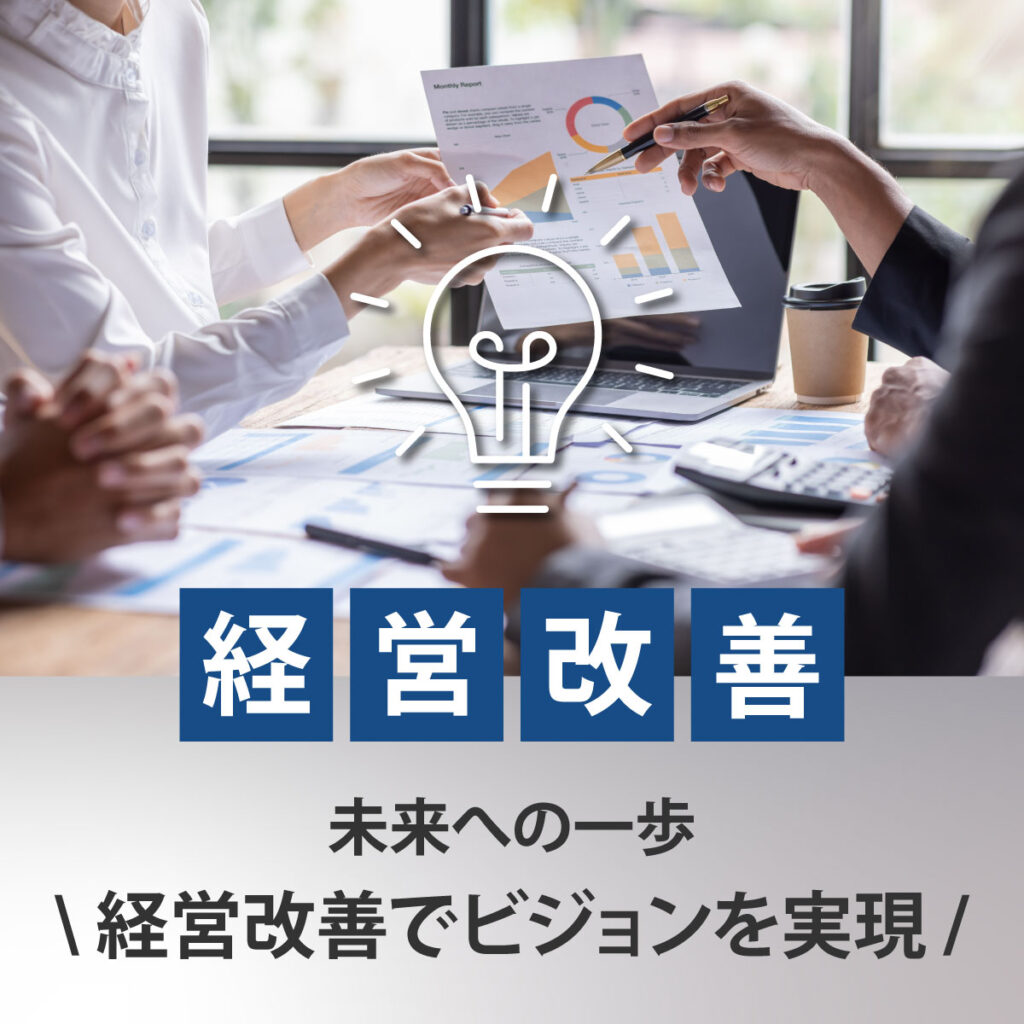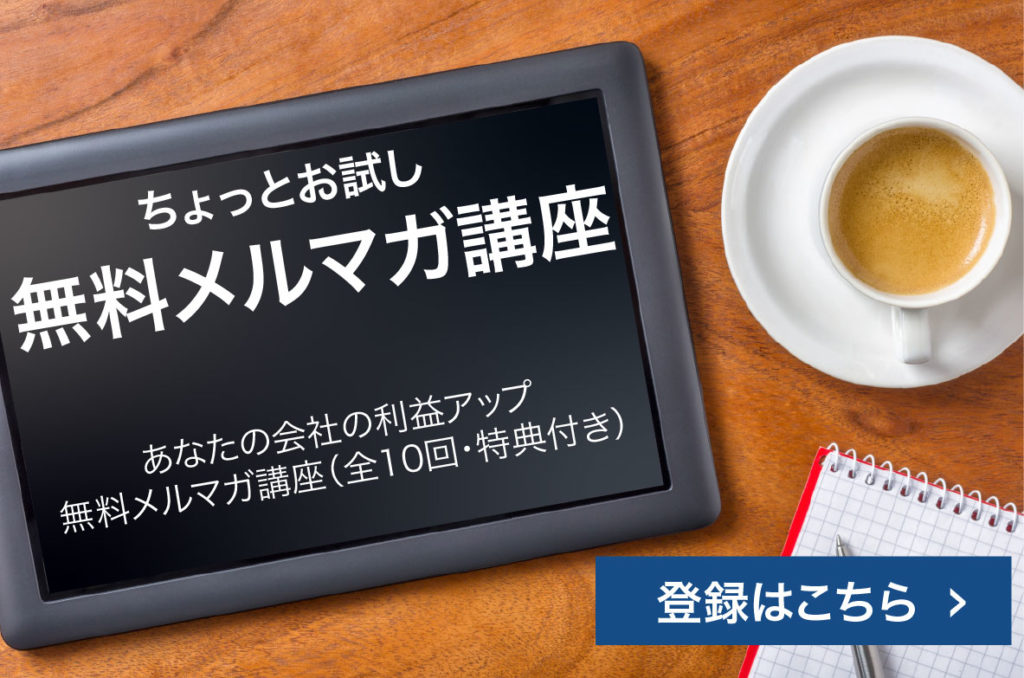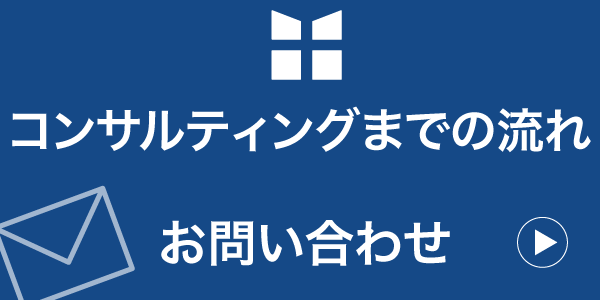中小企業の利益を3倍にする経営改善コンサルタント本田信輔です。
今回のテーマは「あなたの会社、給与アップの見込みはありますか?」です。
この問いかけは、従業員やスタッフさんの給与に限ったことではありません。経営者やオーナーの年収もアップできるかどうかということも含んでいます。
私は北海道の菓子屋の家に生まれ、コンサルタントとしても長年製菓業界に携わってきました。地方にある和菓子店、和洋併売店、スイーツショップ、パティスリー、洋菓子店など業態や扱う商品は違いますが、共通しているのは経営者やオーナー、頑張る従業員さんの成長を見ていると、それに見合う収入や給与アップをなんとか実現したいと思います。
そうなると製菓業の給与アップについて調べるわけですが、インターネットで「菓子店 収入」「パティシエ 給与」などと検索すると様々な情報が出てきます。
上位に上がってくるのは製菓専門学校のホームページなどで、パティシエの給与は他業界と比較して低いこと。もしも給与や年収を上げたいのであれば、技術を高めること、資格を取ること、有名菓子店や有名ホテルに勤めた経歴をつけること、独立してオーナーになること。挙げ句の果てに他のホームページによっては副業を推奨したり、転職支援サービスへ誘導するような内容が書かれています。
ですが根本となる“菓子店の経営”として給与アップや年収アップを実現するための内容は書かれていません。どれだけ技術や資格、経歴を持った人材であり、自身の収入を高めるために努力してきたとしても会社や店舗の経営が高い給与を払える体制を作っていなければ、従業員にも経営者にも高い給与を払うことができません。
だからこそ経営として、給与を高めていく取り組みをしていくことが大事だと考えています。
もちろん採用や安定雇用の面でも給与アップの必要性はどんどん増しています。
正社員さんの月給に限らず、パートさんの時給なども含め、給与を上げなければ人材確保・採用自体が難しいことが多くなりました。地方の菓子店では人が採用できないことで店舗の営業日を減らしたり、事業を存続させるために従業員の給与の方が社長よりも高いということも起きています。(オーナーや経営者が薄給で経営をしている状態)
今回の記事では地方の菓子店で給与アップをするために、経営者はどう考え、取り組んでいくかをお伝えします。
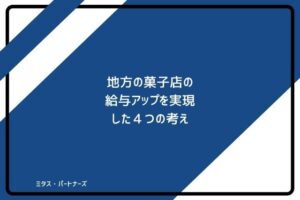
目次
0.こんな時でも最低賃金は上がる。全国平均で28円増ー2021年度
2021年7月厚生労働省の諮問機関は、2021年度の最低賃金を全国平均で28円アップさせ、930円とすることを決めました。28円のアップ幅は2002年に時給で示す現在の方式としては最大で、給与は3.1%になります。
時給で示す現在の方式になった2002年に663円だった平均賃金は2021年に930円に。約20年で267円も上がり50%以上も上昇しています。

(厚生労働省HPに掲載されている数値より)
菓子業に限らず、コロナ禍で経済が低迷しているのに、売上が上がらないのに経費は増える、労働時間は短くなり休日は増える・・・。そんな中でも給与を上げなくてはいけないのかと、特に中小企業の経営者にとっては不満を通り越して悲鳴・悲痛な状況にもなっています。
売上も利益も減っている中で、経営としてかなり厳しい状況が続いているという経営者やオーナーからの相談も増えています。
この給与水準は主要先進国の中では低い値ですし、業界として見ても、もっと給与を上げてあげたいと私も思います。
ですが経営者の気持ちとしては、国に決められて給与を上げろと言われるのは腹が立つし、それを従業員が当たり前と言う態度で示すことに不満と感じる方も多く。できれば経営を良くして、気持ちよく自発的に従業員の給与を上げてあげたいと願う経営者の方がほとんどと思います。
真に会社のことを考えてくれる従業員にとっても”会社は本当に大丈夫?”と言う不安にもつながりますので、会社としては給与アップの見込みを考えたり、従業員に伝えていくことも考える必要が出てきています。
さらに言えば、リスクを持ちながら経営をしている経営者やオーナーの給与もさらに高めていくことができなければ、将来の後継者や、自ら創業しようという次の世代にも暗い影を落とすこともあるでしょう。
まずは、経営者として給与アップのために何に取り組んだら良いでしょうか。
1.菓子業の給与は安すぎる。みんな給与アップを目指したいと思っている
はっきり言えば、菓子業界の給与水準は他業界と比較してかなり低いと言えます。
「業界の給与が低いのは昔から。そんなことわかっているよ」とか「中小の菓子店やケーキ屋・洋菓子店どうしても手作業に頼りがちだから」という声も伺いますが、まずは現状を確認します。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、パティシエ(洋生製造工)の初任給は月15万円〜18万円。年収でいうと約180〜220万円。ボーナスが出ても250万円にいくかどうかというところ。経験10年ほどで年収がようやく300万円に到達。50歳頃に年収400万円程度でピークを迎えます。
2020年の国税庁調査によれば日本人の平均年収は441万円と言われていますので、会社の規模や役職によって多少違うことはあるかと思いますが、他業界と比較して大きく低いといのが現状。業界の収入は東南アジアの国の平均年収と変わらない程度になっています。
初任給の時は低くて、一人前になれば給与は上がるということも世の中にはありますが、菓子業界の場合、経験を重ねれば上がる給与も、他業種と比較すると上限が低くなっています。
地方菓子店に焦点を当てれば、初年度の年収は200万円(月収14万円くらい)を切ることも多く、税金などを差し引かれると手取り12万〜14万になることも多くあります。
販売スタッフに至ってはさらに厳しく。バリバリ働き、会社にとって大きな貢献をしてくれるような30代女性店長でも基本給は15万円程度。役職手当などが加算されようやく20万円になるかどうかですし、経験を重ねても給与アップはわずかという会社も多くあります。
実家暮らしだったり、結婚してご主人と共稼ぎだったりすれば、十分に生活していけますが、男性で奥さんや子供などの家族が入れば、生活が成り立つかどうかも難しい水準で、子供を大学や専門学校に行かせようとすれば、自身の給与だけで生活が成り立たない可能性もあります。
働く立場からすれば、美味しいお菓子やパンを作り、お客様を笑顔にしたいと思いがあって入社してくれる人も多いと思いますが、それが一生の仕事とできるかどうか。家族を養うことを考えた場合には給与・年収という点で、あなたの会社では働き続けることを諦めたり、別の業界や仕事を選ばざるを得ない状況になっている。
経営者の方に話を伺っても、ほとんどの方が今が良いとは思っておらず。
なんとか従業員の給与アップを目指していきたいと取り組んでいます。売上が数千万もあるのに従業員に給与を払ったら、経営者自身の給与がパート並み(年収100万円台)というケースも見受けられます。
菓子業界の給与アップは従業員に限ったことではありません。経営者自身も頑張りに応じた収入を得ることが大事ですし、その姿を見て菓子業界の未来を背負う人材が出てくるためにも大事なテーマだと考えています。
2.給与アップのために経営者が考え、取り組むこと
実際、地方の菓子店で給与アップを実現している会社やお店が存在します。
地方に拠点があり、同規模の年商なのに給与アップを実現している会社があり、逆に従業員よりも安い給与で働かざるを得ない経営者の会社もある。
天国と地獄のような両極端のどちらになるか。あなたの会社はどうでしょうか。
もちろん。このブログを読んでくださる方には給与アップが実現できる会社やお店になって欲しいというのが本音です。
違いを生み出しているのは4つの考え方です。
(1)経営者の値づけ技術を高めること
経営者やオーナーが値づけの技術を高めること。
例えば。原価が120円かかるショートケーキを値づけするとした場合、
原価120円
A店:400円(原価率30%)
B店:500円(原価率24%)
どちらの値づけが上手でしょうか。
400円と500円。100円の差が値づけ技術の違いによって、同じ商品でも原価率は6%違う。
仮に全ての商品に対し値づけの技術が高ければ、会社全体の原価率は6%低くなり、粗利率は6%高くなります。
年商1億円の会社であれば600万円の利益差が生まれ、このうち3分の1にあたる200万円を人件費にまわすことができれば、従業員20名の会社で、社会保険等を考えないで単純に計算しても1人当たりの年収を10万円増やすことができる。(さらに、残りの400万円うちの2分の1を経営者の年収アップにできれば、年収ベースで200万近く増やすことができる)
そんなことをお伝えすると
「400円で売れるものを500円にするのが難しい」
と言われることもあります。
これを実現するのが値づけの技術を高めることと、次項で説明する人の技術なのです。
もしも給与を上げたいと考えるのであれば、経営者は値づけの技術を高めることは必須。
→今までの固定概念としてあった「ケーキの原価率は30%」や「原価の3倍で値づけする」「この地域の価格水準、競合と同じくらいの価格」などの古い考えを、給与アップを実現した経営者はとうの昔に捨てています。
→原価から考えるのではなく、自分たちの質とお客様が満足してもらえる価格をどこに設定するか。お客さんの目線で価格を設定する。
あとプラス10円、プラス50円、プラス100円。価格を上げるにはどうしたら良いかを考える。
これが経営者の値づけ技術を上げる第一歩です。
(2)人だからこそできる技術にお金をもらう
地方の菓子店で給与アップを実現した経営者は、人の技術に対してお金をいただく考えを持っています。
わかりやすく言えば「高くても、遠くても買ってもらえる人の技術です」
もともと菓子業は製造業なので、ものづくりに対する技術が評価される傾向にあります。そのため美味しく作る・早く作るなどの技術が上がることで給与が上がってきていましたが、世の中のお客様は変化しているので、ものづくりの技術だけではお金(高い価格)をもらえなくなっています。
どこでも美味しいものは作るし、原材料もこだわったものを使う。安かろうが質が悪ければ売れない。美味しく作るだけでは差別化できない時代なのです。
製造業として、同じ原材料でより美味しく作る技術は当然必要だと思います。
上記を前提とした上で、それ以外にも、
・買いたいと思わせるようなデザインの技術
・美味しそうと魅せるための写真撮影の技術
・接客力やサービス力、セールストークの技術
・ここで高い商品を買っても良いと判断させる現場の基礎的な整理整頓や清掃の技術
こういった人の技術を総合して、今のお客様は価格への妥当性をつけているのです。
「美味しいものを作っていれば売れる」と言われる方もいらっしゃいます。
残念ですが、今の世代の人たちは美味しさだけで判断できる舌を持ち合わせていません。見た目、接客力、販促物やWebで見る写真のクオリティを総合して“美味しい”とか、“買う価値がある”と判断しているのです。
先述した、ショートケーキ400円と500円の違いはここにあります。
・500円で売れるためのデザイン(カット、デコレーション、ネーミング)はどうするか?
・500円で買いたいと思わせる写真(レイアウト、角度、背景、照明)はどう撮るか?
・500円で買いたいと思わせる接客力(接客スタッフの対応力や気づく力、セールストーク、コピーライティング)はどうするか?
・500円のショートケーキを買うにふさわしいお店の整理整頓や清掃のレベルは?
こういった“人でなければできない技術”を高め、高くても買ってもらえるような経営をする。
そこに給与アップの要点があります。
例えば。これだけスマホが普及し、画像が当たり前になった今。
“美味しそうに魅せる写真をとる技術”はとても重要になってきました。正直、それらの写真を撮る技術は若い世代の人たちの方がはるかに上です。生まれた時からスマホが身近にあり、多種多彩な画像に接してきた経験があるからです。
そう考えれば、今までのように「美味しく作る技術が上がっていないから給与は上がらない」と一つの技術指標ではなく、各人の強みや長所、時には趣味や好きなことなども技術に活かしながら、会社全体で“高くても買いたい”高いなりの価値がある“を目指していく。
極端に言えば、原材料ではなく“人の技術”に払うウェイトを上げていく。
→原価率を5−10%下げるのは経営者の“値づけの技術”
→やじるそこで生み出された利益を人件費に加えていくために必要なのが会社全体の“人の技術”
これが給与アップに向けて必要になりますし、大手企業やコンビニに対して最も強い差別化要素になります。
(3)機械化による効率化・利益化から脱却する
前項の最後に書いた大手企業やコンビニとの差別化。これは“人の技術”による差別化ですが、もう一つは“機械化”からの脱却でもあります。
コンビニがスイーツ・菓子の領域に参入し、大きく変わったのは“機械で作るものは大手に勝てない”“販売がAIや機械に変わっている”という点です。
商品品質に関して、確かに“違い”はあるかもしれませんが“差”にはならない。
コンビニなりの美味しさというものが高まってきたためです(これは聞いた話ですが、大手コンビニには100名を超える試食担当がいて、開発された商品の品評を行なっているそうです)
その上でコンビニはAIによる販売の効率化を進めています。
そうなるとあとは大手企業と中小企業の資本力の差になるわけですが、これは勝ちようがない。機械で作り、AIが販売する商品であれば、あとは原材料と価格の勝負。規模が違うので差が出てしまう。
→今まで菓子業界は機械化による効率化を進めてきました。ですが、これからは機械化で効率化・利益化することは難しくなる。
中小規模の菓子店ほど機械化による生産性向上概念から脱却し、人の手・技術による製造・販売によって生き残る戦略の時代に入り、機械に投資するのであれば人に投資する。その中に給与アップも含まれています。
→大手の機械化やAI化に追従するのではなく、自社独自の機械やAIにはできない商品を作り、サービスをする。
特に規模が小さい菓子店・ケーキ屋さんほど重要な戦略になるでしょう。
商品構成に関しても見直す必要がでてきます。新しい視点で見ればスクラップした方が良い商品も出てきます。多品種生産ではなく、季節特化の商品構成へ移行する。アイテムを絞り込むことがプラスになることも増えています。
機械で作れることは中小の菓子企業にとってメリットはなくなり、機械製造を前提とした商品開発や重点強化商品を考えていく時代は終わりつつある。そこには給与アップに向かうチャンスが内包されていて、給与アップを実現した経営者はそのことにいち早く気づいています。
(4)修行前提、残業前提の給与体系はすでに終わり。
修行だから安い給与で良い。残業時間を前提として給与を設定している。
この発想を変えること。これが菓子業の給与アップにつながります。
まずは修行前提の発想。
将来は独立するから今は勉強のため。こういう理由で働く時代があったことは事実です。
オーナーシェフ型の洋菓子店が、素晴らしい原材料を使っているにも関わらず、それなりの価格で売ることができたのは、修行という名の低賃金・超労働時間という要因があったとも感じています。
実際、今、経営者やオーナーをされている多くの方が、そういった修行という名の働き方を経験されてきています。有名な和菓子屋や洋菓子店、老舗の菓子店では今でもそういう風潮があり、一時期は従業員のほとんどが修行のために働いているケースも見たことがあります。
その感覚が残っている。製造技術を学んでいる期間だから給与は安くなる。そんな風潮は未だに多くあります。
ですが働く人、特に若い世代の働き方に対する意識は大きく変わりました。
まずは本気で独立する気概を持ち、修行だと考えて働く人は減っている。会社やオーナーは修行だからと言っていて、聞いているフリをしているが本心ではそんなことを思っていない。逆にあまりリスクを負わず、そこそこに会社に属しながら働きたい若者が増えています。
今、独立をしようと考える人たちは、修行前提で働くことをベースとするのではなく、自身で様々に勉強して独自性を持ったお店や商品を作る。修行して技術を身につけて独立することはすでにオワコン(すでに終わったコンテンツ・方法)となりつつあります。残っているのは菓子企業の後継者が、勉強のために修行として働くくらいです。
そんな若者にとって修行前提が通じません。当然、給与が低ければ早い段階で会社に見切りをつけるか、求人募集にもかかってもきません。
「若いんだから。経験も浅くて、技術がないよ!」というのは、製造技術が全てという過去の発想。年齢が若くても、製造技術だけではなく、各人の特性を生かした“強みを生かした技術”を評価して、会社やお店で活かすことで給与水準を上げていく発想への転換が必要になっています。
菓子業だけじゃないけれど・・・やりがい搾取という言葉は悲しい。
もう一つは残業前提をやめること。
残業代が給与の前提になっていたり、そもそもサービス残業が多かった業種としても菓子業界は挙げられています。
繁忙期になれば残業は当たり前。だから残業込みで年収を設定している。この発想は捨てた方が良い。
働きがいがあるとか、やりがいがあるとか。菓子業は確かに夢のある仕事です。多くの方に喜んでもらえます。だからこそ、働きたいと思う人も多いです。ですが“やりがい”と“残業前提”を同じ土俵で考えるのは難しい。
手作りで、手間をかけて、そこそこのお値段で提供するから、お客さんに喜んでもらえる。お客さんに喜んでもらえるから働く時間が長くなってもしょうがない。という考えを変えていく。菓子業でやりがい搾取というような言い方をされることは悲しいです。
繁忙期だからしょうがないという考えもやり方次第で変えられます。
繁忙期の記憶として覚えているのはクリスマス。私が学生の頃、実家の菓子屋はクリスマスになると毎年夜遅くまで残業をしていました。時には家族総出で手伝いをしたこともあります。今となっては良い思い出ですが、やはり今の時代には沿わない。世の中全体としても残業を減らす風潮が進んでいます。
給与アップに成功した経営者はお客さんに喜んでもらいながら、繁忙期であっても、どうやって残業せずに利益を出すかを真剣に考えています。バースデーケーキやクリスマスケーキを全て予約限定にする。一つ一つの商品でちゃんと利益を出せる値づけをして、製造個数・販売個数が少なくなっても今以上の利益を出せるようにする。そうする取り組みで給与アップや時給アップを実現しています。
以前に私が勤めていたコンサルティング会社では、残業するのは力がない。仕事のスピードが遅いからという風潮がありました。菓子業でも同じことがあるのではと感じることもあります。
もちろん個々人の仕事のスピードをあげることも大事です。ですが同じくらい会社の経営として“少ない時間でより大きな利益を上げる”取り組みをすることが必要。
そのことをわかっている経営者は新たな取り組みをはじめ、成果を出しています。
3.菓子店経営と給与アップについて
今後、人口はますます減っていきます。日本全体で年間50万人近くが減っています。
高齢化も進み、様々な仕事の自動化・AI化が進むでしょう、そのとき中小企業の菓子店はどのように生き残っていくのか。
機械やAIを使うとなれば間違いなく大手企業との競争になり、資本力で劣る中小企業は生き残る道がどんどん狭まってきます。
中小菓子店の生き残りを考えれば、機械ではなく“経営者・従業員、双方の人の力”に軸足をおいた経営を目指し、商品開発やサービスで差別化していくことが必須になると考えています。
その時の重要な要素の一つとなるのが“給与・収入”。何度も言いますが、この中には経営者のぶんも含まれています。
さらに言えば、給与や収入が仕事を選択する一つの指標であるとすれば、他業界よりも低い給与水準の菓子店は人材不足になることが目に見えています。
お菓子を作る楽しさ、お客様に喜んでもらえる仕事など、菓子店の仕事は魅力的で夢があります。
その一方で働く、生活していく、家族を養うと考えた時、収入という面が菓子業に関わる人の夢や将来を暗いものにしていることも事実として認識しています。
菓子店で働く各人の成長。
これはもちろん大事。
でもそれと同じくらい、経営として給与アップを目指す取り組みも大事です。
あなたの会社やお店はいかがですか?
給与が上がらない理由を個々人の成長や働き方のせいにしていませんか?
従業員の“働き方”は変わり、菓子店で必要とされる“技術”の領域は広がっています。
まずは、経営者自身の考えを変えていくことが給与アップにつながります。
給与アップを実現した経営者が考えている4つのこと。
あなた自身の考えとどこが違いましたか?
・経営者自身が値づけの技術を高める。
・人だからこそできる技術でお金をいただく
・機械化からの脱却
・修行前提、残業前提の給与は終わり
給与アップを目指したいのであれば、ぜひ今回の記事を参考に経営を考えてみてください。あなたの会社のため、あなたの会社で働く人たちのため、業界のため、あなた自身や家族のためになります。
お気軽にご相談ください
弊社ではこれまで開業してから約400件のご相談を承り、そのうち約200件を超える企業・事業者さんのご支援を行いました。もしお困りのことがございましたら、お力になれる点があるかと思いますので、お気軽にご連絡ください。
=PR=
【無料メルマガ講座】こんな時こそ勉強しよう!無料で学べるあなたの会社の利益アップ実践策