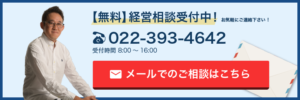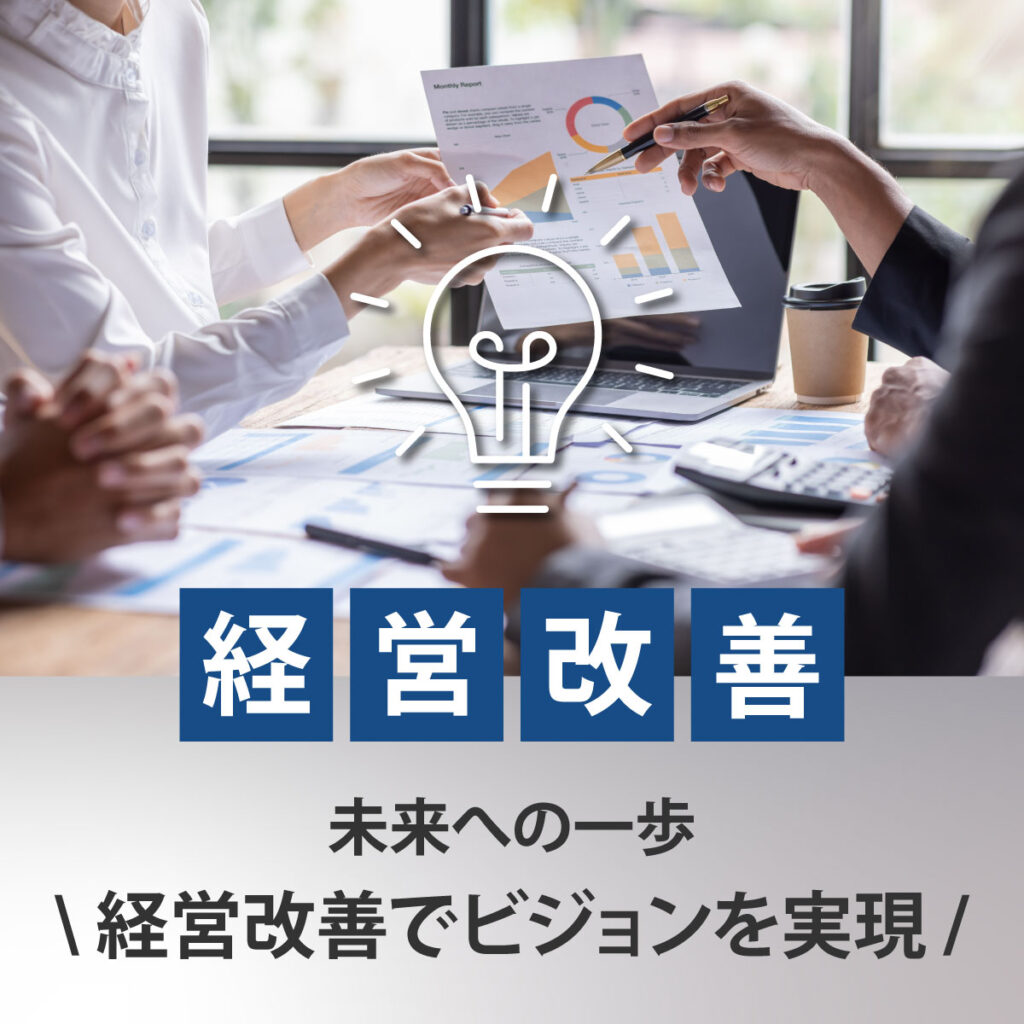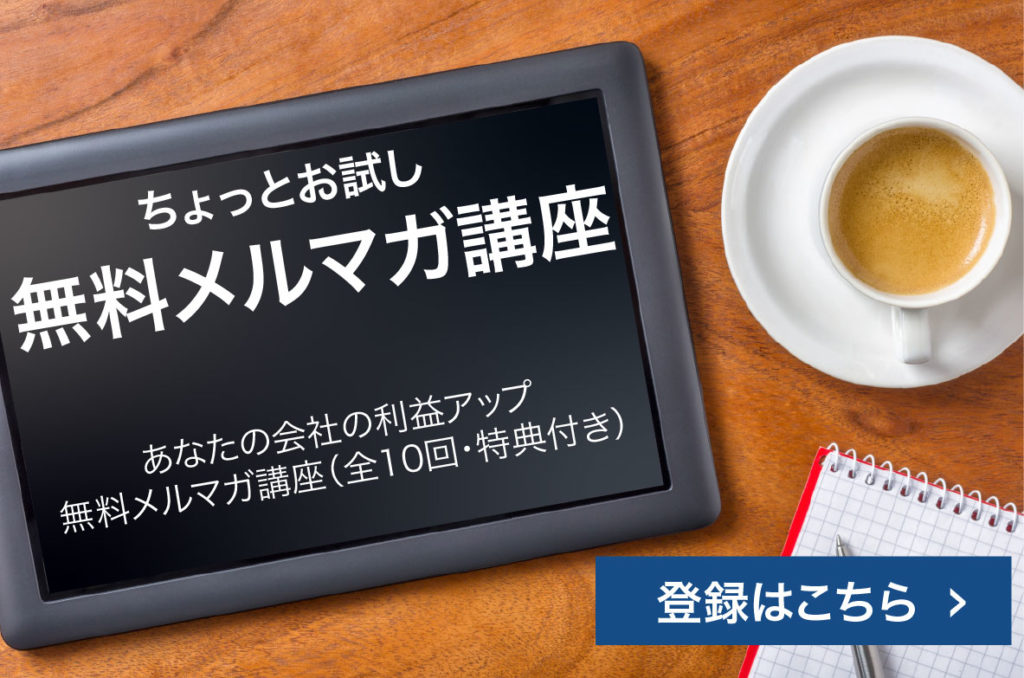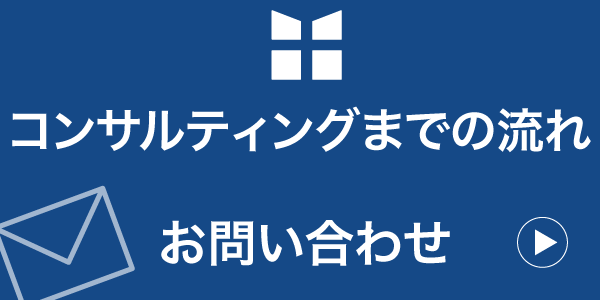利益を3倍にする経営改善コンサルタント 本田信輔です。
前回の経営改善とは何をすること?会社を立て直す秘訣に続く内容。
今回のテーマは経営改善を成功させる4つのポイントをお伝えします。
経営改善は大小・業種関係なく多くの企業・会社で取り組んでいます。
ですが。。。なかなかうまくいかない会社が多い。
・自分たちでやろうとしたら、より良い方向へ変えられなかった。
・思ったほどの成果が出なかった。
・銀行や会計事務所など、外部からの声だけがプレッシャーになった。
・どうして良いかわからず、頓挫した。
経営改善の第一は業績が上がること。
さらに言えば、経営者も従業員も成果が出た!と実感できること。
かかった苦労に対する見返りもそうですし、今後の改善に対するモチベーションにもつながるため、目に見える成果がでる。ということは非常に大事なことです。
では経営改善で成功している企業の共通点はどこにあるか。
確実に押さえておいて欲しいポイント4つにまとめています。
目次
1.経営改善は未来のためにするもの。理想像と現実の間をつなぐこと
ほとんどの会社の場合、経営改善の第一目標は業績を改善させることにあります。
売上を上げる、利益を増やす。財務状況が改善する。
これはほとんどのケース間違いありません。
ですが失敗する会社がある。
原因は大きな問題は“業績が上がった後、どうしたいのか?”がないこと。
単に売上や利益を改善させることがゴールではなく、その先にある目的や将来像は何かが示されていないことです。
経営改善がうまくいかない。なんとなく一時しのぎ的なカタチになってしまう。
その原因は将来像が設定されていないから。
経営者自身が、現場や従業員に対して「こうなりたいから、改善を進めいく(業績を上げていく)」という理由が説明できないからです。
将来像というと、なんとなく先の話のように捉える方もいらっしゃいます。今が厳しいのに「5年後・10年後のことなんか考えられない。目先が大事だ」という経営者もいらっしゃいます。
確かに目先の業績を改善させなければならない状況がある場合もあります。
ですが将来というのは、1年後・5年後・10年後、そして何と言っても大事なのは経営者が、自分の会社を将来的にどのような会社にしたいか。理想に近いものです。
売上や利益といった目標数字の先にある理想像、
自分たちの会社は何を強みにして、お客さんに何を支持されて。
価格訴求型なのか、価値訴求型なのか?
従業員にどのような働き方で、どれくらいの給与にしてあげたいのか?
漠然としたものでも良いから、経営者がこれを目指すからこそ、経営に全力投球できるというイメージ(将来の理想像)を作らなければ、効果的な経営改善はできません。
この理想像を作ることで、行き当たりばったりの計画にならず、より効果的で発展的で成果を最も出せる方法論を選択することができます。
逆に言えば。
将来像を描くことなく、今が苦しい状況で間違った方向や、非効率的な経営改善を選択してしまうと、会社を立て直すどころか、衰退・廃業へ向かうこともあります。
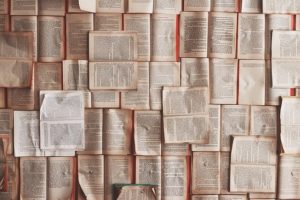
2.課題の抽出は、将来像を描いてからがベスト。
経営改善で失敗しやすいのは、課題の抽出を先にやってしまうケース。
課題を出してから解決法を。というのは間違いないのですが、
将来像を描かずに、課題を抽出してしまうと。
“あれもこれも、課題がたくさん!”に陥ってしまいます。
特に現状の経営が苦しい社長は、マイナス志向になりがち。自分の会社のマイナス部分・課題をどんどん見てしまい、
“これだけ改善することあるのか・・・”と絶望し、改善を諦めてしまうケースがあります。
まずは将来像を作り上げてみる。そうすると、色々な課題がある中でも
・どこから改善したら良いか優先順位が決まる
・短期的に改善するものと、時間をかけて改善で良いものが見えてくる
ことで、改善に対する力を集中し、余分な負担を軽減することができます。
経営書には、スワット分析など●●分析法などが多くありますが、使わなくても十分に課題を抽出することもできるのです。(それだけで経営者の心身に対する負担が減りますね!)
改善には、時間も、気持ちも、コストもかかってきます。
改善を要求する銀行や会計事務所は、そこがわからない時もあり「とにかく改善してください!」と改善可能性があるところ(例えば、コスト削減項目など)を次々と伝えてくるでしょう。
ですが、中小企業だからこそ一気には改善できない。
そのストレスが改善を停滞させてしまう要因になるのです。
まずはどこから手をつけていくか。改善していくかを決める。
自分の会社はどこに向かって進んでいきたいのか?
中小企業として生き残っていくための企業戦略は?
こういった議論を行い、明確にしていくことが遠回りのようで。結果としては正しく、効果的な改善を進めるためのポイントです。
自分の会社の将来像、中小企業としての生き残り戦略は外部と話し合うことで解決しやすい傾向があります。多くの経営者は、自分である程度の考えを持っていても、それを表現するところ・言葉や文章にすることを苦手としています。自分の思いを理解し、経営戦略的な立場でブラッシュアップしてくれる存在を見つけることが大事になってきます。
3.最初に動くのは経営者。経営改善の本質を見失わない。
経営コンサルタントとして様々な会社の経営改善に関わり、時には思ったほどの成果が十分に出なかったという失敗経験も踏まえてお伝えすれば、
経営改善をする時に、大事なのは。
改善を最初に、先頭きって行うのは“経営”(経営者)であるということ。
逆にやってはいけないのは、現場の改善を第一にしてしまうことです。
もしも経営改善の第一に現場改善を挙げてしまえば、現場や従業員は経営に対し、不信感と不満を持ちます。従業員にとっては、「経営が悪いのは自分たち」と経営者に言われたからも同然だからです。当然、改善に対するモチベーションは上がりません。
改善をより効果的に進めたいと思うのであれば、まず経営者が動くこと。経営者が動いて成果を見せることが、現場の経営者に対する信頼感、さらには改善モチベーションに繋がります。
私どもミタス・パートナーズの経営改善事例で多いのは、
まず経営者ができること
・顧客設定と価格戦略(値づけ)を見直し、会社の利益性を改善させる
・会社の原材料の中で、最も使用量が多い(仕入れ金額の大きい)ものを経営者自身が直接仕入れ価格の交渉する
などを行います。
経営改善を考える時は、まず経営者ができること。
正確に言えば、経営者でなければできないことに取り組むこと。
これを第一に置くことを前提にする。
実際、経営者しかできないところを改善した方が、成果が出るスピードも早く、効果も大きいことがほとんどです。
4.経営改善は動かなければ意味がない
当たり前のことですが、経営改善は具体的な行動に移さなければ成果には繋がりません。
コンサルタントや専門業者に依頼して、コストをかけて経営改善計画書を作成しても、銀行などの金融機関は満足するかもしれませんが、結局のところ具体化・行動化しなければ意味がありません。
経営者にしても、計画を作ってなんとなく安心してしまったり、計画を作ることで気力・体力を使い果たしてしまう場合もあります。
そのようなケースを見ていると、経営改善計画書を作るということに固執する必要はないと考えていますし、実際に私どものクライアントで計画書なしでも、十分に経営改善している中小企業が多く存在します。
大事なことは行動化・具体化することです。
経営改善の行動をとることで、売上が変わり、利益が増減し、社内の組織風土なども変化していく。行動の結果が、会社数値の動きとして出てくるわけです。
どんなに立派な経営改善計画書があっても、その中に素晴らしいアイデアや発想があっても、動かなければ意味がありません。
一気に新しいことへ取り組むことに不安がある経営者もいらっしゃいます。改善をしなければならない時点で既にリスクが生まれているのですが、新しいことへのリスクも考えてしまう。
そのような場合は小さくても良いからチャレンジして見ることもアリと考えます。
例えば、実際にあったケース。
値上げをすることへの不安を感じていた経営者の場合。いきなり、定番商品の価格を上げることに不安を感じていたので、毎年定番の季節催事イベントを今までとは違うコンセプトで実施してみようということに。今までは品揃え型・値引き型中心の企画だったものを、単品訴求型・高単価限定商品型の企画へとテスト的にチャレンジすることになりました。
結果は今までよりも大きく売上・利益が伸び、今まで値上げに反対姿勢だった経営幹部も変わり、現場の手応えも感じられる結果となった。
経営者にしてみれば、新しい方向性がなんとなくうまくいく実感も得られたし、経営幹部の反対や現場の自信も実感することができ、その後の定番商品全体の値上げをすることができた。
よくPDCA(PLAN DO CHECK ACTION)が大事と言われますが、これは大きなことではありません。まずはちょっとでも良いからやって見る。
できない理由をたくさん並べ、難しく考えすぎているうちに、どんどん会社の状況は悪化していきます。
計画を立てたにもかかわらず、行動が伴わない場合、意外と目先の行動が抜けているケースが考えられます。
5.中小企業の経営改善を効果的に進める4つのポイントまとめ
中小企業には、中小企業だからこその経営改善があります。
それは経営書にも書かれていないことも多くあります。書いてあってもやたらと難しい言葉や英語で書かれていて、中小企業の経営者にとってはイマイチ理解しづらいこともしばしば。
シンプルに考えることを大事にしてください。
①将来の理想像を作り、それから経営改善の方向性を決める
②課題の抽出は、将来像を組み立ててから行う
③経営者ができることを改善の第一として考える
④ちょっとでも良いから、新しいチャレンジ・行動できることを組み入れる
経営改善の成果が出ない時は、4つのポイントのどこかが抜けている。
逆に4つのポイントをしっかりと抑えて改善が進めば、経営は必ず改善していきます。
利益が出る。資金繰りが楽になる。従業員が明るく仕事をしてくれる。自分の夢や理想に近づいている実感。世の中の役立ちにつながっている実感。
経営改善が、より良い方向に向かえるように。
抑えておいてほしいポイントです。
=PR=